壊れかけの勝利
今回の試合が、メディアにどう描かれるか——
それを、九条は想像していなかった。
あるいは、想像する余裕もなかった。
周囲の心配をよそに、アスリートとしての動きは完璧だった。
反応速度、コントロール、集中力。
どれを取っても、今季最高のコンディション。
結果だけ見れば、圧倒的な勝利だった。
コート上での九条は、機械のように正確で、容赦がなかった。
わずかな隙も逃さず、観客が息を呑むたびに、淡々とポイントを積み上げていく。
ガブリエルのアクロバティックなプレーをもってしても、その流れを止めることはできなかった。
まるで、完璧さの暴力だった。
——だが、ロッカールームで座り込む姿を見た者は、誰もそうは言わないだろう。
蓮見たちは、選手としての“強さ”の裏にある危うさを見ていた。
あの集中は、尋常ではなかった。
極限を超えていた。
「勝ち方としては理想だ。だが、あの状態で続けてたら……」
と、神崎が小さく呟いた。
蓮見は腕を組んで、深く息を吐く。
「メディアは“圧勝”って書くだろうな。でも、現場で見てた俺たちは分かる。あれは、“壊れかけの勝利”だ。」
氷川が画面を見つめながら、静かに言った。
「ニュースの速報、もう出てます。“氷の王、マイアミ4回戦を圧勝。無表情のままベテランを沈める”」
蓮見が苦笑する。
「……だろうな。実際には、無表情どころか、魂抜けてたけどな。」
九条はタオルを膝の上に置いたまま、
その言葉には反応しなかった。
勝利の実感も、達成感もない。
ただ、静かだった。
それでも、選手としての“動き”は完璧だった。
強かった。
圧倒的だった。
——そして、どこか壊れかけていた。
沈黙の会見
メディアセンターの照明は、コートとは違う人工的な白さだった。
冷気の効いた空気の中、九条は無表情のまま席に着く。
背後のパネルにはスポンサーのロゴ。
マイクが三本、机の上に並んでいる。そのひとつが九条の前に向けられた。
記者が最初の質問を投げる。
「圧勝でしたね。ご自身のプレーをどう評価しますか?」
九条は、短く答える。
「悪くない。」
会場に小さな笑いが起きる。
だが、彼の表情は動かない。
別の記者がすぐに続ける。
「途中、完全に“ゾーン”に入っていたように見えました。音が全く聞こえないほどの集中状態だったと、一部では言われています。」
九条は一瞬だけ目を伏せ、「……覚えていない。」とだけ言った。
次の質問。
「ガブリエル選手が試合後、あなたを“最も静かな嵐”と表現していました。どう受け止めますか?」
九条の瞳が、わずかに動く。
「嵐は、何かを壊すために吹くものじゃない。通り過ぎたあと、何が残るかが大事だ。」
会場が静まり返る。
表情のない横顔に、ライトの白が落ちていた。
最後の質問が飛ぶ。
「この勝利で準々決勝進出です。次の試合に向けて、何か一言ありますか?」
九条は少しだけマイクを近づけた。
「……試合をするだけだ。」
言葉が終わる。
記者のペンが一斉に動く。
その瞬間、背後のカメラシャッターが連続で切られた。
画面の中では、
“氷の王、圧勝後も沈黙。ゾーン状態の真相語らず”
という見出しが、数時間後には世界を回ることになる。
だが、九条自身はまだ、あの深海のような静寂の中に片足を残したままだった。
呼吸を取り戻す場所
控室のドアを閉めると、外の喧騒が一気に遠のいた。
冷気の効いた空気の中、九条は深く息を吐く。
氷川が手にしていたiPhoneを差し出した。
「通知がありました。」
それだけ言って、静かに背を向けて去っていく。
画面には、澪からのメッセージ。
勝利おめでとう!…元気?怪我してない?
ウィジェットを開くと、日本時間は昼過ぎ。
きっとネットで勝敗を知ったのだろう。
会場の熱気が嘘のように、手の中のデバイスだけが現実に引き戻してくる。
九条は短く入力した。
問題ない。
送信を押す。
ほんの数秒後、バイブレーションが震えた。
問題あるでしょ。
その一文に、かすかに眉が動く。
間髪を入れず、もう一通。
雅臣さんがそれ言うとき、説明するのめんどくさくなってる時。
そこまで読んで、思わず息が漏れた。
笑ったのか、ため息なのか自分でもわからない。
指先が止まる。喉の奥で言葉にならない感情が渦を巻く。
それでも、短く返す。
ちゃんと生きてる。
数秒の間。画面の上に、“既読”の文字が灯る。
そしてすぐに、返信がきた。
よかった。
ちゃんと息してね。
その言葉を見た瞬間、九条はスマートフォンをゆっくりと伏せた。
さっき、ガブリエルにも同じことを言われた。
“息してなかったぞ”と。
目を閉じる。
呼吸を整える。
肺が動き、空気が入る音が、ようやく“生きている”という実感を連れてきた。
(……息、してる。)
小さくそう呟いて、
九条はタオルで顔を拭いた。
試合の熱も、深海の静寂も、
ようやく身体の外に出ていくようだった。
届かない心配
澪は朝、コーヒーを片手にデスクの前に座る。
まだ社内は静かで、オフィスの空気は澄んでいる。
習慣のようにニュースアプリを開くと、
「Miami Open 2025 — The Fourth Round」
という文字が目に入った。
試合スケジュールを確認すると、九条の試合は現地時間の夜。
日本ではちょうど、出勤中から午前の会議が始まるころ。
——見られない。
少しだけ残念に思う。
だが、仕方ない。彼は戦う人、自分は働く人。
違う場所で、それぞれの“日常”を生きている。
昼休憩。
ようやくスマホを手に取る。
ニュースフィードの上に、九条の名前が躍っていた。
『九条雅臣、モレーノにストレート勝利。マイアミ8強へ』
——勝った。
胸の奥が少しだけ熱くなる。
けれど、記事を読み進めるうちに、眉が寄った。
『深いゾーンに入っているように見えた』
『完璧な勝利』
『マシンのよう』
その言葉に、記憶がざらりと逆流する。
全豪オープン決勝。あの、異様な静寂。人間とは思えない集中。
目線は鋭いのに、何も見ていない目。
打つたびに、世界が遠のいていくようなあの姿。
画面を見つめながら、気づけば自分の呼吸が浅くなっていた。
(また、あの状態まで行ったの……?)
小さく呟く。誰もいない休憩室。
昼の陽が差し込む窓の下で、澪はスマートフォンを見つめていた。
勝って嬉しいのに、何故か胸がざわつく。
その答えを探すように、澪は深く息を吸い込んだ。
問題ない
短いその文字が、画面の中央で静かに光っている。
——問題、あるでしょ。
そう返した自分のメッセージが、あまりにも軽く見えて、小さな後悔が胸の奥に沈む。
(ゾーンに入るサイクル、早くなってる気がする……)
以前、チーム九条のメンバーが言っていた。
「あの状態はそう簡単には入らない。むしろ、長く続ける方が危ない」
けれど、最近の彼は違うように思う。
明らかに、入り方を覚えてしまったように見える。
深く、速く。
そして、誰も追いつけない場所まで。
それが“進化”なのか、“摩耗”なのか、澪には分からない。
ただ、あれを見てしまうと、胸の奥がひどく冷たくなる。
(本人が止めようとしてないのか、入るコツを掴んでしまったのか……)
どちらにしても、あの静けさは、人間のものじゃない。
スマートフォンの画面を見つめたまま、自分の指先に力が入る。
——心配してる。
でも、言えない。自分は“部外者”だ。
彼の内側に踏み込む資格なんてない。
「口出しするな。何様のつもりだ」
そう思われるのが怖いわけじゃない。
ただ、彼の“集中”を、自分の感情で乱してしまうことが怖かった。
(……本当に、問題ないと思ってるの?)
その問いは、文字にはならなかった。
ただ心の奥で、誰にも届かないまま、深く沈んでいった。
勝つために失われたもの
夜のマイアミは、湿った風がガラスを震わせていた。
ホテルの一室を借りた会議室では、照明が少し落とされ、スクリーンの光だけが壁に滲んでいる。
海風に混じる塩の匂いと、MacBookの微かな音。
チーム九条の夜は、静かに始まっていた。
テーブルの上にはタブレット、戦績データ、コート分析。
空調の低い唸りだけが、静かに響いていた。
蓮見が映像を止める。
スクリーンには、イーライ・コーヴァンのプレー映像。
高速サーブからのフォアハンド、観客が湧く瞬間。
「次はイーライ・コーヴァンだ。いま大会で一番注目されてる若手だな。世界ランク12位。勢いがある。」
氷川が補足するようにデータを読む。
「今季はツアー3勝。グラス、クレー、ハード全部で結果を出しています。メディアでは“新世代の象徴”と扱われてます。観客の人気も非常に高い。」
九条は無言で画面を見つめている。
映像の中のイーライは、躍動していた。
跳ねるようなフットワーク。感情を隠さず笑い、拳を突き上げる。
会場が一体になるのがわかる。会議室のスクリーンに映し出されたのは、イーライ・コーヴァンの最新試合。
明るい照明の下、若い選手が笑いながら走り、打ち、跳ぶ。
観客の歓声が、映像越しにも熱を帯びて伝わってくる。
九条が短く呟いた。
「……派手だな。」
早瀬がタブレットに視線を落としたまま答える。
「ただの派手じゃありません。動作の始動が非常に早い。身体の反応が感覚的です。理屈ではなく、勘で打ってるタイプですね。」
その言葉に、理学療法士の早瀬が付け加えた。
「リズムでプレーする選手です。相手のテンポを読む力がある。」
氷川が手元のキーボードを叩きながら、冷静に続けた。
「九条さんへのコメントも出ています。“憧れている。でも、いつか倒したい相手”と。」
蓮見が小さく笑い、腕を組んだ。
「まあ、倒したいだろうな。誰もが思う。」
沈黙が落ちる。
スクリーンの映像は、イーライが勝利ポーズを取る瞬間で止まっていた。
九条の視線だけが、そこに釘付けになっている。
「……観客を味方につけるのが上手い。」
「ええ。試合の雰囲気を作るのが巧みです。あのスタイルは心理的にも影響が大きい。」
「彼は観客を巻き込む。歓声の波を自分のリズムに変える。あの“ノイズ”を心拍のように使っている。」
氷川が頷く。
「分析でも、彼の集中力は歓声のボリュームと連動してます。静寂よりも、熱狂の中でプレー精度が上がるタイプです。」
「……つまり、真逆ってことか」
蓮見が言った。
「お前は“世界が静かな方がいい”ってタイプだもんな。」
九条は応えない。
ただ、スクリーンの中で拳を突き上げるイーライの姿を見つめていた。
その笑顔はまっすぐで、眩しいほどだった。
氷川が画面を切り替える。
「オッズも出ています。九条さんが1.4倍。イーライは2.8倍。ただ……賭け金の総額は拮抗しています。イーライに賭けている観客が多いです。」
蓮見が鼻を鳴らす。
「つまり、負けたら荒れるってことか。いい年した奴らが、金の腹いせに若い選手を叩く。」
「それで人生が変わると思ってる時点で、終わってる。」
九条の声は低く静かだった。
「賭けたのは自分。受け入れられないのは未熟さだ。他人を罵ることでしか現実を処理できない奴は、愚かだ。」
志水がタブレットを閉じながら、わずかに笑った。
「……今日も切れ味がいいですね。」
「本当にインタビューでそれ言うなよ。氷川が倒れる」
蓮見の声に、少しだけ笑いが混じった。
だが九条の瞳は笑っていない。
光を吸い込むように、ただ静かに光っていた。
(俺に向けられるならいい。だが、あの若い選手に向けられるなら――)
一瞬、胸の奥に熱が滲む。窓ガラスに映る自分の顔は、無表情だった。
夜の街の明かりだけが、その輪郭を薄く照らしていた。
蓮見が椅子の背にもたれかかり、腕を組む。
「しっかし……お前がクールなのに対して、情熱的な選手が多いから、何かと“氷と炎”とか、“北風と太陽”とか、そういう描かれ方しがちだよな」
豪快に笑いながら言うその声が、重かった会議の空気を一瞬だけほぐした。
「この場合は、北風が勝っていますね」
氷川がメガネのブリッジを指で押し上げ、キーボードを軽く叩いた。
ブルーライトカットのレンズが青く光る。
「安直な書き方しかできないんでしょう」
早瀬がタブレットを見たまま、淡々とApple Pencilを走らせた。
蓮見が吹き出す。
「お前もなかなか切れ味鋭いな」
「事実です」
早瀬は顔を上げずに答えた。
九条はそのやり取りを黙って聞いていた。
ほんの一瞬、口元の筋肉が動く。
笑いかけるでもなく、ただ“人の会話の温度”を感じているような表情だった。
その微細な変化を、志水だけが見逃さなかった。
彼は何も言わず、ただ目の奥で少しだけ安堵の色を浮かべた。
スクリーンに映るのは、明日の対戦相手——イーライ・コーヴァンの映像。
画面の向こうの若者は笑いながら、観客に手を振っている。
(氷と炎、か……)
九条の脳裏に、蓮見の言葉が残っていた。
その対比が、明日のコートでどんな形になるのか。
彼自身も、少しだけ興味を覚えていた。
「というか、九条さんが相手なら、誰でも感情的な選手ですよ」
氷川が淡々と告げた。
会議室にいた全員の動きが、一瞬止まる。
蓮見が眉を上げた。
「おい、それ、ちょっとディスってないか?」
氷川はキーボードから手を離しもせず、静かに返す。
「いえ。単なる比較の話です。」
早瀬がペンを走らせながら、わずかに口角を上げた。
「確かに。普通の選手なら、感情を表に出して戦うのが自然ですから。」
「……つまり俺が異常だと?」
九条が低く呟いた。表情は変わらない。氷川は顔を上げず、短く答えた。
「はい。異常なほど冷静です。」
室内に静寂が落ちる。
蓮見がわざとらしく頭をかく。
「フォローの仕方があるだろ……」
だが、九条は微動だにしない。
むしろその言葉を、事実として受け止めているようだった。
(他の選手が感情的で熱いわけじゃない。自分に“人間らしい温度”が無さすぎるだけだ。)
彼はそう理解していた。
だが、それを改める気もなかった。
感情は揺らぎ。
揺らぐ者は、勝ち続けられない。
九条は、わずかに首を傾けて言った。
「……問題ない。氷川の言う通りだ。」
その声には、皮肉も怒りもない。
ただ、氷のように研ぎ澄まされた静けさだけがあった。
誰もそれ以上、何も言えなかった。
「気持ちは冷静でも、身体には負担がかかるんだから、あまり無茶はしないでくれよ。」
神崎の声は穏やかだったが、その奥には切実さがあった。
彼はチームメンバーとしてというより、一人の医師として言っている。
九条の身体が、常人とは違うリズムで削られていることを、誰より理解していた。
九条は椅子に深く座り、視線をスクリーンから外さずに答える。
「検討する。」
短く、それだけ。
神崎が小さくため息をつく。
「……“検討する”って、それは“やる”とも“やめる”とも言ってないぞ。」
「だから検討する。」
その声は、冷たさではなく、淡々とした誠実さに近かった。
彼にとっては、それが最大限の譲歩でもある。
蓮見が肩をすくめて笑う。
「お前、ほんとに“わかった”って言わねぇよな。」
九条は何も返さない。
「全然熱くならねーのに、勝つことには意欲的だよな。」
蓮見が笑いながら言う。
軽口のようでいて、どこか本音が混じっていた。
九条はタオルで手を拭い、静かに答える。
「勝つために、こうなった。」
蓮見が眉を上げる。
「熱くなれなくなった、じゃなくて?」
「違う。熱くなっても勝てない。だから、捨てた。」
会議室の空気が、わずかに沈む。
誰も笑わない。
ただ、九条の声だけが冷たく響いた。
「感情で勝てるなら、誰も苦労しない。」
氷川がわずかに視線を落とす。
神崎も言葉を挟まなかった。
それは諦念ではなく、研ぎ澄まされた選択の音だった。
人間らしさを削ってでも、勝ち続けるための、静かな代償。
イーライ・コーヴァン(Eli Corvan)
あの人の目には、風が吹かない。
コートに立った瞬間、誰も入り込めない“無風地帯”ができる。
観客の声も、相手の息遣いも、何も届かない。
彼は、ただそこに立ち、世界を制する。
俺は、それを初めて見た時、恐ろしくて、同時に見惚れた。
あんな静けさの中で、人はどうして呼吸ができるんだろう。
どうして、孤独でいられるんだろう。
俺の中では、いつも音がしている。
心臓の音、観客の声、風がコートを抜ける音。
それら全部が、俺を動かしてくれる。
でも九条は、それを全部切り捨てているように見える。
「完璧だ」
誰もがそう言う。
確かに、彼のテニスは答えそのものだ。
無駄がなく、感情もない。
すべての球が“正解”として打ち出されている。
でも、俺は——あの正確さの中に、何か大事なものが抜け落ちている気がしてならない。
たぶん、“鼓動”だ。
生きてる音。
人間である証みたいなもの。
あの人は、それを犠牲にして頂点に立った。
けれど、俺は違う道を行きたい。
勝つことと、生きることを同じ場所に置きたい。
感情を持って戦うことは、弱さじゃない。
俺にとって、それは勇気だ。
笑っても、泣いても、苛立っても、全部抱えたまま勝ちたい。
——九条雅臣。
あなたが切り捨てた世界の全部を、俺が取り戻してみせる。
沈黙と風
照明の白が、通路の壁を無機質に照らしていた。
スニーカーのソールが床を擦る音。
息を吸うたびに、冷たい空気が肺の奥に刺さる。
通路の先に、黒い影が立っていた。
肩のラインが、まるで定規で引いたように真っすぐだ。
——九条雅臣。
その背中を見ると、空気が変わる。
温度も、重力も、すべてが別の層にあるようだった。
あの人の周囲には、音がない。
まるで世界ごと停止しているみたいだ。
イーライは歩きながら、ほんの一瞬、思う。
(俺がこの人に勝てたとして、この静けさを壊してしまうことになるんだろうか)
すぐに頭を振る。
違う。壊すんじゃない。
風を通すんだ。
通路の出口で、九条が振り返った。
一瞬だけ視線が交わる。
何も言葉はない。
それでも、良かった。
イーライは笑う。
わざと、軽く。
この試合で、世界を少しだけ息をしやすくするために。
音の割れる場所で
——歓声が、割れた。
入場通路を抜けた瞬間、熱の塊のような音が全身を打った。
湿った空気の中に、ライトの光が反射して滲む。
観客席の波が、立ち上がっては押し寄せる。
コートの奥には、九条がいた。
彼はゆっくりと歩み出し、まるで音のない世界の住人のように、白いラインの上に立った。
背筋は伸びて、影ひとつ乱れない。
拍手も歓声も、彼には届いていないように見える。
——静と動。
対照的に、イーライの名前が呼ばれた瞬間、スタンドが再び沸いた。
それは音ではなく、熱。
誰かが口笛を鳴らし、旗が振られ、客席のあちこちでスマホのライトが点滅する。
イーライは拳を軽く上げた。笑顔を見せたわけじゃない。
ただ、観客の息と呼吸を合わせるように、一度だけゆっくりと息を吸い込んだ。
(これが、俺の戦場だ。)
今、ふたつの世界が並んだ。
片方は静寂。九条雅臣。
もう片方は鼓動。イーライ・コーヴァン。
二人の間に漂う空気は、もうすでに試合そのものだった。
審判の声が響く。
「プレイ!」
その瞬間、九条は氷のような視線をまっすぐに前へ。
イーライはわずかに笑って、風を吸い込む。
——支配と呼吸が、同じコートに並び立った。
無音と鼓動
——打球音が、空気を裂いた。
立ち上がりから、イーライが前に出た。
まだウォーミングアップの熱が残るうちに、フォアの強打を叩き込む。
コートの奥へ。サイドへ。角度をつけて、流れるように。
その動きは若さそのものだった。
勢い、直感、迷いのなさ。
反応が速い。
打つ瞬間には、もう次の一手が決まっている。
(悪くない。だが——)
九条はスプリットステップの一拍だけで、全てを読み切る。
体の軸は揺れず、返球は最短距離。
スピンでもなく、フラットでもない。
“必要なだけの球質”が、正確にライン際へ落ちる。
イーライが追う。
それをまた、九条が迎え撃つ。
テンポが速い。
だが、速さの質が違う。
イーライは「生きている速さ」。
九条は「止まって見える速さ」。
観客の目には、二人の動きが対照的に映っていた。
九条は無音の連続。
イーライはリズムを刻むような足音。
1ゲーム目、イーライがサービスエースを決める。
観客が沸く。
両腕を軽く広げ、彼は息を吐いた。
(届いてる。俺の声が、観客に届いてる。)
その一方で、ベースラインの向こう。
九条は汗ひとつ流していない。
わずかに視線を下げ、静かにボールを見つめている。
(問題ない。動きは速い。だが、揺らぐ。)
次の瞬間、九条のリターンが走る。
反射ではなく、予定された軌道。
まるで、ボールが引き寄せられるようにラケットに吸い込まれた。
“パシッ”
完璧なタイミング。
打球が一直線にネットを抜け、イーライの足元へ。
観客席が息を呑む。
イーライは振り遅れ、返したボールがネットの上で止まり、落ちた。
——1-1。
九条は表情を変えない。
イーライは微笑む。
「なるほど、“支配”ってこういうことか。」
小さく呟いて、もう一度構えた。
九条の無音の世界に、イーライの鼓動が割り込んでいく。
支配と呼吸。
静寂と鼓動。
試合は、まるで“哲学”のぶつかり合いのように始まった。
流れで戦う者
——音が跳ねた。
イーライのフォアが、稲妻のように走る。
ベースラインの奥から振り抜かれたボールは、空気を裂き、クレーの上で一瞬跳ねて消えた。
まるで、打球そのものが感情の塊だった。
(押し込む。支配じゃない、“共鳴”だ。)
イーライの頭は冷静だった。
体は熱いが、思考は凪いでいる。
この矛盾こそが、彼のスタイル——アグレッシブ・ベースライナー。
フォアの一撃で相手を後ろへ下げ、次の瞬間にはバックのスピンで角度を殺す。
力だけではなく、流れを読む感覚。
打つ前に、九条の動きがわずかに傾くのを感じ取っていた。
“読む”のではなく、“感じる”。
彼にとってテニスは理屈ではない。
ボールも風も、観客の呼吸も、全部が同じリズムの中にある。
その波を掴めば、体が勝手に動く。
(俺は、止めない。流れの中で戦う。)
対する九条は、まるで別世界の住人だった。
足音も、息遣いも、ない。
ラリーを続けているはずなのに、まるで時間の中に一人だけ“静止”しているように見える。
(支配する気はない。
けど、俺の流れの中では、お前も呼吸するしかない。)
イーライはそう思って、もう一度ベースラインの後ろへ下がる。
サーブのトスを高く上げた。
その一連の動作には、焦りも力みもない。
ただ、美しい軌道を描いて、ラケットが空を切る。
“ドンッ——!”
ボールが九条のバックサイドへ突き刺さる。
観客が湧く。
イーライは振り返らずに、深く息を吸った。
感情は持つ。だが、呑まれない。
熱を帯びたまま、冷静に勝つ。
——それが、イーライ・コーヴァンという男の戦い方だった。
世界を呼吸させる者
イーライ・コーヴァンは、攻撃的でありながら、バランスの取れたオールラウンダーだ。
力任せの若手ではない。
全てのショットに、計算と意図がある。
身長196センチの体が生むサーブは、高さと角度で相手を押し下げる。
だが本当の武器は、その後だ。
三球目の攻撃。
わずかな甘い返球を逃さず、フォアで一撃を入れる。
クロスでもダウンザラインでも構わない。
その瞬間の最適解を、直感で選ぶ。
そして、ほとんど迷わない。
リターンも速い。
相手のサーブを利用して、低く速く打ち返す。
弾道が低い。
球が伸びる。
その一球が、ベテランの呼吸を狂わせる。
だが、彼の一番の強みは精神の安定だった。
感情を燃料にしながら、爆発させない。
プレッシャーのかかる場面でも、目の奥の温度だけは変わらない。
——冷静な炎。
観客から見れば、それは矛盾していた。
激情ではなく、静かな集中の中で攻め続ける。
その姿は、まるで“感情を制御する感情”のようだった。
彼のテニスは、暴れない。
けれど、止まらない。
九条雅臣が“世界を黙らせる”王なら、
イーライ・コーヴァンは“世界を呼吸させる”挑戦者だった。




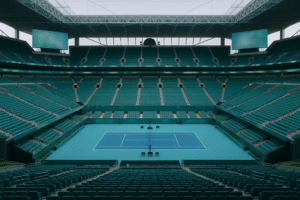

コメント