大会当日のルーティン
まだ夜の気配を残す、午前五時。
九条は音を立てぬようにベッドを抜け出した。隣で眠る澪を起こすことはしない。
淡々とシャワーを浴び、白いタオルで髪を乱れなく拭いあげる。
体内時計のように決まった流れで、消化の良い朝食を口に運ぶ。米、味噌汁、鮭。最小限、だが決して欠かさない。
会場に着くと、ラケットを五本、必ず同じ順番・角度で並べる。
狂いがあれば、何度でも整え直す。
十分快速でエアロバイクを漕ぎ、続けて二十分、全身をダイナミックに伸ばす。
呼吸のリズム、汗の量、体温。すべてが計算通りかを自分の内側で確認する。
その横顔は、昨夜澪の匂いを抱き締めていた男の面影を、どこにも残していなかった。
――氷の王。
そこにいたのはただ、勝利のために磨き上げられた存在だった。
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権。
世界ランキング上位の選手たちが集まる、中東最大級の大会だ。格付けはATP500――四大大会やマスターズ1000に次ぐ規模で、優勝すれば賞金は数千万円、世界ランキングに大きく響く500ポイントが与えられる。観客席には各国からの観光客や富裕層が集まり、リゾート都市らしい華やかな雰囲気が漂っていた。
だが――九条にとって、この大会は「絶対に勝たなければならない場所」ではなかった。
年間を通じて目指すのは四大大会、グランドスラム。そこにすべての照準を合わせている彼にとって、ここはあくまで“通過点”。勝ちに行かないわけではない。だが全身全霊を削り取って挑む舞台でもない。
観客が熱狂する中で、彼の目は静かに冷えていた。
――「本気を出す場所ではない」
そう言い切れるだけの確固たる基準が、彼の中にはある。
公式練習コート。
九条はウォームアップの動作一つ一つを正確に積み上げていく。呼吸のリズム、足裏の接地角度、ラケットのスイング速度――その全てに、わずかな誤差も許さない。
数メートル離れた場所にチームの姿がある。
氷川も、蓮見も、志水も。誰もがそこにいる。
だが誰一人、声をかけない。
理由は単純だ。
九条が試合前のルーティンに入った時、会話は意味を持たない。声をかけることは、集中を乱すだけだと全員が知っている。
彼らは必要な補給水を置き、視線で合図を送り、ただ静かに待つ。
九条がラケットを振り下ろす乾いた音と、ボールが地面を弾く響きだけがコートに広がる。
――ここはもう、戦場の入口だ。
澪起床
一方、澪はホテルの部屋で一人目を覚ました。
アラームをかけずに寝たせいで、「今何時!?」と慌てて飛び起きる。
幸い、まだ朝のうちだった。深く眠っていたせいで時間の感覚が思ったより長く感じただけだった。
寝癖を直しながらリビングに向かうと、テーブルに一枚のメモが置かれていた。
――氷川の連絡先。九条の筆跡で、端的に書かれている。
「会場に着いたら、関係者席への入り方を聞け」
そして最後の一行。
「朝食はルームサービスを頼め」
たったそれだけの指示。
澪は思わず苦笑する。
(……無愛想なのに、ホント、そういうところだけは抜かりないんだから)
会場の入口に着くと、すでに氷川が待っていた。
黒いシャツにサングラス姿で立っているだけで、周囲の空気がぴんと張る。
「綾瀬さん、こちらです」
短く告げられて、澪は慌てて小走りで近づいた。
人混みを縫うようにして、氷川の案内で会場内へ入る。一般の観客とは別のルートを通されると、ますます自分が場違いな気がしてきた。
「関係者席までは私が案内します。ただし――」
氷川が歩を緩めずに低い声で続けた。
「九条さんに声は掛けないでください」
「……あ、はい」
注意されると分かっていたけれど、実際に言われると胸がきゅっとする。
「今日から彼は試合モードです。試合前は誰にも話し掛けさせない。それがルールです」
淡々とした口調なのに、一言ごとに重みがあった。
澪はこくこくと頷きながら、(わかってる、わかってるけど……)と心の中で繰り返した。
執着を向けられる者
氷川に連れられて入ったのは、一般客の通路とは違う、静かな動線だった。
小さなゲートの前で名前を確認され、細いリストバンドを巻かれる。――これが「関係者証」なのだという。
入る前に金属探知機、厳しい視線、巡回する警備員。
ただの一人の観客であれば流されてしまう空気が、関係者という立場になった途端、重くのしかかってくる。
(私は何も悪いことしてない。…でも、少しでも挙動不審に見えたら追い出されそう)
アジア人の若い女一人。無害に見えるのは分かっている。
それでも、警備の目が肌に突き刺さるようで、澪は自然と歩幅を小さくして氷川の背にぴたりとついた。
「いつもこんなに厳戒態勢なんですか?」
思わず小声で尋ねると、氷川は歩調を崩さずに答えた。
「関係者用のルートなのでチェックは厳しいですが……今年は女子の大会で観客が強制退出になる事件があったので、警備が増やされています」
「……?何があったんですか?」
「……とある女子選手に対して、異常な執着を見せ、執拗に嫌がらせを行った観客がいたんですよ。全ての大会から出禁になりましたが」
「……」
澪は言葉を失った。
自分がいま通っているのは、そうした“危険”と隣り合わせの場所なのだと、実感がじわりと胸に広がっていく。
「有名な人って大変なんですね……」
まるで他人事のように言った澪に、氷川は視線を前に向けたまま返す。
「あなたが今、片足を突っ込んでいる世界です。自分は無関係だなんて、思わない方がいい」
「……私はただの一般人ですから」
「一般人だからこそ、その世界にいることを良く思わない人間はいるものです」
氷川の声音は低く、淡々としているのに、冷たい現実を容赦なく突きつけてきた。
「……覚悟だけは持っておいた方がいい」
澪は息をのんだ。
自分の足が、すでに知らない領域に踏み込んでいるのだと、遅ればせながら自覚する。
「………いつまでいられるか、わかりませんから」
何も感じていないふりをして、澪は軽くそう口にした。
永遠なんてない。続いてほしいと願うものでも、ある日突然壊れることを知っているから。
氷川は淡々と返す。
「あなたが拒絶しない限りは、いられますよ」
「……私に決定権があるんですか?」
「というより、あの男は中途半端な気持ちで外部の人間を内側に入れる人間ではない、ということを理解した方がいい。あなたもすでに“執着”を向けられる側にいるんです」
「なんか今日……氷川さん、意地悪」
むくれてみせる澪に、氷川はわずかに目を細めた。
「あなたを思うからこそ言っています。あなたは警戒心が薄い」
「そんなことないですよ。私こう見えて、人に気を許さない女ですから」
ふふん、と胸を張ってみせる澪に、冷静な声がかぶさる。
「それとこれとは別です。気を許そうが許すまいが、来るものは来ます。……心当たりがあるのでは?」
「………」
胸の奥が一瞬ひやりとした。
つい最近まで、職場の既婚者に狙われ、強く拒絶できずに長い間執着されていた――その記憶が澪を縛っていた。
意地悪なマネージャー
「……やっぱり意地悪」
澪が小さく口を尖らせる。
氷川は眉一つ動かさずに答えた。
「意地が悪くても、言うべきことは言います。それが本人のためになると信じているので」
「これぞ九条雅臣のマネージャーって感じ」
澪の言葉に、氷川はわずかに目を細める。
「そうですね。ゴマをするだけの人間なら、彼のそばにはいられないでしょう。あなたが彼のそばにいるのも、ゴマをすらないからでは?」
氷川の問いかけに、澪は一瞬だけ視線を落とす。
「……私、人に迎合するの、苦手なんです」
自嘲気味にそう答える声は、笑みすら伴わなかった。
氷川は短く頷き、歩みを進める。
「ならばなおさら、彼に選ばれた理由が分かります」
澪は返事をしなかった。ただ、胸の奥に小さなざわめきを抱えたまま、彼の背を追った。
「私は、なぜ選ばれたのか…選ばれたと思っていいのか、わかりません。今でも、裏切られるんじゃないか、突然連絡が取れなくなるんじゃないか、ってどこかで不安です。でも、今はここにいられるから、います」
「……意外と、楽観的ではないんですね」
「根っこの部分はすっごく暗いです。頑張って見せないようにしてます」
関係者席までの廊下。すれ違う人々の声は英語やフランス語、アラビア語が入り混じっているのに、二人の会話だけが静かに日本語で続いていた。
「こう言うのもなんですが……」
氷川が珍しく口ごもる。
「はい?」
「彼は、驚くほどあなたに多くのものを渡していますよ。私は驚きと同時に、少し呆れています」
澪は一瞬目を丸くし、それから小さく笑った。
「マネージャーさんが言うなら、間違いないですね」
「ええ。彼が子供の時から見てきてますから」
「そうなんですか?」
「その話はまた後日。――そろそろ関係者席に着きます。蓮見と志水がいるので、目印にしてください。私はまだやることがありますので、ここで。試合が始まる頃には戻ります」
氷川はそう言って、背を向けて去って行った。
選手の関係者席
中に入ると、目の前に広がるのは一般席よりもコートに近い特別席。
座席は余裕をもって配置され、革張りの椅子には小さなテーブルまで備わっている。
本来は、選手の家族やコーチ、トレーナーなどの近しい人物しか座れない特別な場所。
その場所に、家族でもチームメンバーでもない澪は、座ることを許されている。
「おはようございます。お疲れ様です」
関係者席に腰を下ろした澪が、ふと横に座る蓮見と志水の横顔を見た。
2人揃って同じデザインの黒縁眼鏡を掛けている。
(……お揃い?)
意外すぎる光景に、澪は首をかしげてしまった。
視線に気づいたのか、蓮見が小さく笑う。
「これスマートグラス。お揃いじゃなくて、機能が同じなんだよ。男とお揃いにはせんって」
「スマートグラス?」
「九条の動きとデータをリアルタイムで共有できる。およその心拍、打球の回転数、体重移動……全部チームで把握と記録ができるようになってる」
「へぇ……そんなのまで」
思わず声が漏れた。
澪にはただの眼鏡にしか見えないのに、その内側では数字やグラフが映っているらしい。
隣の志水は相変わらず無言で前を向いたまま。
蓮見が片方のこめかみに触れると、かすかに小さなライトが点滅した。
「無線でやり取りもできる。チームメンバー同士が離れた場所にいてもやり取りができるようにと、内容を文字起こしして記録するようになってる。あとで情報整理に使うんだよ」
澪は目を丸くした。
(……こんな風に、みんなで九条さんを支えてるんだ)
蓮見は、澪の視線に気づくとわざとらしく口角を上げた。
「すげーだろ」
スマートグラスを指先で軽く押し上げる仕草までつけて、どや顔。
隣の志水が小さくため息をついた。
「……これ、開発したの宙ですけどね」
「え、そうなんですか!?」
澪は思わず声を上げる。
宙とは、先日カザランに紹介された若いオタク少年のような男性スタッフだ。見た目だけなら普通の日本人の若者にしか見えなかった。
「俺は使い方を伝えただけ。仕組みを作ったのは全部あいつ」
それでも蓮見は胸を張ったまま。
志水は淡々と前を向いた。
「まるで自分の手柄みたいに言うのはやめてください」
澪は堪えきれず笑いそうになり、必死に口元を押さえた。
それぞれプロ
澪は二人のやり取りを見ながら、思わずぽつりとこぼした。
「なんか、みんなそれぞれにすごいプロですね」
蓮見は「当然だろ」とでも言うように顎を引き、
志水は淡々と「それぞれ役割がありますから」と短く返した。
言葉少なでも、その背中から“支える者の誇り”が伝わってくる。
澪は二人のやり取りを見ながら、思わずぽつりとこぼした。
「なんか、みんなそれぞれにすごいプロですね」
蓮見は「当然だろ」とでも言うように顎を引き、
志水は淡々と「それぞれ役割がありますから」と短く返した。
言葉少なでも、その背中から“支える者の誇り”が伝わってくる。
蓮見が肩をすくめる。
「あんたもプロだろ?ヨット販売の。プロじゃなきゃ、九条に相手にされない」
澪は思わず手を振った。
「いやいや、私なんてただの営業ですから。スポーツとか全然関係ないですし」
澪は無自覚に謙遜してしまう。
そこで志水が、眼鏡の奥からじっと澪を見て口を開いた。
「関係なくても、中途半端な仕事をしてたら九条さんと親しくなってませんよ。あの人、そういうことに対しては全く容赦ないので」
フォローなのかどうなのか分からない一言に、澪は返す言葉を失って小さく笑うしかなかった。
選手入場
関係者席で蓮見や志水と他愛ない会話をしていた澪は、不意に場内が静かになったのに気付いた。
「……あ、始まるんだ」
大型スクリーンには大会ロゴが浮かび上がり、低く響く音楽が流れ始める。観客のざわめきが波のように押し寄せ、やがてアナウンスの声が響き渡った。
コートサイドへと続く通路から、選手たちが一人ずつ姿を現す。
ラケットバッグを背負い、無駄のない歩みで入場するその姿に、観客席から拍手と声援が湧いた。ライトが強く照らし出す舞台に、一気に空気が張りつめていく。
澪は息を呑む。
――今までテレビ越しにしか見たことのなかった「世界」が、目の前にあった。
アナウンスが場内に響いた瞬間、観客席の空気が変わった。
それまでざわついていた声が一気に収まり、ライトがコート入口に集中する。
「――Masatomi Kujoh!」
名前が呼ばれた途端、拍手と歓声が爆発した。
立ち上がって声を張り上げる者、スマホを掲げる者。
会場全体が一瞬で熱を帯びる。
黒いラケットバッグを背負い、無表情のままゆっくりと歩み出る長身の男。
揺るぎない足取りは、勝利を約束された者のそれだった。
誰にも目をやらず、観客に手を振ることもない。
ただ前だけを見据え、コートへと歩を進める姿に、観客は歓声ではなく“静けさ”でさえ飲み込まれていった。
コートに入った瞬間、澪は息を呑んだ。
同じ人なのに、別人のようだった。
氷の仮面をかぶった横顔は、昨夜まで自分を抱きしめてくれていた人とは思えない。
名前の読み方
「……てかさ、名前の呼び方違うし」
澪が思わず小さくこぼした。
アナウンスでは「まさとみ」と紹介していたが、本当は「まさおみ」だ。
「読み間違えされるからって言うのもあるんだろうけど、もうここまで有名になってたらもはや記号化するから、ちゃんと正しい読み方を伝えればいいのに」
誰も聞いちゃいない。歓声にかき消されたその声は、ただ自分の胸の奥にだけ残った。
コートに立つ九条は、完全に“氷の王”だった。
観客席から名前がコールされる。けれど、その発音はまたしても正しくない。
澪は小さく顔をしかめた。
「……間違えて呼ばれる度に、なんか緊張感緩むんだけど」
隣で腕を組んだままの蓮見が、ぽつりと呟く。
「あー、そういやアイツが若い頃、いちいち読み方を訂正するのが嫌で、海外でも読みやすい名前に変えてそれっきりだったな」
「もう今更、正しい名前で登録し直すことに抵抗を示すのでは?」と志水も淡々と続ける。
澪は頬を膨らませたまま、視線をコートに戻した。
「……ちゃんと呼んでもらえばいいのに」
小さな不満は、熱気に包まれた会場に溶けていった。
極限の集中状態
澪はむくれたまま口を尖らせた。
「雅臣さん本人がそれで良いんだったら、私からは言えないけどさ」
そこで、いつの間にか戻ってきていた氷川が、背後から低い声で割り込む。
「試しに、あなたから言ってみては? 案外聞くかもしれませんよ」
「……えっ、私が?」
澪は慌てて振り返る。
氷川は表情を崩さず、ほんの少しだけ口元を緩めた。
「彼に“直してほしい”と頼めるのは、あなたぐらいでしょうから」
澪の胸に、不意に小さなざわめきが広がった。
「…じゃ、じゃあ試合終わってから、話す時間あったら、言ってみようかな…。とりあえず、今は試合を邪魔しないようにします」
「多分、声かけても聞こえてないってぐらいになるぞ、あいつ」
蓮見が肩をすくめる。
「あ、私、全豪オープン観たんですけど……雅臣さん、いつもあんな感じなんですか?」
関係者席に沈黙が落ちた。
蓮見も志水も氷川も、ほんのわずかに表情を曇らせる。
「………」
澪は思わず身じろぎし、気まずそうに視線を泳がせた。
さっきまで和やかだった空気が、一瞬にして張り詰める。
「“あんな感じ”というのが、どの状態かによります」
氷川が低く答えた。
「決勝の時の状態なら、普段はああはなりません。それより前の試合の状態なら、常に試合ではそうなります。そうなるように、ルーティンを組んでいるからです」
澪は思わず息を呑んだ。
「じゃあ、全豪の決勝は……やっぱり特別だったんですね」
「……ええ」
氷川は目を細める。
「相手の技やテクニックをすべて吸収し、他の選手の特性までも繰り出す――あれは彼が理想とする“到達点”です。常にああなれるように、今もなお試みている」
澪は言葉を失った。
その背中を、つい昨日まで同じベッドで撫でていたことが信じられないくらい、遠い存在に思えた。
「それ……危なくないんですか?強かったけど、見ていてすごく怖かったし……いつか壊れそうに見えました」
澪は、無意識に声を落としていた。
氷川が表情を動かさぬまま答える。
「……危うい状態です。本人は“平気だ”と言っていましたが、筋肉が痙攣を起こしかけても構わず動き続ける人なので、あまり信用できる言葉ではありません」
「……止めないんですか?」
言った瞬間、澪は自分が部外者の身で口にするには軽すぎると悟り、視線を落とす。
蓮見が、珍しくふざけずに短く言った。
「止めて聞くやつなら、ここまで来てない」
志水が静かに続ける。
「だから俺たちの仕事は“壊れないように支える”ことです」
淡々とした声だったが、澪にはその裏ににじむ緊張感が痛いほど伝わった。
「……ごめんなさい。軽率でした」
澪は素直に頭を下げるしかなかった。
「あなたの存在に、支えられている面もあります。それは、私たちでは代わりになれません」
氷川が、静かに言葉を添えた。
「……私、甘えてるだけで、何もしてませんよ?」
澪は笑おうとしたが、声が少し震えていた。
氷川はその言葉に、ただ一瞬目を伏せただけで、否定も肯定もしなかった。
曖昧な表情のまま――“あなたがそう思うなら、それでいい”とでも言うように。
氷の王の登場
コートに九条が姿を現した瞬間、スタンドのざわめきが一斉に収束した。
観客席の空気が急激に冷え込むようで、澪は思わず背筋を伸ばした。
ただ歩いているだけなのに、視線が全部持っていかれる。
拍手も声援も、まるで遠くで響いているみたいに感じた。
胸が締め付けられる。呼吸が苦しい。
これが――世界の頂点に立つ選手の「試合の顔」なのだと、澪は理解する。
コートに九条が現れた瞬間、観客席の空気が変わった。
張り詰めるような緊張感が、皮膚の上を這う。
息をするのが苦しい。肩がこわばる。
ただ歩いているだけなのに――別人みたい。
ホテルのスイートで見た姿とも、あの穏やかに笑っていた顔とも、まるで違う。
ここにいるのは“世界一の選手”であって、澪の知っている雅臣さんじゃない。
同じ人だって、分かっているはずなのに。
そこに立っている九条は、形こそ同じなのに――まるで違う存在みたいだった。
雅臣さん、じゃない。
ただの一流アスリートでもない。
得体の知れないものが、あの肉体に宿って動いている。
知っている人のはずなのに。
触れたことも、声を聞いたこともある人なのに。
――怖い。
呼吸が浅くなる。
それでも――声を上げるわけにも、席を立つわけにもいかない。
関係者席の誰もが、張り詰めた空気の中で黙って見ている。
自分だけが取り乱すわけにはいかない。
澪は膝の上で両手をきつく握りしめ、ただ大人しく、コートの上の“九条雅臣”を目で追い続けた。
試合開始
打ち合いが始まった瞬間、空気が変わった。
ラケットがボールを捉える音が、他の選手のものとは明らかに違う。乾いた音が、やけに鋭く響く。
相手のサーブがネットを越えた途端、九条は一歩で詰めて、打ち返した。
何が起きたのか一瞬わからない。ただ、次の瞬間には相手が走らされている。
――速い。
澪はただ、その一言しか浮かばなかった。
目で追っているはずなのに、ボールが線を描かず、点から点へ跳んでいるように見える。
九条は汗ひとつかかず、表情を変えないまま、無機質に次の一撃を放つ。
観客のざわめきが耳に入る。けれど澪の耳には、ラケットとボールの衝突音だけがやけに強く届いていた。
淡々と、ただ勝つためだけの動き。
九条のラリーには、駆け引きの熱も、観客を沸かせるサービス精神もなかった。
無駄を削ぎ落とした機械のように、相手の弱点を探り当てては突く。
返せば返すほど、逃げ道を塞がれていく。
まるで出口のない迷路に相手だけを閉じ込め、正解を見せないまま体力を奪い続ける。
澪には、それが「美しい」と同時に「怖い」と思えた。
同じ顔をしているのに、ここにいるのは知っている人ではなく、冷たく研ぎ澄まされた刃そのものだ。
観客席からはため息や驚嘆の声があがる。
だが、九条は一度も観客を振り返らず、視線はただネットの向こうに突き刺さっていた。
打ち込みは速い。だが派手さはない。
無理にウィナーを狙わず、相手の戻りが一歩でも遅れた瞬間に角度を突き、余裕を与えない。
サーブも最速を出すわけではなく、コースを正確に打ち分けて、受け手の体勢を崩すことだけを徹底している。
ストロークのラリーは、すぐに終わる。
深く沈むボールで押し込み、返球が浅くなったところで一撃。
見ている側には、ただの“作業”のようにも映る。
だがその作業は、相手の体力と気力を一球ごとに削り取っていった。
感情のない試合展開
澪には、九条が“勝つ”こと以外をすべて切り捨てているのが分かった。
どれだけ速く、どれだけ効率的に、どれだけ容赦なく。
そこに迷いも情けもなかった。
ラリーは長引かない。
九条の放つボールは深く、重く、相手を一歩外へ追いやった瞬間に角度を突く。返すだけで精一杯になった打球は浅くなり、その一球を冷徹に仕留める。
観客席にざわめきが広がった。
“Too fast…”(速すぎる……)
“It’s not tennis, it’s hunting.”(テニスじゃなくて、狩りだ)
“He makes the other guy look helpless.”(相手がまるで無力に見える)
“So cold… he doesn’t even flinch.”(冷たすぎる……一切感情が見えない)
歓声ではなく、恐怖に近い囁きが重なる。
派手なラリーや劇的な逆転ではない。じわじわと追い詰められていく光景に、観客たちは息を呑んでいた。
――違うのにな。
今はそう見えるかもしれないけど……。
本当は、優しいところもあるのに。
胸の奥がちくりと痛む。
声を上げて否定したいわけじゃない。ただ、知らない人の言葉に、知られたくない彼の一面を勝手に決めつけられるのが少し寂しかった。
澪は黙って、ただラケットを握る彼の姿を見続けた。
「このままだと一方的な試合になる」
蓮見が、記録用の端末に目を落としながら淡々と呟いた。
「相手がよほど食い下がってこない限りは、このままストレートで勝てるでしょうね」
志水も短く同意する。
「やはりスピードが出るサーフェスだと、展開が早い」
氷川はスマートグラス越しにコートを見据えたまま、眼鏡の奥を一切緩めない。
――同じ試合を見ているのに。
観客は「冷酷だ」と怯え、彼の仲間は「順当だ」と淡々と記録している。
それでも傷付く
無表情でラケットを握る九条は、声援にも拍手にも一切反応を返さない。
ただ淡々と、サーブを打ち、打球を返す。その姿は氷の彫刻のように感情が見えない。
「He ignores the crowd…(観客を無視してる…)」
「No emotion at all.(全然感情がない)」
英語のささやきが耳に入る。
澪は膝の上で拳を握った。
――違うのに。
本当は無関心なんかじゃない。ただ、外の音が耳に入らないほど集中しているだけ。
優しさを知っているからこそ、その誤解の声が胸に突き刺さった。
「いちいち気にしていたらキリがありませんよ」
氷川が低い声で忠告する。
「もう数えきれないほど言われてきた言葉です。本人も気にしていません」
「っていうか、アイツ聞こえてねーよ」
蓮見はあっけらかんと笑った。
志水も視線を外さないまま、静かに言葉を添える。
「そういった“他人の声”で集中を乱されることを嫌って、聞こえないほどの集中状態に入ることを覚えた人間ですからね」
「……聞こえてないのは分かってるけど……それでもちょっと傷付きます。心が痛いです」
澪は苦々しい表情でコートを見つめる。
試合は九条が完全に掌握していた。相手は食い下がる余地もなく、展開は淡々と進む。
――それなのに。
「面白くない」「ハラハラしない」「圧倒的すぎてつまらない」
「観客の声を無視」「無感情」
観客の声が耳に刺さる。
その状況を作るまでに、彼がどれだけの努力を積み重ねてきたか。
どれほど痛みや孤独を抱えてきたか。
誰も知らない。誰も見ようともしない。
ただ結果だけを消費する声が飛び交う中、澪の胸だけが軋んでいた。
「多くの注目が集まれば集まるほど、人々の声も大きくなり、厄介な存在も寄ってきやすくなる。だからこそ試合以外の時間は静けさを好みますし、近くにいる人間を厳選する。あなたはその選び抜かれた中の一人なんです。胸を張ってください。他人の声など聞かず、九条さんを見ていてください」
氷川の低い声に、澪は胸の奥を掴まれるような感覚を覚えた。
ぐらつきそうになっていた心が、すっと落ち着いていく。
「……はい」
澪は小さく頷き、目を逸らすのをやめた。
外のざわめきではなく――コートの上の九条だけを、真っ直ぐに見据える。
あっけない終了
結局――試合は何のどんでん返しもなく、あっけなく幕を閉じた。
九条のストレート勝ち。
相手は歯が立たず、危うい場面も一度もない。
効率だけを追い求めたようなスピード決着に、観客席からは拍手よりもざわめきが広がる。
そんな中、澪は複雑な気持ちで立ち上がれずにいた。
――ここに辿り着くまでに、どれだけの積み重ねがあったかを、見てはいなくても、想像はつく。
いや、恐らく彼は想像を超える努力をしてきた。
それでも、この空気の中で「優しい人なんです」と叫ぶことはできない。
ただ、胸の奥にしまい込んだまま、コートの上で無表情にラケットを片付ける彼を見ていた。
席を立つ観客達が、各々呟きながら去っていく。
“His matches are boring. He always wins.”
(九条の試合はつまらない。必ず彼が勝つからだ)
“Where’s the suspense? It’s over before it starts.”
(サスペンスがない。始まる前から終わってる)
“Yeah, he’s flawless… but too cold.”
(完璧だけど、冷たすぎる)
――違うのに。
そうじゃないのに。
澪は心の中で小さく呟いた。
彼の優しさも、不器用な部分も知っているのに。
観客の声が突き刺さるたび、胸の奥がじわりと痛んだ。
控え室へと退場していく九条の背中を、澪は最後まで目で追った。
帰国準備
そして小さく息を吸って、席を立つ。
「私、そろそろ飛行機の時間があるので、ここで失礼します」
隣にいた蓮見が眉を上げる。
「……会って行かないのか?」
少し考え、澪は首を横に振った。
「集中を乱したくないし、彼はまだ大会が始まったばかりだから…。メッセージを送っておきます」
言いながら、自分の中でほんの少しだけ寂しさが滲む。
でもそれを顔には出さず、笑って蓮見に頭を下げた。
空港へ向かう車の中、澪はiPhoneを取り出して短く指を走らせた。
お疲れ様。すごかったよ。
この2月、いろいろありがとう。
お世話になりました。
日本に帰ります。
怪我しないように気を付けて。
陰ながら見守ってます。
「……うん、これでいい」
送信ボタンを押してから、胸の奥がきゅっとした。
スマホが震え、画面には「九条雅臣」の名前。
思わず背筋が伸びる。
「…なんだ、あの畏まった文面は」
受話器越しの声は、先ほどまでの冷酷な試合中の声ではなく、少しむくれたような低音だった。
「…え、いや、だって…」
「だってじゃない。まるで他人みたいだ」
「…他人じゃないけど…」
「けどなんだ」
「なんか…しばらくお別れだから寂しくて…」
一瞬、沈黙が落ちる。
「ならあんな、今生の別みたいな文章を送ってくるな」
「ならなんて送ればいいのよ」
「いつものお前らしくいろ。調子が狂う」
「えええ…これも私なんですけど…」
「他人行儀だ」
ため息まじりの低い声には、拗ねたような気配すらあった。
澪は、思わずスマホを耳から少し離し、画面を見つめる。
――試合のときとはまるで別人みたい。
「……雅臣さん、拗ねてる?」
「拗ねてなどいない」
「完全に拗ねてる声なんですけど」
「……」
返事がないのが、むしろ図星の証拠だった。
電話の向こうで沈黙が落ちる。澪は思わず吹き出した。
「ふふ、可愛いなぁ。試合中の冷酷な王子様はどこ行ったの?」
「……茶化すな」
「ごめんごめん。でも、なんか安心した」
澪が笑いながらそう言うと、九条はようやく小さく息を吐いた。
試合で見せた圧倒的な姿との落差が、寂しさも可笑しさも一緒に伝えていた。
「……次は、ちゃんと直接言え」
「え?」
「別れの挨拶も、感謝も。文章ではなく、俺に直接」
「……はいはい。じゃあ今度は面と向かって言いますよ」
「それと」
「まだあるの?」
「帰国しても、連絡は怠るな」
「……もしかして、やっぱり寂しい?」
「……黙れ」
澪はくすくす笑いながら「はい、連絡します」と素直に答えた。
「時差あるけど、そっちもちゃんと電話してね」
「お前も出ろ」
「できるだけ出ます。でもなるべく夜にして。昼間は出れないこともあるから」
「わかった。……横浜のマンション、ちゃんと行けよ」
「うわ、なに急にオラオラ系になって」
「……」
「はいはい、行きます。ありがとうね」
「着いたら連絡しろ」
「はーい。雅臣さんも無茶しないでね。私も心配してるよ?」
「……わかった」
「絶対わかってないでしょ。ちゃんと見てるからね?」
「ああ」
澪の小さなため息とともに、電話は静かに切れた。
――彼の「わかった」は、きっと誰よりも信用ならない。
澪は通話を終えたあと、スマホを膝の上に置いて、ふっと笑った。
しばらく会えなくなるのは寂しい。胸の奥がしゅんと縮むように心細い。
――でも。
電話はできる。画面越しに顔も見れる。
「いつでも連絡が取れる」という事実が、少しだけ気持ちを温めてくれる。
庶民の生活へ
搭乗ゲートを抜け、通路を歩く。
周りは旅行客や出張客でざわついていて、九条といた世界の緊張感とはまるで別物だ。
「はぁ……エコノミーか……」
座席の狭さや長時間のフライトを思うと、どうしても気が重くなる。
けれど同時に、妙に安心もした。
自分はやっぱり“こっち側”の人間で、どこにでもいる普通の客の一人なんだ、と。
窓際の席に腰を下ろすと、キャリーケースを頭上に押し込み、膝の上でスマホを握りしめる。
さっきの電話の余韻が残っていて、胸の奥が少しだけ温かかった。
「よし……帰ろう」
小さく呟いて、シートベルトを締めた。
遠ざかるドバイの街の光が、次に会う日への期待をほんの少しだけ明るくしてくれた。
通常モードへ戻る

澪を送り出したあと。
九条はチームに指示し、滞在先を会場近くのホテルへと移した。
九条が移ったのは、JBR地区に建つザ・リッツ・カールトン・ドバイ。
観光客にとってはアラビア湾を望む楽園だが、彼にとっては会場に近いことと、調整用のテニスコートがあること、それだけが重要だった。
窓からは海がきらめいて見える。
だが九条の視線はそこには向かず、ベッドに置かれたラケットバッグと、氷川が手配した栄養バランスの食事に落ちる。
――澪と過ごしたレジデンスタイプの部屋には、生活の気配があった。
ここには、ただ「戦う準備」のための静けさしかない。
試合に必要な最低限の荷物は、すでに氷川が搬入を済ませている。
ここは“生活”の場ではなく、“戦うための拠点”だ。
室内に足を踏み入れた九条は、ラケットバッグを静かに置く。
窓の外には、コートへと続く街路が見える。
呼吸を整え、汗を流し、食事を摂り、眠る。
余計なことは一切排除し、ただ勝つためだけに身体を調律する場所。
澪のいた部屋では気配を分け合っていた。
だが今はただ一人、合理的に整えていく静寂だけがある。
作戦会議
ザ・リッツ・カールトンのスイートルーム。
窓の外には夜景が広がっていたが、部屋の中に漂う空気は、リゾートの華やかさとは無縁だった。
丸テーブルの上に並ぶのは、湯気を立てる野菜スープと鶏胸肉のグリル、玄米リゾット。レオンが調整した「試合前用」の夕食だ。
「タンパク質は控えめ。エネルギーは消化の良い炭水化物から」
栄養士のレオンが淡々と説明する。九条は頷きながらスープを口に運んだ。
テーブルの中央には、蓮見のタブレットが立てられている。再生されるのは次の対戦相手の直近試合の映像。
「リターン時、バックに集められると浅くなる癖がある。こっちからの高速展開に対応できない」
蓮見が指で画面を止め、角度を示す。
「サーブの確率は? 一発で取れるか」
「初球は高い。だが二球目は甘い」
九条は短く「わかった」とだけ返す。
横で志水がタブレットを覗き込み、低く補足する。
「腰の可動域が狭い。体幹が強い分、逆を突かれると遅れる」
「なら二歩前に出る」
九条はそう断じ、鶏肉を口に運んだ。
食後、早瀬が静かにマットを敷く。
「食べ終わったら、筋膜リリースを」
声は淡々としていたが、手元の器具は既に準備されている。
氷川はメモを確認しながら口を挟む。
「明日のスケジュールは既に調整済みです。余計な取材はいつも通り、すべて断ってあります」
神崎医師が錠剤ケースを差し出す。
「睡眠の質を優先しろ。必要ならこれを」
九条は頷き、席を立った。
リッツの部屋は確かに豪奢だが、そこに漂うのは戦場の空気だった。
チーム九条は、それぞれの役割を果たしながら、次のの勝利へ向けて淡々と準備を進めていった。






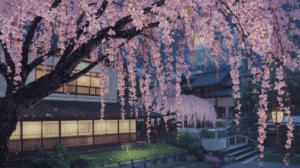


コメント