“無”の時間
ベンチに腰を下ろした九条雅臣は、タオルを取ることすらしなかった。
冷却も、補給も、排除するように。
まるで“次”が始まるのを、既に知っていたかのように。
その眼差しは、何も見ていない。
だが、何もかもを見ていた。
観客のざわめき、実況の声、会場に流れるBGM、
——全てがノイズとして遮断されていく。
代わりに、彼の中にだけ鳴っていた。
無音の起動音。
リスタートではない。
再開ですらない。
あれは、次の構造へのシフトだった。
前のセットを「勝った」のではなく、
ただ「終えた」だけ。
そして次の支配が、すでに始まっている。
身体も、試合も、まだ途切れてない。
酸素消費のリズムも乱れなし。
このまま2セット目、ノンストップで行けます。
休憩、という概念がない。
【第7ゲーム】無響室の王
センターラインを挟んだ向こう側で、相手がサーブを構えた。
だが、その気配すら、遠い。まるで防音ガラスの向こうに立っているかのように──何も、届いてこない。
九条雅臣の視界からは、観客の顔も、揺れる看板も、主審の白いシャツさえも消えていた。
残っているのは、計算済みの軌道と、対応すべき選択肢だけ。
1球目。
ラケットが音を立てたはずなのに、聞こえなかった。
返す。踏み込む。沈むように打ち込む。
音はない。ただ、スコアボードが更新されたのが視界の端でわかる。
(15−0)
次。
相手が息を呑んだ。ほんの一瞬、サーブのフォームが乱れる。
その刹那、九条は右足の重心をずらした。打点は読み通り、バックの外。
ラリーすら成立しない。即、得点。
(30−0)
スタンドはざわついていた。だが、それは“向こう側の世界”のことだ。
このコートの中に音は存在しない。ここは、王の無響室。
ラストポイント。
九条はネット際に出た。フェイクだ。
相手が焦ってロブを上げた瞬間、彼は一歩も動かず、トスの落下点を凝視した。
予測などいらない。そこにしか来ないと、最初から知っていた。
乾いたボール音が、ようやく耳に届く。だがそれは、ゲームが終わったあとの残響だった。
ーGAME KUJO
【第8ゲーム】「精度の狂い」
ボールが、思ったよりも、半歩分だけ外れた。
ほんの数センチ。
ほんの数フレームの、遅延。
だが九条雅臣にとって、それは“誤差”ではなかった。
“狂い”だった。
──何かが、変わった。
空間の密度が、わずかに違う。
湿度か、風か、あるいは照明の明度。
だがどれも“要因”にはならない。
次のサーブ。相手は確実に、流れの変化を嗅ぎ取っていた。
(スライスだ)
読みは合っていた。だが、スイートスポットの感覚がズレる。
数ミリ、芯を外した打球が、わずかに浅く跳ねた。
(15−0)
その瞬間、スコアより先に、九条の中で何かが“点滅”する。
──違和感。
初めての“揺らぎ”。
すぐに修正に入る。姿勢、体重移動、筋出力のバランスを切り替え。
だが、彼の中のどこかが告げていた。
(これは、コートの問題じゃない)
(──俺自身に、何かある)
一球、また一球と処理する中で、彼は密かに“内部確認”に入っていた。
反応、0.2秒くらい。
指令伝達に乱れはない。
……ただ、入力が“今”じゃなかった。
体はここにあるのに、思考だけ未来。
あの人、もう“次”のゲームの出口まで見えてる。
九条は、表情一つ変えず、サーブを構える。
身体が「原因」を特定するより先に──
彼は、次の“修正構造”を始動していた。
【第9ゲーム】起動音なき再起動
立ち上がる九条雅臣に、どこにも「再開」の気配はなかった。
彼は、さっきまでの試合をまるごと切り離すように、別の構造体として起動する。
それは、再始動でもなければ、修正でもない。
起動音すら鳴らない、新たな支配のプログラム。
彼の視界には、コードのように展開される“可能性の網”が広がっていた。
一手先ではなく、三手先。
五手先ではなく、“相手がそこで選び得ない選択肢”すら計算に含まれていく。
ファーストサーブ。相手はまた読みづらいスイングを見せた。
だが、今の九条にはそれすら**「記号」**でしかなかった。
フォームの崩れ、グリップの深さ、足の重心。
──これは、クロスの深いボールではない。浮く。打点が遅い。
カウンター、鋭角。音はない。
(15−0)
次のポイント。相手が手元を見た。迷いのサイン。
九条は、トスが上がる前に既にポジションを変えていた。相手のサーブは、そこへ導かれるように飛ぶ。
バックでブロックし、前に出る。詰める。
相手のボールが浅くなった瞬間、彼のラケットは一度だけ空を切った──
フェイクだ。
相手が動いたその逆を、正確に撃ち抜く。
(30−0)
スタンドがどよめいた。けれど、それは彼の“外”の音。
九条は、もうこのコートの中にすらいなかった。
彼は、自分の中にある「構造」を走らせているだけだった。
ラストポイント。
相手はネット際に走り込む。イレギュラーなプレーだ。
だがそれすら、プログラム内の“例外処理”として処理されていく。
ロブ。相手の頭上を抜く。返すか? 否、打点が高すぎる。
跳ね返る音は、また無音。
(GAME KUJO)
九条は振り返らない。
ベンチにも座らない。タオルにも手を伸ばさない。
もう、冷却はいらなかった。
でも筋出力は一定。……何か、演算だけが先に走ってる。
あいつ、どこまで行く気だ。
……これ、まだ試合中だよな?
この人だけ、今もう次の試合始めてるのかもしれない。
【第10ゲーム】静音圧縮
──音のない制圧
コートに音がなかった。
いや、“音を置き去りにした”と表現すべきかもしれない。
九条雅臣の動きに、無駄は一つもなかった。
スプリットステップの着地音すら、砂塵の中に沈んでいた。
──それが怖かった。
打球音、歓声、ラケットの軋み。
通常ならそれが“試合の気配”を構成する。
だが、今、相手の耳に届いていたのは、自分の息の音だけだった。
静かすぎる。
沈黙が、全方向から圧をかけてくる。
1ポイント目。
九条はただスライスで返した。浅く、そして低く。
相手が一歩踏み出した瞬間、もう逆サイドに球はあった。
(15−0)
視線を逸らした一瞬の迷いが、ラリーを終わらせた。
2ポイント目。
今度はラリーになった──かに見えた。
だが、テンポが一定だったのは最初の3球だけ。
そのあとは変則。呼吸と歩幅とストロークのリズムが、全部ズラされる。
身体が“演奏不能”になった。
(30−0)
観客は拍手も忘れていた。
というより、どこで拍手を入れればいいのかすら、わからなくなっていた。
ラスト。
ネットを狙ってきた相手に、九条は動かない。
全てが止まったかのような間。
その後、相手のラケットからスピンの利いた球が放たれた──が、それも九条の予測の内だった。
左足を軸に、背面に回り込むようにしてカウンター。
静かすぎて、球が抜けたあとのネットの揺れだけが、視界に残った。
(GAME KUJO)
沈黙のまま、スコアがひとつ増える。
音のないまま、空気がひとつ潰される。
この試合において、“制圧”とは騒音ではなく、
静けさの中に潜む演算の密度だと、誰もが思い知らされた。
……酸素、減ってないよな?(冗談)
一種のノイズコントロールです。本人、完全に意図してる。
それ、**あいつにとっては“成功条件”**だよ。
俺たちはもう慣れたよ。**これが、九条雅臣。**
【第11ゲーム】無音のコマンド
—1ポイントずつ、淡々と。
九条雅臣は、何も喋らなかった。
喉すら動かない。まばたきすら、ない。
けれど、“命令”だけが発されていた。
それは言葉ではなく、
動きでもなく、
ただの、“結果”。
ポイントごとに、淡々とスコアが更新されていく。
まるで、あらかじめ用意されたコマンドを
トレースしているかのように。
(15−0)
鋭く切り裂くようなクロス。
相手の読みの逆。だが、それは“読み負け”ではない。
初めからそうなるように設計された一手。
(30−0)
サーブ後、動かなかった。
相手が勝手にミスした。
九条の“静止”が、圧となって先に動かせた。
(40−0)
ドロップショット。予想外のように見えたが、
そう思わされた時点で、もう“操作”は完了していた。
(GAME KUJO)
すべてが完了した時、
ようやく彼のまばたきが落ちた。
その一瞬、彼の中で何かが「更新」されたように
周囲の空気が、ほんのわずか震えた。
でもそれを感じ取れる者は、
このコート上に、もう誰もいなかった。
【第12ゲーム】無響室の王、止まらず
第12ゲーム。
開始直後、相手の打球はネットに触れてわずかに軌道を変え、ライン際に落ちた。
九条は動かなかった。
拾わなかったのではない。切り捨てたのだ。
得点は相手についたが、空間の空気は揺れなかった。
スコアは進んでも、支配は揺るがない。
この時点で、それを正確に理解していたのは、コートに立つ二人と、チーム九条だけだった。
動けば届いた。でも、動かないほうが正しい。
……意図的に1ポイント譲った。
……準備運動、終わったか。
—セットポイントから決着へ。
スタンドがざわめいている。
だが、その音は届かない。
──ここは、王の無響室。
九条雅臣が、最後のサーブに入る。
動きは、なめらか。
呼吸は、整っている。
気配は、──ない。
(40−15)セットポイント。
観客も、対戦相手も、そしてカメラ越しの誰もが、
「これが最後のポイントになる」と感じていた。
だが九条は、その空気すら遮断していた。
それは、あまりに自然で、
あまりに機械的な一打だった。
フォームに無駄がなく、
振り抜きに迷いがなく、
そして──音がなかった。
ネットを越えた瞬間、ボールは地面に吸い込まれるように沈み、
相手はただ、棒立ちになった。
無音のまま、1セット目が終わった。
握られた拳もなければ、
叫びもなかった。
ただ、スコアボードが数字を更新しただけ。
観客の拍手が少し遅れて波のように広がり、
そのざわめきの向こうで、
彼の眼差しだけが“まだ次”を見ていた。



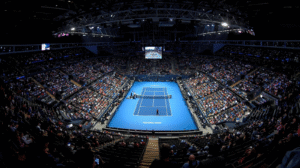

コメント