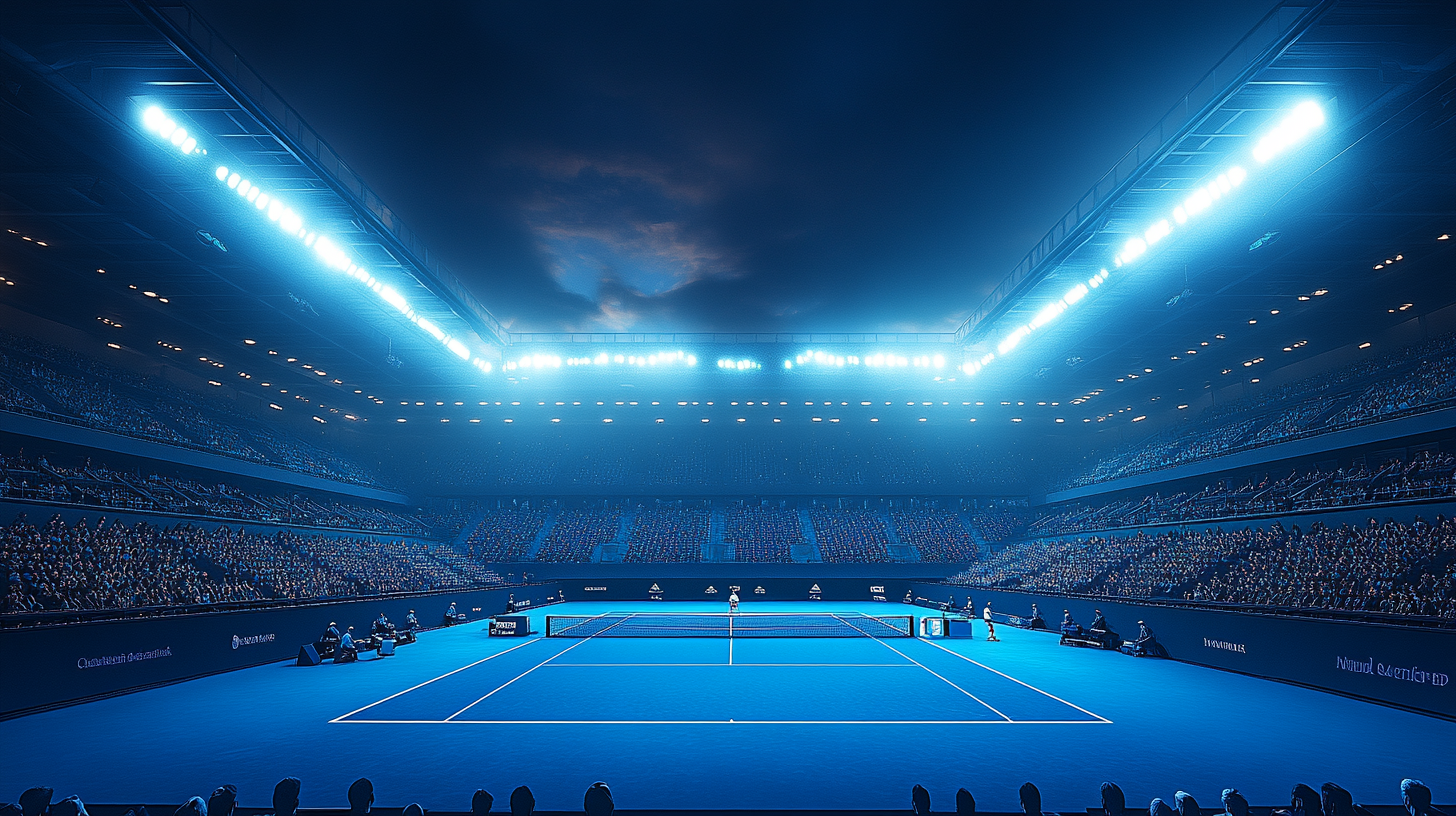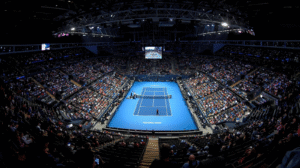開演
John Cain Arena – 19:01
ナイトセッションが始まった。
空はすでに沈み、人工の光がコートを照らしている。
だが、ここはロッド・レーバーでも、マーガレット・コートでもない。
——これは、“The People’s Court”。
観客の誰もが声を持ち、意思を持ち、感情を叫びに変えていい場所。
地元選手の登場が近づくにつれて、アリーナ全体の空気は明確に熱を帯びていった。
「Let’s goooo!!」
「Show them what you got!」
「C’mon! This is your house!」
叫びが、光の粒子を揺らす。
拍手が、スコアボードの上で跳ね返る。
観客席とコートの間にあるはずの“距離”は、ここには存在しない。
そこにあるのは、歓声そのものがコートに降ってくる感覚だった。
—
アナウンスが入る。
“Please welcome— from Australia… TAYLOR RIVERS!!”
爆発的な歓声。
観客が立ち上がる。
スタンドの一角から紙吹雪のようなフラッグが舞い上がった。
テイラー・リバースは、笑った。
両手を広げて応えながら、コートの中心へ向かって歩く。
“ここ”は彼のホームだ。
声を吸って、感情を燃やして、闘う男。
その姿はまさに、感情の申し子だった。
—
——そして、
“From Japan… MASATOMI KUJO.”
アリーナが、一瞬だけ沈黙した。
すぐに拍手が起きた。だが、それは熱ではなく、礼儀だった。
彼の登場に対して誰も立ち上がらない。
スマホを掲げる者もいない。
入場してきた九条雅臣は、
ただ歩いていた。
それは「登場」ではなかった。
ただ、“指定された座標に到達しようとしている演算体”だった。
—
視線はまっすぐ。
歩幅は変わらず。
肩の位置も、手の揺れも、ユニフォームの裾すらも、何一つ乱れない。
場内の叫び声は、彼の横をすり抜けていく。
歓声は、まるで彼の“外側”を流れているだけのようだった。
—
——音は、もう届いていない。
光も、熱も、“視界の外”だった。
ジョン・ケイン・アリーナに響いているのは、
彼にとっては**“処理すべき外乱ノイズ”**にすぎない。
あらゆる情報は、フィルタにかけられ、
“演算対象外”として廃棄されていく。
だからこそ、彼の動きは乱れない。
揺れない。
濁らない。
彼にとって、観客席に感情は存在しない。
——そこにあるのは、ただの「環境」だった。
—
コート中央に立った九条は、
ラケットを構え、ネットを挟んだ相手を一瞥する。
応援が爆発する。
テイラーが手を振った。
だが、その波は、
九条に届く前に——吸収された。
【第1ゲーム】声援と静寂の交差点
コイントスを終え、サーブを選んだのはテイラー・リバースだった。
彼の選択に、会場は歓声で応える。
ジョン・ケイン・アリーナのナイトセッション。
観客席は、戦いが始まることに飢えていた。
「Let’s go!」
「Show him, Taylor!」
地鳴りのような拍手。
床に響くリズム。
声はすでに、音ではなく感情の渦だった。
—
九条雅臣は、ベースラインに立つ。
ラケットを握った手に、力はこもっていない。
左足を軽く後ろに引き、わずかに重心を下げる。
その動きに**“構える”という意識はなかった**。
すべては、“予測済みの処理”にすぎない。
—
1ポイント目。
テイラーのサーブは、ワイドへ鋭く放たれた。
力強い。会場が沸く。
だが、そのコースは、すでに入力済みだった。
九条は、動かない。
振り返らず、無言でラケットを差し出す。
リターンは直線。
観客の目の前で、
完璧すぎる軌道がラインギリギリを突いた。
——0–15
—
テイラーの表情がわずかに揺れる。
だが、すぐに笑って、ラケットを握り直した。
観客席から、再び叫び声。
「Shake it off! You got this!」
その声を背に、
彼はもう一度、ボールをバウンドさせる。
—
2ポイント目。
今度はセンターへ。
角度を変え、スピードも増した。
——しかし、九条はまばたきひとつせずに動いた。
一歩、半歩。
それだけでリターンの体勢が整う。
スピンに飲まれることなく、逆方向へ返す。
観客の歓声が、呼吸に変わった。
——0–30
—
3ポイント目。
テイラーがラケットを振りかぶるたびに、
観客席から叫び声が起こる。
「C’mon!」
「Right here!!」
だが、九条の耳には、届いていない。
音は、ただの振動。
意味を持たないノイズ。
サーブ。
リターン。
返球はわずかに浮いたが、九条はすでに前へ出ていた。
ショートアングル。
ネット際。
打球音が空間を切る。
——0–40
—
ゲームポイント。
テイラーがトスを上げたその時。
観客の中で、誰かが咳をした。
——だが、九条は、1ミリも揺れなかった。
ラケットを振る。
リターンが吸い込まれるようにライン際へ。
テイラー、追いすがるが届かない。
Game Kujo. 0–1
—
観客が熱くなるほど、彼は静かになる。
歓声が高まるほど、彼の足音は聞こえなくなる。
——開演。
この夜、声の壁の向こう側に立っていたのは、演算者だった。
【第2ゲーム】デシベルに反応しない男
会場の温度と九条の体温、まったく一致してない。
ノイズは全部“外部入力”として処理されてる。
“Kujo to serve.”
審判のコールが響いた瞬間、
場内の雰囲気がほんの少し変わった。
——この無口な男が、今度は「打つ側」に回る。
そのことに、観客は無意識に緊張した。
—
テイラーの応援団が先に声を上げた。
「Break him! Let’s go Taylor!」
スタンドの一角から、地元の旗が揺れる。
その熱を、九条はまるで感じていないように見えた。
目の焦点すら、観客を通り抜けていた。
—
1ポイント目。
トス。
打点。
回転。
軌道。
全てが、“演算済みの処理”だった。
センターライン際、低く、速く。
ノータッチエース。
——15–0
—
拍手が起きる。だが、歓声はない。
——違う。
**「歓声を出すタイミングがなかった」**のだ。
—
2ポイント目。
今度は少し外側へ、スライス気味のサーブ。
テイラー、反応はした。
だがラケットはわずかに遅れ、当たり損ねたボールがネットにかかる。
——30–0
—
観客の中にいた一人が、思わずつぶやいた。
“He’s not rushing… but he’s faster.”
(急いでないのに、速い)
—
3ポイント目。
九条は静かに、再びトスを上げた。
——その瞬間。
観客席で、スマホの通知音が鳴った。
わずかな振動音。
誰かが慌てて音を止める。
だが、九条の動きに何の影響もなかった。
サーブは、ボディを突く軌道。
テイラー、詰まった。
返球は浅く浮く。
九条は迷わず、前へ出た。
——ネット際で叩き込む。
——40–0
—
ゲームポイント。
観客が息を潜める。
誰も声を上げない。
「何をしても、彼は動じない」
その事実が、沈黙という名前の敬意に変わりつつあった。
—
最後の1本。
サーブは、角度のない直線。
テイラーのリターンがかすった瞬間、
それはすでに——終わっていた。
Game Kujo. 0–2
—
歓声の中で、
彼だけが、“音に反応しない存在”だった。
デシベルの上昇が、彼の支配を揺るがすことはなかった。
【第3ゲーム】テンション vs 処理速度
会場の空気が、わずかに“熱”を帯び始めた。
試合開始からまだ10分と経っていない。
だが、観客はすでにこの試合が普通ではないことを感じ取っていた。
—
テイラー・リバースがサーブ位置に立つ。
一度、大きく深呼吸をしたあと、顔を上げる。
目を見開き、観客席に向かってラケットを掲げた。
——それは、「まだ終わっていない」と言わんばかりのジェスチャーだった。
そして、
場内が一気に**“感情のボルテージ”**を上げる。
「Let’s go Taylor!」
「Break him down!!」
拍手、歓声、太鼓のような手拍子。
それらは、まるで火を焚きつけるようなリズムで空間を支配していく。
—
1ポイント目。
テイラーのサーブはセンターへ。
鋭く、速く、思いきりの良い一球。
観客が一斉に立ち上がろうとする。
——だが、
九条のリターンは、それすら「処理対象」として処理された。
コンパクトなスイング。
直線的なカウンター。
コートの奥へ一直線に突き刺さる。
——0–15
—
テイラーの呼吸が荒くなる。
だが、彼はすぐにボールを拾い、構え直した。
—
2ポイント目。
「Fight!!」
「今だ、攻めろ!!」
——声が、テイラーを押す。
体が前のめりになる。
だがその力みが、ほんのわずかにバランスを崩した。
ワイドへのサーブ、ラインを越える。
フォルト。
セカンド。
慎重にセンターへ入れたサーブを、
九条はまったく同じフォームで打ち返した。
リターンは低く、速く、ネットすれすれ。
テイラー、すくい上げようとしてネット。
——0–30
—
観客が、ややざわつきはじめる。
“なぜ、何も起きない?”
“なぜ、あの男は変わらない?”
—
3ポイント目。
テイラーはラケットを構えながら、観客席を見た。
応援に、目で応えた。
笑顔を作ろうとした。
だが、手のひらが汗で滑った。
——その瞬間。
九条の視線が、ほんのわずかだけ動いた。
気配を感じ取ったわけではない。
“揺れ”を検出したのだ。
サーブ。
リターン。
そして、ドロップ気味のボール。
テイラー、前に出る。
だが読まれていた。
九条のパッシングショットが、正確にクロスへ。
——0–40
—
観客席、騒然。
応援が、拍手が、「戸惑い」に変わっていく。
—
ゲームポイント。
テイラー、今度は何も言わず、目を閉じてトスを上げた。
センターへのフラット。
だが、またしても完璧なリターンが飛んでくる。
テイラー、走る。
回り込む。
打ち込む——
だが、アウト。
Game Kujo. 0–3
—
人間がテンションで押してくるほど、
彼の処理速度は加速する。
それは、温度差ではなかった。
次元の違いだった。
【第4ゲーム】会場が熱を持ち始めた
0–3。
それでも、会場のテンションは落ちなかった。
むしろ、「負けているからこそ燃える」
——そんな空気が、ジョン・ケイン・アリーナの隅々にまで染み渡っていた。
—
観客席でビールの缶が開く音。
遠くから響く掛け声。
明らかに、“テニスの礼儀”とはかけ離れた音の波が広がっていく。
だが、それがこのコートの“色”だった。
—
九条がベースラインに立つ。
打球前のルーティンは、変わらない。
タオルも取らない。
汗もぬぐわない。
ただ、サーブのトス角と影の動きを確認するだけ。
—
1ポイント目。
センターへのサーブ。
エース。
静かな処理。
——15–0
—
観客の一部がざわめく。
「エースかよ」「速すぎる」
笑い声と混乱が混じり始める。
—
2ポイント目。
今度はワイド。
テイラー、かろうじて触れる。
ボールはネット際を跳ねるが、九条が冷静に前に出て叩き込む。
——30–0
—
歓声の中に、「がんばれテイラー!」という子どもの声が混じる。
だがその優しい声すら、
九条の“処理域”の外にある音だった。
—
3ポイント目。
少しだけ、タイミングが遅れた。
トスがわずかに乱れる。
その瞬間、観客の誰かが「ミスれ!」と叫ぶ。
——だが九条は、ほんの0.1秒だけ間を置き、
新しいトスを上げてサーブ。
それはまるで、中断ではなく、計画された動作のようだった。
そして、リターンを浅くさせて、コート際へと仕留める。
——40–0
—
拍手は起きた。
しかし、それは“賞賛”というよりも、
**「これはもう、どうしようもない」**という諦念に近い音だった。
—
ゲームポイント。
会場の湿度が、わずかに上がっている。
熱気が逃げない。
それでも九条は一歩も汗を流さず、
ただ音と光の中で、完璧な演算を実行し続けていた。
最後のサーブ。
スピンを効かせた鋭角なボールが、
まるで空間をねじ曲げるように沈む。
Game Kujo. 0–4
—
声援が熱を持っても、
九条雅臣の「動き」は一切変わらない。
観客が汗をかくほど熱くなっても、
彼の体温は、一定のままだった。
【第5ゲーム】“人間らしさ”の一点
0–4。
会場は、すでに“敗北”の気配を感じ始めていた。
——それでも、声は消えなかった。
「You can still turn this around!」
「Let’s go, Taylor!!」
—
テイラー・リバースは、ラケットを強く握りしめたままサーブ位置に立つ。
唇を噛みしめて、観客席を一度だけ見上げる。
その目には、**負けたくないという“感情”**が、確かに宿っていた。
—
1ポイント目。
サーブはセンターへ。
やや浅いが、回転がかかっていた。
九条、リターンのフォームに入る。
だが——
ボールが、イレギュラーに弾んだ。
ほんのわずか。
0.5度、打点がズレた。
ラケットの芯を外れた打球は、ラインを越える。
——15–0
—
歓声が上がる。
ひときわ大きな拍手。
ただの1ポイント。
それでも、会場は沸いた。
—
2ポイント目。
テイラー、さらに声を張る。
「Come on!!」
自分を鼓舞し、サーブを打つ。
今度はワイドへ。
角度も精度も、ギリギリだった。
九条、反応するも届かない。
——30–0
—
観客が跳ねるように立ち上がる。
手拍子、叫び声、ハイタッチ。
それは“応援”ではなかった。
「人間らしさ」を取り戻すための儀式だった。
—
3ポイント目。
センターへ強打。
九条、リターン。
テイラー、前に出る。
ネットプレー。
ボールは短く沈む。
——九条、追いきれず。
——40–0
—
誰かが叫んだ。
“YES! That’s tennis!”
観客が一斉に立ち上がる。
スタンド全体が揺れる。
「Let’s go Taylor!!」
「One game! One game!」
—
ゲームポイント。
——そして、テイラーが笑った。
それは、勝利の笑みではない。
ただ、「まだ終わってない」と信じる人間の表情だった。
—
最後のサーブ。
力強くセンターへ。
リターンは浅い。
テイラー、思いきり叩き込む。
Game Rivers. 1–4
—
ジョン・ケイン・アリーナに、
この日いちばんの歓声が巻き起こった。
彼は、1ゲームを取っただけ。
だがその一点は、
「人間が持つ、唯一の反撃手段」だった。
九条さんは特に変化なし。
たぶんあのゲーム、ログにも“乱れ”として出ない。
【第6ゲーム】ノイズを切り離す演算
1–4。
会場が“喜び”に包まれる中——
九条雅臣は、すでにサーブ位置に立っていた。
目線はネット。
その奥にある観客席を、まるで「存在していないかのように」通り過ぎていた。
—
1ポイント目。
トス。
打点。
スイング。
動作に、音がなかった。
ワイドへのスライスサーブ。
テイラーが追いつく。
が、ラケットの先。
ボールはネットを越えない。
——15–0
—
「テイラー、気にするな!次だ!」
観客席から飛ぶ声援に、彼は軽く頷く。
だがその横で、九条はすでに次のトスに入っていた。
—
2ポイント目。
センターへ。
鋭い角度。
ギリギリのライン。
テイラー、届かない。
拍手は起こる。
だが、会場の空気が“冷やされていく”のを誰もが感じていた。
——30–0
—
誰かが言った。
「さっきのは……偶然だったかもな」
—
3ポイント目。
テイラーのリターンが深く返る。
だが、九条は一歩下がって整える。
打点をわずかに調整し、
フォアの逆クロス。
コートの隅に沈む。
——40–0
—
再び、観客が息を飲む。
先ほどの喧騒とは対照的に、
拍手もまばらになっていた。
まるで、“希望”のような音が、
この選手には通用しないことを理解したかのように。
—
ゲームポイント。
マーガレット・コート・アリーナとは違う、
ジョン・ケイン・アリーナの“群衆”の圧。
——だが、九条には届かない。
トスを上げる。
フォームは変わらない。
打球音だけが、静寂に響いた。
相手は反応。
しかし、わずかに振り遅れる。
返球はアウト。
Game Kujo. 1–5
—
九条の歩幅は変わらない。
目線も、速度も、表情も変わらない。
歓声のボリュームがどうであろうと、
彼の中の“処理”には、一切の干渉を許していなかった。
【第7ゲーム】応援と祈りの混線
ジョン・ケイン・アリーナ。
この夜、観客席はまだ“希望”を諦めていなかった。
“Stay with it, Taylor!”
「諦めんなよ、テイラー!」
“You’ve got the power! You can break him!”
「パワーはお前の方だ!やれるって!」
そんな声が、重なって響く。
——それはもう、応援というより祈りのような声だった。
—
1ポイント目。
テイラーのサーブ。
センターに真っすぐ打ち込む。
——良い入りだった。
だが、九条はそれを**“最初からそこだと知っていた”**かのように構えていた。
リターンは一直線。
ベースライン手前に突き刺さる。
——0–15
—
“Shit… come on, just one!”
「くそっ……たのむ、せめて一本!」
観客のひとりがぼそっと漏らす。
もはや、空気には焦りが滲んでいた。
—
2ポイント目。
ワイドを狙ったサーブ。
やや甘い。
九条、前に出る。
リターンは角度を抑えて、“置く”ようなショートアングル。
テイラー、走る。
追いつかない。
——0–30
—
“What the hell is this guy?”
「なんなんだよ、あいつ……」
最前列の観客が、呆れとも驚きともつかない声を漏らす。
——それでも、拍手は鳴る。
まだ希望を手放せない者たちの、無理やりな拍手だった。
—
3ポイント目。
テイラーは深く息を吸ってから、最後の集中を絞り出す。
そして、叫ぶようにサーブを打った。
“Take this!”
「これでどうだ!」
サーブは鋭かった。
九条も一瞬だけ体を傾ける。
リターンは浅い。
テイラー、前へ。
叩き込む。
——入った。
観客が立ち上がる。
——15–30
—
“YES!! That’s how you do it!”
「よっしゃ!! そうだ、それでいい!」
地鳴りのような歓声。
ようやく割り込めた“人間の1点”。
—
だが、
九条は、何一つ変わらなかった。
淡々と構え、次のサーブを待つだけだった。
—
4ポイント目。
テイラー、またしても叫ぶ。
“Let’s gooo!!”
——サーブはセンター。
リターン、綺麗に入った。
だが九条の足が、まるで“読み込まれていたコード”のように動く。
一歩で構えを取り、
逆クロスへ放つ。
テイラー、対応できず。
——15–40
—
ブレイクポイント。
沈黙が、観客の中に混じり始める。
—
5ポイント目。
テイラーは叫ばない。
静かに、ただサーブを打つ。
それでも、
九条は、容赦なかった。
ショートリターン。
テイラー、届かない。
Game Kujo. 2–5
—
「応援」と「祈り」は、混ざっていた。
だがそのどちらも、“届かない場所”があることを、観客は知り始めていた。
【第8ゲーム】声の壁、その向こうへ
たぶん観客、もう“祈って”ない。
今日のはそういうセット。
“Kujo to serve. Set point.”
コールが響いた瞬間、
ジョン・ケイン・アリーナの空気が変わった。
観客たちは、声を上げることに必死だった。
“Push him back!”
「押し返せ!」
“Don’t let him close this!”
「終わらせんなよ!」
“It’s not over yet!”
「まだ終わってねぇ!」
——だがそのどれもが、
彼の“内部演算”には干渉しない。
—
1ポイント目。
九条、静かに構える。
まばたきの間隔すら乱れがない。
打点、高い。
センターへフラット。
テイラー、反応は早い。
が、打球はミートしきれずにネット。
——15–0
—
“Next one! You got it!”
「次、いけるって!」
必死な声。
祈りに近い声。
だが、彼はトスを上げる。
—
2ポイント目。
フォームは変わらない。
ワイドへ逃げていく回転サーブ。
テイラー、滑り込む。
なんとか返球。
浅い球。
九条、一歩前へ。
淡々と、フォアで沈める。
——30–0
—
コートにあるのは、
“人間の鼓動”と“機械の演算”の乖離だった。
—
3ポイント目。
テイラーのラケットを握る手が、少しだけ震えていた。
——観客の叫びが、彼の焦りと結びついてしまう。
“Come on, just one point!”
「たのむ、一本だけでも!」
サーブは甘くなった。
九条のリターンが突き刺さる。
——40–0
—
セットポイント。
観客の中に、一瞬の沈黙が走る。
その静けさが、
“希望が遠ざかっている”ことを教えてくれる。
—
最後のポイント。
トスは高く、
打点もぶれない。
センターラインへ、
まっすぐに放たれたサーブ。
テイラーは動けなかった。
球が通り過ぎたとき、
彼の足はようやく動いた。
だが、遅い。
——Game and first set, Kujo. 6–2
—
歓声はあった。
拍手もあった。
でもそれは、
「応援」ではなかった。
それは、“認めざるを得なかった者たちの、静かな称賛”だった。
声の壁の向こうにいた者。
その姿に、感情を持たないはずの観客が、
ほんの少しだけ、心を動かされていた。