戻る気のない朝
夜。
試合後に食事とシャワーを済ませ、志水と早瀬が交代で体をほぐし続け、神崎が深度のチェックを続け、レオンが栄養補給を管理した。
九条は眠っている間でさえ、筋肉の収縮が均一か、呼吸が乱れていないか、何度も確認されていた。
そして翌朝。
意外なほど、九条はすっきりしていた。
目を開け、一瞬だけぼんやり視線を漂わせるものの、すぐに“いつもの朝”の動きに戻る。
ベッドから起きる動作はスムーズ。
頭の重さも、精神の揺れもない。
シャワーを浴び、レオンの用意した試合用の朝食を食べる。
驚くほど事務的だった。
余計な迷いが一切ない。
ただ、神崎は気づいていた。
九条の瞳の奥に“昨夜の影”が薄く残っていることに。
完全には戻り切っていない。
だが、戦うには十分。
普通という異常値
控室に入ると、神崎が最終チェックに入った。
ライトで瞳孔の反応を確認し、肩・首・腰の緊張、左右差、呼吸の深さ、重心移動の癖、ふらつき、目線の安定。
あらゆるチェックを、慎重すぎるほど慎重に。
志水と早瀬も横でメモを取り、九条の動きの一つ一つを記録していく。
最後に神崎が九条に向き直った。
「気分はどうだ?」
九条は短く答える。
「……普通」
「頭の重さは?」
「無い」
「視界は?」
「……問題ない」
嘘ではない。
ただ、“強がりでもない”。
本当に問題は無い。
だが神崎は、なおも慎重だった。
「昨日の状態を考えれば、この回復は異常だ。だが――九条、お前は大丈夫か?」
九条は一瞬だけ考え、言葉を選ばずに答えた。
「……やる。それだけ」
神崎はため息をつき、蓮見は苦笑し、氷川は一言皮肉のように呟いた。
「…準備万端ですね」
ただし全員、同じことを思っていた。
今日の相手は、昨日のようにはいかない。
そして九条も、昨日のようにはいかせないほうがいい。
それでも試合は来る。
準々決勝、開始まで数時間。
九条はテーピングを巻き直し、静かにラケットバッグを担いだ。
その背中は、どこまでも静かで、それでいて、またどこか“深いところ”に沈もうとしている気配を帯びていた。
勢いの名を持つ敵
準々決勝の相手は、フランスの選手アレクサンドル・フィオル。
・身長186cm、体重82kg
・右利き/両手バック
・強烈な初速のフォアと、ライン際を狙い続ける高精度の攻撃
・ジュニア全仏準優勝、ダブルス優勝
・18歳でプロ転向
・21歳にしてツアー優勝3回、現在ATPランキング18位
・コーチはセバスチャン・グロージャンとセルジ・ブルゲラの二人体制
・まだ荒削りだが、爆発力はツアー随一
プレースタイルは、攻撃が止まらない“アグレッシブ・ベースライナー”。
サービスの初速は190km台後半、フォアの展開力は他の若手の中でも図抜けている。
ただし、メンタルはまだ若い。
熱くなると荒くなる。
冷静になると手がつけられない。
クレーとの相性も悪くなく、何より“若い勢い”がある。
リベラとは違い、粘りではなく「点を取りにくる強者」だった。
蓮見は資料を見ながら言った。
「若手で勢いあるやつか……。まあ、当たるよな」
氷川が冷静に返す。
「爆発力は危険ですが、安定感はまだ未成熟です。九条さんが今日“普通”なら問題ありません」
蓮見は九条の顔をちらりと見る。
「普通ならな」
選手の情報を一通り整理しながら、蓮見はほっとしたように息を吐いた。
「ここに来て粘り型じゃないのは助かるな。クレーとの相性も最良ってほど良くはないし、しかも若い。九条との相性としては悪くない」
氷川が淡々と補足する。
「昨日のことを思えば、あまり長時間化する相手は避けたいところですからね」
その言葉に、神崎の表情が初めて崩れた。
普段は冷静な医師の顔。
だが今日は、笑ってごまかす余裕がない。
「……正直、昨日の深さは限界に近かった。戻っただけでも奇跡だ。今日が粘り型だったら、どうなっていたか分からない」
そう言う神崎の口調は固く、言葉の端々に“医者としての不安”が滲んでいた。
蓮見が腕を組む。
「でもフィオルのタイプなら、一気に持っていける可能性もある。ハードが得意な相手だ。赤土で暴れようとすりゃ、多少は雑にもなる」
「爆発力は怖いですが、長期戦にはなりにくいでしょうね」
氷川が頷いた。
レオンが食事の準備を整えながら言う。
「九条さんが普通でいられれば、ね」
一瞬、控室に静けさが落ちた。
“普通でいられれば”。
その一言が、このチームの誰もが抱えている恐怖を正確に突いていた。
昨日のように深く入り込めば勝てる。
勝てるが、そのたびに戻すのがどんどん難しくなる。
戻れなくなる日が来るかもしれない。
それでも試合は待ってくれない。
準々決勝は数時間後だ。
神崎は深く息を吐き、九条の方に向き直った。
「……よし。何かあったらすぐ言え。無理をするな。今日は絶対に“戦い方を間違えるなよ”」
九条は短く答える。
「分かってる」
声は落ち着いていた。
ゆらぎはない。
ただ、それが安心材料になるかは誰にも分からない。
蓮見がラケットバッグを肩にかける。
「じゃ、行くか。準々だ」
控室の空気が、少しだけ引き締まった。
今日の相手は若く、強く、勢いもある。
だが、昨日のような“消耗戦”にはならない。
なるべくなら、ならないでほしい。
九条は淡々と歩き出す。
その背中に、昨日の影はほんの薄く残ったままだった。
若き強者の自信と警戒
フィオル陣営は、選手ラウンジの奥で輪になっていた。
コーチのグロージャン、ブルゲラ、そしてフィオル本人。
フィオルはヘッドホンを首に下げたまま、軽く肩を回しながら笑っていた。
「昨日もフルパワーだったみたいだな、九条。でも、俺は引かねぇぞ」
若さ特有のまっすぐな自信。
しかし、それだけではない。
九条という存在には、確かに“警戒”が宿っている。
グロージャンが言う。
「いいか、アレックス。九条は昨日の試合で深い集中に入っていた。あれを今日も出されたら厄介だ」
ブルゲラが淡々と続ける。
「だが、彼の疲労は確実に残っている。お前の攻撃力で最初に主導権を握れ。何より……長いラリーに付き合うな」
フィオルは頷き、笑った。
「分かってるよ。昨日の粘り合いをもう一度やれる体じゃないはずだろ?10代やそこらの選手でもない。俺は最初からぶっ叩く」
軽く聞こえるが、内容は正しい。
フィオルは若い反面、分析能力が高い。
そして、勢いがある。
勢いがある若手は、クレーでも危険だ。
フィオルは立ち上がり、ラケットバッグを担いだ。
「よし。フランスにいいニュースを持って帰るぞ」
若さの熱と自信が、その背中に満ちていた。
二つの温度が並ぶ場所
通路。
片側にはフィオル陣営の熱気。
片側には九条陣営の無音。
対照的だった。
フィオルは表情が明るく、肩の力も抜けている。
隣のスタッフと軽く笑い合っている。
一方で九条は、呼吸を静かに整えながら前を向いていた。
動きはスムーズ。
昨日の影はほとんど消えている。
ただその静けさは、異様なほど深かった。
蓮見がぼそりとつぶやく。
「……落ち着きすぎじゃね?」
氷川は真顔のまま返した。
「通常運転です」
「いや、昨日の今日だぞ……見慣れてる俺でも違和感あるわ」
レオンが苦笑する。
「ここまで平然とできるのが、九条さんの怖いとこだよね」
神崎は視線を九条から離さない。
「入ってはいない。ただ、いつでも入れる“手前”で止めてる」
警戒の色が濃い。
入口のカーテンが開き、センターコートの光が差し込む。
二人のシルエットが並んだ瞬間、観客席がざわめきに変わる。
アナウンスが響き、フィオルは拳を軽く突き上げ、九条はただ一歩前に踏み出した。
温度差が、そのまま勝負の構図になっていた。
荒れる前提の試合
● 第1ゲーム
フィオルのサーブで始まる。
初球。
193kmのフラットサーブがセンターに刺さる。
九条、反応はするが返せない。
フィオルは迷わず畳み掛ける。
フォアのクロス。
バックのライン際。
前に入り、再びフォア。
蓮見がうなった。
「うわ……本気で“短期決戦”狙ってるな」
氷川は画面を見て即座に言う。
「攻撃の質は高い。ただ、精度にムラがあります」
そして実際、フィオルは3ポイントを一気に取り、40-0まで持っていった。
若さの勢い、爆発力。
昨日とはまったく違うタイプだ。
しかし。
九条は、全く焦っていなかった。
● 第2ゲーム
九条のサーブ。
初球は、大きな力は入れず――
ひどく“深い”一本だった。
スピードより、精度。
あえてフィオルに打たせる球。
フィオルは迷いなく叩く。
強烈なフォア。
だが、アウト。
蓮見は腕を組む。
「九条、相手の勢いを利用してるな……」
氷川が頷く。
「フィオルの攻撃テンポを計っていますね。昨日のように粘る必要はない。流れを見ている段階です」
九条は淡々と深い球を続け、フィオルは強打を混ぜるがミスも増える。
スコアは40-30。
最後は九条がワイドへサーブを流してキープ。
互いに“入りの形”を作った。
● 第3ゲーム
フィオルは、さらに攻撃に振る。
フォアを叩き、バックをラインに通し、躊躇なく前に入る。
九条は受ける。
しかし、受けながらも球質を変えていた。
昨日のような深すぎる球ではない。
ただ、フィオルの強打の“逆を突く”球。
蓮見が小声で言う。
「これ、どっちに転ぶか読めねぇな……」
氷川は目を細める。
「フィオルの勢いが本物であれば、九条でも押されます。ただ、九条の読みが当たれば……一気に流れが傾く」
二人の打球が赤土を滑り、スタンドは呼吸を止めて見守る。
昨日の粘りとは違う。
今日は“鋭さ”と“勢い”の衝突だった。
最初の三ゲームで、観客はすでに理解していた。
この試合、長引けば荒れる。
短くても荒れる。
九条の静、フィオルの熱。
どちらが先に音を上げるか。
勝負はそこにあった。
読み合いの火蓋
第3ゲームを境に、フィオルの目つきが変わった。
それは、勢いに乗った若者のそれではない。
獲物を見極める側の視線だった。
――このまま殴り続けても、落ちない。
そう悟った瞬間の、切り替え。
次のラリーで、それははっきりと現れた。
強打。
もう一発、強打。
観客が「来る」と身構えた、その直後。
フィオルは突然、スライスを沈めた。
九条の体が一瞬だけ、前に流れる。
そこへ、ショートクロス。
会場がどよめいた。
若い。
だが、雑ではない。
間の取り方が、異様にうまい。
蓮見が舌打ち混じりに呟く。
「……勢いだけのガキじゃねぇな。完全に“九条用”に対策してきてる」
氷川は視線を外さずに答えた。
「対応力があります。年齢の割に、ですが」
九条は走った。
走って、追って、追いつく。
だが、一本だけ――
返球が、わずかに浅くなった。
その瞬間を、フィオルは逃さない。
一歩、前へ。
バックのダウン・ザ・ラインが、赤土を切り裂く。
完璧だった。
スタンドが沸き、フィオルは拳を握る。
最初に崩れるのは、お前だ。
そんな意志が、その背中から滲み出ていた。
だが。
九条は、崩れない。
崩れないどころか――
その動きは、さらに静かになった。
速さが消えたわけではない。
力を抜いたわけでもない。
ただ、熱が引いた。
冷たさだけが、増していく。
蓮見が、思わず声を落とす。
「……まずいな、これ」
レオンが横目で見る。
「昨日と同じ?」
「いや、まだ一歩手前だ。でも――」
蓮見は言葉を切った。
「あの顔は、“潜る”直前だ」
九条の視線は、ボールを追っていなかった。
打点でも、回転でもない。
次に起こる軌道を、見ている。
フィオルが強く叩けば、九条は“その次”の強打の位置に立つ。
フィオルがテンポを落とせば、九条は、さらに一段落とす。
読む速度が、噛み合い始めていた。
勢いと読み。
速度と未来。
二つが交差した瞬間、会場の空気が、ひたひたと張り詰めていく。
(これ以上、深く沈むな。自分を壊しに行くな)
蓮見の願いは、声にならない。
だが、その不安は、表情にありありと出ていた。
動きの激しさに対して、目線が静かすぎる。
昨日と同じ静けさが、また、コートに降り始めていた。
迷いが生まれる瞬間
スコアは接戦。
互いに攻撃的で、互いにミスも出る。
でも、その裏で“質”が変わっていた。
● 4-3(九条)
フィオルのサーブゲーム。
3本めのフォアを叩いたところで、九条のバックが完璧なタイミングで逆クロスへ。
フィオルが止まる。
(読まれてる……?)
若い選手にとって、“読まれている実感”ほど怖いものはない。
● 4-4(フィオル)
次のゲームは、九条があえて浅い球を混ぜ、フィオルの強打を誘う。
フィオルは迷わず叩き、そのまま押し切ってキープ。
エネルギーと自信で取り返す。
● 5-4(九条)
ここで、流れが動いた。
九条のリターン。
速度はない。
角度も派手ではない。
ただ、深い。
それだけの球だった。
それなのに、フィオルの足が――
ほんの一瞬、止まった。
踏み込むか。
待つか。
その迷いが、刹那、生まれる。
次の瞬間、ミス。
若さが、顔を出した。
蓮見が思わず息を呑む。
「……これ、どっちが若手だよ」
本来、若手は失うものがない。
追う立場で、挑む側で、
上の選手を徹底的に研究し、噛みつくだけだ。
だが、コートに立つ二人は逆だった。
追われる側であるはずの九条が、
まるで何も背負っていないかのように打つ。
ランキングを守る恐怖も、
ポイントを削られる不安も、
次の大会の計算も――
すべて、コートの外に置き去りにしている。
普通なら、背負う。
普通なら、守りに入る。
だが、九条の戦い方は違った。
失うものなど、最初から存在しない。
守る立場など、考えたこともない。
そう言わんばかりの、
無茶で、冷静で、覚悟のある選択。
若さを武器にするはずのフィオルが、
ここで初めて「考えさせられている」。
年齢ではない。
経験でもない。
覚悟の量が、コートの主導権を奪い始めていた。
● 5-5(フィオル)
だが、フィオルは折れない。
サービスゲームに全力を注ぎ、強打で流れを断ち切る。
ラケットを握る手が震えていたが、それを隠さない。
(怖い。でも、攻めるしかない)
その若さと熱だけは揺るがない。
● 6-5(九条)
九条のサーブ。
テンポを遅くし、角度を変え、また深さを取り戻す。
フィオルのミスが増える。
ただ、フィオルのミスは“強さゆえのミス”。
蓮見は頭を押さえた。
「……あぶねーなこれ。二人ともバカみてぇに強い」
● 6-6 タイブレークへ
フィオルの最後のポイントは、渾身のラインショットで取った。
若さゆえの無鉄砲さと、若さゆえの才能が詰まった一打。
九条は表情を動かさず、静かにベンチに戻る。
フィオルは息を弾ませながら笑う。
(来いよ、九条。こういう勝負がしたくて俺はここに来た)
観客席が一斉に立ち上がる。
緊張、熱、静寂。
すべてが混ざり、センターコートが震えた。
――タイブレークへ。
深さが試合を変える
6−6。
コートには、不思議な緊張が漂い始めていた。
蓮見が腕を組んだまま、ぼそりと漏らす。
「おいおい……この試合、長引かないはずじゃなかったか?」
誰も視線を動かさない中で、氷川だけがいつもの無表情で答える。
「さぁ。未来は誰にも読めませんから」
「お前は読めるんだろ、多少は……」
「九条さんの行動は読めません。過去の傾向からも」
蓮見が肩を落とした瞬間、反対隣でレオンが口を挟む。
「わざと長引かせてるんじゃなくて?」
蓮見が思わず振り返る。
「わざと?」
「攻撃型を崩すなら、最初に“長くなるぞ”って匂わせるだけでメンタルに来るよ。テンポ狂わせて、生殺しにする感じ。……単純かな?」
蓮見は眉をひそめる。
「アグレッシブな攻めがクレーで長引くことはあるが、わざと長引かせるのは九条の状態だと危険だぞ」
その会話を聞きながら、神崎が九条の顔をじっと見つめていた。
瞳孔、目線の動き、呼吸の深度、汗の量。
「……もし、わざとなら」
神崎の声が低く落ちる。
「俺は怒らざるを得ない」
普段穏やかな医師が、ここまで言うのは珍しい。
レオンがぽつりとこぼした。
「九条さん、自分の身体とか健康とか……度外視じゃん。勝つためなら“使い捨て”でもいいって顔してる」
その言葉に、蓮見も、氷川も、志水も、早瀬も、一瞬黙った。
否定できなかった。
そしてコートでは…。
● タイブレーク 3-3
フィオルの強打。
九条の深い返球。
フィオルのショートクロス。
九条のライジング。
球質が噛み合いすぎて、観客の息が止まる。
フィオルの目つきが鋭くなる。
(崩れねぇ……こいつ、本当に昨日あれだけ戦ったのか)
● 5-4 九条
九条が一つ、リターンで逆を取る。
小さくも鮮やかな一打。
蓮見が舌打ちする。
「……完全に振り切って戦ってるぞ、あれ」
神崎は顔を歪めた。
「深く入り過ぎたら、また戻すのが遅れる……!」
氷川が冷静に言う。
「本人はそんなこと全く気にしていない様子ですね」
● 6-5 九条(セットポイント)
フィオルは叫びもせず、ただ深呼吸を一回。
(負けねぇ……こんなところで折れねぇ)
フランスの若きエースの眼差しは鋭い。
サーブを放つ。
強烈。
だが――九条が返す。
深い。
重い。
ブレがない。
フィオルは踏み込む。
だがその踏み込みが、半歩遅れた。
次の瞬間。
九条のフォアの逆クロス。
白線をかすめる“音”。
主審の声が響いた。
「ポイント、九条。7−6、九条。九条が第1セットを取りました」
会場が揺れた。
赤土が震えるほどの拍手。
九条は――やはり無表情だった。
ただラケットを握り直すだけ。
勝利の裏側に潜むもの
● フィオル陣営
グロージャンが立ち上がった。
「……まずいな。メンタルが折れかけている」
ブルゲラは口元を押さえ、
「いや、まだだ。アレックスは強い。だが相手の“集中力の強さ”が予想以上だ」
フィオルはベンチで肩を上下させながら、苦く笑った。
(なんでそんな落ち着いていられんだよ……お前、昨日あの試合したんだろ)
でも、眼は死んでいない。
若さの火がまだ燃えている。
● 九条陣営
蓮見は大きく息を吐いた。
「……取ったのはすげぇけどよ、これ、勝てばまた明日試合なんだけどな?」
早瀬は淡々と記録を更新し続けている。
「データ上は問題ありません」
レオンは苦笑して肩をすくめる。
「問題あるのはメンタルのほうでしょ。こっち側の」
志水と早瀬は黙々とモニターを確認しながら、しかし顔色が少し硬い。
神崎だけは、誰よりも深刻な表情だった。
「……これ以上は深いところへ入ってほしくない。入られたら、また“戻す時間”が足りない」
蓮見も渋い顔で頷く。
「頼むから、早く終わらせてくれ……勝っても負けてもいいから、短くしてくれ……」
氷川がぼそり。
「負けるのは良くないです」
「分かってるよ……分かってるんだけどよ……!」
九条はベンチで水を一口飲み、深呼吸を一つ。
目を閉じると、今にも“深く一気に沈みそう”な危うさ。
蓮見が青ざめた。
「……おい九条、自分を捨てるな…自分を守れ…!」
しかし九条は何も言わなかった。
ただ立ち上がり、ラケットを持った。第2セットへ向けて。
支配の質が変わる
第2セット。
フィオルは、完全に開き直っていた。
初球から、200キロに迫るサーブ。
続けて、フォアの逆クロス。
コート後方を抉る、逃げ場のない弾道。
若さの勢いが、そのまま暴力に変わっている。
「……相手も、相当来てるな」
蓮見が低く呻いた。
迷いは消えていた。
恐怖を押し込み、強さだけで押し切る選択。
――引いたら、飲まれる。
だから、攻める。
その単純な結論が、プレーに直結している。
九条は――受けていた。
慌てない。
表情も変えない。
フィオルの強打を、ただ拾う。
力ではない。
読みと角度と、最小限の動きだけで。
神崎の眉が、わずかに動いた。
「……目線が、動き始めた」
三ゲーム目。
一本のラリーが、異様な長さに入った。
フィオルが叩く。
九条が返す。
深く。
正確に。
淡々と。
そして――
ふ、と。
九条は、顔ごと目線を横に送った。
反射でそれを追ったフィオルの体が、そちらへ流れる。
だが次の瞬間。
九条は、見ていない方向へボールを放った。
ノールック。
方向を確認する動作すらない。
完全にフェイントを取られたフィオルの横を、ボールが抜けていった。
「……くそっ」
若さが、そのまま苛立ちとして漏れた。
フィオルは感情を隠せなかった。
九条は――
一切、見なかった。
振り返りもせず、背中を向けて、静かにベースラインへ戻る。
その姿を見て、チームの全員が理解した。
九条はもう、ボールを見ていない。
相手を見ていない。
相手の“次の反応”を見ている。
目線で誘導し、動きを先に決めさせ、そこに打ち込む。
若さの爆発力に対して、経験が牙を剥き始めていた。
勢いで来る相手を、力で潰すのではない。
――操る。
それが、九条の選んだ勝ち方だった。
フィオルが攻めれば攻めるほど、燃えれば燃えるほど、九条はそれを受け流すように試合を動かした。
押しても、押しても、崩れない。
むしろ――
感情が前に出るたび、フィオルの選択肢は減っていく。
怒り、焦り、闘志。
そのどれもが、九条にとっては「次の一手を読む材料」に過ぎなかった。
試合は、いつの間にかフィオルが動き、九条が決める形に変わっていた。
氷川が、視線を切らずに言う。
「……暖簾に腕押し、ですね」
若いフィオルが心を剥き出しにするほど、
九条の表情は、逆に削ぎ落とされていく。
笑わない。
拳を握らない。
ポイントを喜ばない。
疲労も、苛立ちも、達成感も、外には出さない。
ただ、終わりに向かって、正確に駒を進めていく。
感情を出した者の負けだと、言葉にせず、態度だけで突きつけるように。
そこにはもう、若さと勢いの勝負はなかった。
残っていたのは、
経験が静かに勝ちを刈り取る時間だけだった。
見られていないという侮辱
――分かっているのに、止められない
分かっている。
ここで感情を出せば、状況は悪くなる。
怒れば怒るほど、相手の思う壺だ。
それは、頭では理解している。
(冷静になれ……)
フィオルは何度も自分に言い聞かせた。
自分は、感情だけで打つ選手じゃない。
準備する。
相手を研究する。
強さの根拠を積み上げて攻める。
そうやって、ここまで来た。
なのに、ネットの向こう側にいる九条は、何も変わらない。
声を出すわけでもない。
表情を歪めるわけでもない。
挑発の言葉など、一切ない。
ただ、撃ち合っているだけだ。
それなのに。
まるで、こちらを見下ろしているように見えた。
ポイントになる球を、最後まで見ない。
決まった瞬間に、もう次へ向いている。
――見なくても分かっている、という態度。
お前には分からなくても、俺には分かる。
そう言われている気がして、胸の奥に、じわりと熱が溜まる。
(……クソ)
怒るな。
ここで怒るな。
そう思うほど、怒りははっきりと形を持ち始める。
九条は、こちらを煽っているわけじゃない。
それが、逆に腹が立つ。
「お前など眼中にない」
そう言われているようで、視線を向けられないこと自体が、侮辱だった。
理解できない変化
「……九条、戦い方を変えてきたな」
蓮見が低く言う。
「相手の感情を、明らかに動かしにいってますね」
氷川は、視線を切らさずに続けた。
「珍しいです。九条さんは、こういう精神的な揺さぶりを使わない」
「使わなくても、煽ってるように見えるからな」
レオンが苦笑する。
だが今日は、明らかに違っていた。
九条の目線は、どこも見ていない。
光を宿していない。
それなのに、その目線で相手を動かしている。
テニスでは、目線は重要な情報だ。
人は、打つ方向を先に見る。
だからこそ九条が見ていない方向へボールを送るたび、相手は一拍遅れる。
さらに。
アウトになると分かっている球には、一歩も追わない。
ポイントが終われば、背を向ける。
態度は静かで、礼儀正しいほどなのに、結果だけが、相手の神経を逆撫でしていく。
だが。
九条の目には、何も宿っていない。
怒りも、喜びも、優越もない。
心が動いている様子が、どこにも見えない。
神崎が、低く言った。
「……何も考えていないのに、考えているように見せている」
全員が、言葉を失う。
「身体への負担を減らすためなのか、それとも……また、別の場所へ行ったのか」
試合中に相手を観察し、「こうすれば操れる」と理解して、即座に使い始める。
理屈としては説明できる。
だが、実際にやっていることが異常だった。
チームで見ていても、理解が追いつかない。
ただ一つ分かるのは、相手の感情が露出するほど、九条は、ますます無色になっていくということ。
それが、この試合でいちばん危険な兆候だった。
壊れるまで戦う男
「ねえ、あの戦い方さ」
レオンが視線をコートから外さずに言った。
「誰か、事前に作戦として話した?」
「いや」
蓮見は即答した。
「少なくとも俺は言ってない」
「蓮見さんが知らないなら、他はないですよね」
早瀬が短く言い切る。
「ってことは……」
レオンが言葉を選ぶ。
「あれ、九条さんが一人で考えて、その場で使ってるってこと?」
一瞬の沈黙。
早瀬は九条の動きを追いながら、慎重に口を開いた。
「……体への負担が気になります」
「普通なら、かかりますよね」
志水が続ける。
「フォームで意図を悟らせないようにして、目線と逆方向に球を出している。あれ、どこかに無理が出てもおかしくない」
その直後だった。
九条が、完全なチャンスボールに入る。
誰もがスマッシュを予想した。
――次の瞬間。
空中で体をわずかにひねり、落としたのは、ネット際へのドロップ。
フィオルが完全に置き去りにされる。
「あ……」
レオンが声を失う。
「……本来、ああいうプレーをする選手じゃないですよね」
早瀬が言った。
「九条さんは」
「トリッキーとは、真逆だ」
蓮見が低く返す。
「ってことは」
志水が言葉をつなぐ。
「自分のプレーを研究し尽くされた前提で、あえて“別の九条”を作ってきた、ということか」
「……それ、人間業ですか?」
レオンが半ば本気で聞いた。
その問いに、氷川が淡々と答える。
「九条さんに、人間であることを求めるのは」
一拍。
「もう、やめたはずです」
空気が静まり返った。
「……全豪のときみたいに」
蓮見が額を押さえる。
「誰か他の選手のプレーを、自分の中に引っ張り出してきたか」
「この相手には、この戦い方が最適だと」
志水が続ける。
「試合中に結論を出したのでしょう」
「で、効かなくなったら?」
レオンが言う。
「また、別のやつを出す」
「……」
誰も否定しなかった。
「あいつ」
蓮見が天井を仰ぐ。
「何人分の選手として、戦ってるんだよ……」
本当にやめてほしい、という声だった。
人にはそれぞれ、骨格がある。
筋肉量がある。
癖がある。
それが“個性”であり、“限界”のはずだ。
それを消して、必要に応じて別の型を被る。
――それはもう、人間の技術の話ではなかった。
神崎が淡々と言った。
「そんなことを続けてたら、どこかで壊れる」
蓮見は歯を食いしばった。
「そうまでして、なんであんなことしてるんだ、あいつ……!」
レオンは静かに九条を見つめた。
「止める気がないんだよ、九条さん自身が」
「……は?」
「全豪が終わったあと言ってたでしょ。“あの状態に入れば勝てる。確実に再現する方法を見つける”って」
華奢な見た目のシェフが、自分の手のひらの中の選手を見つめる目が、やけに痛かった。
「言えば誰かが止めるから、言わずに実行してるんだよ」
蓮見が呆れたように、怒りを帯びた声を出す。
「お前がそれを言ったら、俺らは止めるんだが?」
「でも、試合に出るのは止められないでしょ。怪我もしてない。棄権させられない。出てしまえば……もう誰の声も届かない」
氷川が小さくつぶやいた。
「テニスは個人競技ですから」
神崎は頭を抱える。
「試合が終わってから戻すこっちの身にもなってくれ……!」
レオンはほんの少し目を伏せた。
「戻りたくないんじゃない?」
全員の顔がレオンを見る。
「……何?」
「“あの世界”にずっといたいのかも。あそこなら、身体が持つ限り永遠に勝てる」
蓮見が声をひそめる。
「永遠に身体がもつわけないだろ……」
レオンの答えは短かった。
「だから――壊れるまで戦い続ける」
静まり返った控室。
誰も、言い返せなかった。
九条のプレーは、もうアスリートのそれではなかった。
ただの、戦闘マシンだった。
恐怖を知る瞬間
フィオルは、何を見ればいいのか分からなくなっていた。
普通なら、判断材料はある。
構え、目線、体重移動、踏み込みの癖。
どんな選手でも、打つ前には“兆し”が出る。
だが――九条には、それがない。
視線が定まらない。
肩の向きも読めない。
体重移動すら、意図を隠している。
(……どこだ?)
ボールが飛んでくるまで、分からない。
分からないから、構えられない。
構えられないから、下がるしかない。
フィオルは、じりじりとベースラインの後ろへ押しやられていく。
本来、攻める側のはずだった。
初速で叩き、主導権を握り、相手に考える暇を与えない。
それが、自分のテニスだった。
なのに今は――
守らされている。
意図せず、選択を奪われている。
(どうする……?)
強打か。
ネットか。
テンポを落とすか。
考えた瞬間に、もう遅い。
九条は“考える間”を与えない。
それなら、とフィオルが一歩踏み込んだ、その瞬間だった。
九条が前に出た。
(……来る?)
ネット際。
豪速球。
逃げ場のない角度。
反射で振ったラケットが、空を切る。
会場がどよめく。
(……攻めてきた?)
違和感が胸に刺さる。
九条は、アグレッシブな選手ではない。
ネットプレーを多用するタイプでもない。
なのに――
迷わせた上で、詰めてくる。
考えさせない。
選ばせない。
逃がさない。
次のポイント。
また読めない。
また下がる。
また前に来る。
また、撃ち抜かれる。
(なんだよ、これ……)
頭が追いつかない。
怒りが湧く。
焦りが混ざる。
呼吸が浅くなる。
冷静になれ、と自分に言い聞かせる。
(分かってる。ここで怯えて下がったら、もっとやられる)
分かっているのに、止められない。
ネットの向こうの九条は、何も語らない。
煽りもしない。
睨みもしない。
表情すら、ほとんど動かない。
ただ、淡々と球を打つだけだ。
腹の奥が、冷える。
フィオルは、もう何を見て戦えばいいのか分からなくなっていた。
それこそが、九条が待っている反応だと分かっているのに。
拍手の中の異常
スタンドは、熱を帯びていた。
ラリーが続くたびに歓声が上がり、信じられない角度のショットには、ため息と拍手が混じる。
「すごい……!」
「今の見たか?」
「やっぱり九条は別格だな」
強い選手同士の試合。
勢いのある若手と、絶対王者。
観客が求めている条件は、すべて揃っていた。
ポイントが決まるたび、音が跳ねる。
スーパープレイが出るたび、手が鳴る。
そこにあるのは、純粋な高揚だ。
誰も、悪気はない。
誰も、間違ってはいない。
試合に出ている以上、戦うのは当然。
勝っている選手が、さらに強くなることを、誰が止められるのか。
まして九条は、身体を壊していない。
医師のチェックも通っている。
プレーは安定し、スコアは支配的だ。
観客の目には“進化した九条雅臣”が映っている。
完成度を増し、隙がなくなり、若手の勢いすら呑み込む、絶対王者。
だが。
ベンチの空気は、違っていた。
蓮見は、拍手の方向を一度も見なかった。
氷川は、歓声が上がるたびにモニターから視線を外さない。
神崎は、九条の呼吸と目線の微細な変化だけを追っている。
志水と早瀬は、数字にならない“違和感”を必死に拾い集めていた。
盛り上がるほどに、彼らの表情は硬くなる。
強い。
美しい。
理想的だ。
――だからこそ、怖い。
勝っているから止められない。
怪我がないから引き戻せない。
結果が出ているから、異常だと言えない。
観客が「最高の試合」を見ているその瞬間、チームは「限界に近づく音」を聞いていた。
誰にも聞こえない、だが確実に積み重なっていく、内部の軋み。
拍手は祝福であり、同時に、逃げ場のない圧力でもあった。
九条は、そのすべてを背中で受けながら、何も感じていない顔で、次のポイントへ向かっていく。
王者に見えるその姿は――
生きている気配が、薄すぎた。
勝っても戻らない
5–3。
九条がリードしたまま、第2セットは深いところへ沈んでいく。
フィオルは、まだ折れていなかった。
強打を連発し、足を止めず、声も出さず、ただ“勝ちに行く”。
若さ特有の諦めの悪さではない。
トップに来る選手の“意地”そのものだった。
強烈なフォア、角度のついたバック、逆をつくスライス、ボディへのサーブ。
持てる全てを使って、九条の集中を揺らそうとする。
しかし――揺れない。
九条は表情を失い、反応速度は常識を超え、読みの精度も異常に高い。
(……化け物かよ)
フィオルは心の中でそう呟きながら、それでも前へ出る。
だが、九条の球は淡々と深く、重く、正確だった。
マッチポイント。
フィオルは最後まで攻めた。
全身で踏み込む。
最後のフォアハンドを振り抜く。
赤土を削る音。
ボールがライン際に落ちる――
ほんの数センチ、外れた。
アウト。
主審が手を上げる。
「ゲームセット。6–3、6–3。勝者、九条雅臣」
場内が大きく沸いたが、九条は反応しない。
ガッツポーズもしない。
視線を上げることもない。
ただ、ラケットを持ったまま“動作として”ネットに向かう。
まるで、勝敗がどうでもいいかのように。
握手を交わすとき、フィオルは九条の目を見た。
そこに「勝った喜び」も「達成感」も無く、ただ底が見えない“暗闇”だけがあった。
フィオルは、無意識に呼吸を止めていた。
(……こいつ、本当に人間か?)
勝利の外側
コートを出た瞬間。
九条の足取りがふらりと揺れた。
蓮見がすぐに支える。
「おい、大丈夫か……!」
九条は返事をしない。
瞳だけが焦点を結んでおらず、呼吸の深さも一定ではない。
神崎が表情を硬くして駆け寄る。
「間隔が短すぎる。昨日も限界に近かったが、今日はさらに沈んでいる。回復させる時間が足りない」
九条の瞳孔反応を確認しながら、神崎が唇を噛む。
「このペースで続けば、戻らない時間のほうが長くなる。試合に勝っても反応しない。再び深い状態に入るほうが早い体になっている」
早瀬が落ち着いた声で補足する。
「幸い、身体の動作効率が上がっているので脳への負担は少なめではありますが……」
声は淡々としているが、内容は重い。
志水が九条のサポートに回りながら、ストレッチの準備を進める。
誰も、勝利を喜んでいない。
蓮見が低く言った。
「明日が準決勝、勝てば決勝。あと二日。相手が強くなるほど、さらに引き返しづらくなるだろうな」
氷川がデータを見ながらつぶやく。
「九条さん……戻す気がないんでしょうね」
レオンは悲しげに息を吐く。
「昨日も今日も、本人が止める気がない。“あの世界にいたい”んだよ」
九条は言葉を発さない。
反応しない。
ただ立っているだけ。
神崎の声が低く落ちる。
「この状態で、競技を続けさせるのは医師としては反対だ。怪我をする前に棄権させろと言いたい」
蓮見が苦く笑う。
「それやったら、こいつ……二度と戦わなくなるぞ」
その言葉に、誰も反論できなかった。
九条雅臣は、アスリートという枠を超えていた。
ただ勝つためだけに作動する、無機質な戦闘装置のように。
残されたスタッフは、ただ彼を守りきるしかなかった。
大会が終わる、その瞬間まで。
コントロール不能の天才
控室に戻ると、空気が一瞬だけ緩む。
だが誰も安心していない。
志水はすぐに水を渡し、九条の手に押し込むようにして飲ませた。
早瀬はふくらはぎに冷却材を貼り、呼吸の浅さを確認しながらゆっくりと肩をほぐす。
神崎が九条の顔を覗き込む。
「九条。……深呼吸しろ。吸って、吐いて。ゆっくりだ」
九条は反応が遅い。
言われた動作を“機械的にやるだけ”という状態。
蓮見がタオルを持ってきながら小さくぼやいた。
「……ひでぇ顔だな。昨日より戻りが遅い」
氷川はタブレットを確認しつつ言う。
「心拍は落ちてきていますが……意識の“戻り”が弱い」
九条は、まだどこか遠くにいる。
神崎は静かに呼吸して、しかし声ははっきりと落とした。
「このまま試合に出し続けるのは危険だ。フローに入ったまま連日戦う。頭も心も、何も感じないまま動く……これは、いい兆候じゃない」
志水と早瀬が黙って手を止める。
蓮見が腕を組んだまま言う。
「問題は本人が、それを“悪いこと”だと感じてないってことだよな」
氷川が苦笑を漏らす。
「うちにはメンタル専門のスタッフがいませんから」
神崎が肩をすくめる。
「本人が“整えられる”ことを嫌うからな。他人に心の内を触られるのが一番嫌なタイプだ」
蓮見が言う。
「何があっても狼狽えないし、落ち込まないし、傷つかない。メンタルが強過ぎるのも……考えもんだな」
レオンがスプーンを片付けながらぽつり。
「それって強いんじゃなくて……固いだけじゃない?氷の柱と同じで、折れやすいよ」
蓮見が頷く。
「折れたら刺さるしな。周りに」
早瀬も小さくため息。
「冗談にならないですね」
九条はその会話のどれにも反応しない。
ただ、ぼんやりと一点を見つめていた。



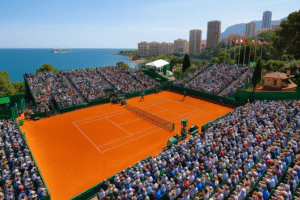

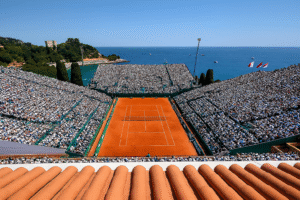

コメント