決断
土曜の朝。
まだ街が動き出す前の時間に、澪は小さな鞄を肩に掛けて外に出た。
生理が終わりかけのタイミングを計って予約したこの日。平日は仕事があるし、痛みが長時間続くなら、休みの日の方が良い。
春には九条と温泉に行く予定がある。
動くなら早い方が良い。
――だから、今日しかない。
産婦人科のドアを潜ると、特有の消毒の匂いが鼻をかすめた。
受付で保険証を渡して、番号札を受け取る。指先に小さな紙の感触を覚えながら、待合室の椅子に腰を下ろした。
隣の席では、小さな赤ちゃんを連れた母親が、赤ちゃんに向かって微笑みかけている。反対側では、妊婦らしき女性が腹を撫でながらスマートフォンを見ていた。
そのどちらでもない自分を意識して、澪は膝の上で手を組む。
――生理の終わりかけ。
予約した時間に合わせて、澪は産婦人科の待合室に座っていた。
「装着は三日目から七日目が望ましいんですよ」
診察のとき、医師がそう説明してくれた。子宮口がわずかに開いているから、器具を入れる痛みもまだ耐えやすいのだという。
七日目。ちょうど今が、その「適した最後の時期」。
澪は待合室で、緊張した様子で手のひらを膝に置いていた。
数分で終わる処置だと聞いている。けれど、その数分の間に自分の体の奥へ異物が入る。その現実を想像するだけで、喉が渇いた。
名前を呼ばれ、ゆっくりと立ち上がる。
――今日、この決断をする。
目的
事前検査は先日、既に受けていた。
それでも、処置直前の検査はある。
問診のあと、いくつもの検査。
妊娠の有無を確認する検査。
超音波で子宮の形や位置を調べると、モニターに白と黒の影が浮かんだ。
子宮頸がんの細胞診、性感染症の検査――淡々と進んでいく項目の一つ一つが、澪の心に小さな重みを落としていく。
問診票に丸をつけるとき、澪は一瞬だけ迷った。
目的は、本当は「避妊」。けれど、それだけじゃない。
毎月の激しい痛みに、鎮痛薬を手放せない日があるのも事実だった。
――月経困難症治療のため。
そう言えば、嘘にはならない。
紙の上に書かれた文字を見つめながら、小さく息を吐く。
自分の選択を正当化するための理由づけ。
でも、それがなければ、この制度の冷たさに押しつぶされそうになる。
白衣の医師が結果を一通り確認し、書類をめくりながら顔を上げた。
「特に大きな問題はありません。今日、挿入できますよ」
安堵と同時に、緊張が胸に広がった。
これで本当に、自分の体の中に“異物”を入れることになる――そう思った瞬間、手のひらにじわりと汗がにじむ。
「装着後は、不正出血や、直後は下腹部の鈍痛が出ることがあります。ただ、多くの場合は出血は数ヵ月で落ち着きます」
「……はい」
澪は小さく頷き、同意書に署名した。
カーテンで仕切られた処置室に移動すると、看護師が優しい声で言った。
「リラックスしてくださいね。大丈夫ですから」
だが、心臓の鼓動は早まるばかりだった。
――これは自分で選んだこと。雅臣さんには言わない。誰にも言わず、ただ自分の中に抱え込む。
不安
「力抜いててくださいね」
医師の声は落ち着いていて、安心させようとしてくれているのがわかる。
けれど、澪の背中は自然に強ばっていた。
冷たい金属が当たる感覚に、思わず喉が鳴る。
お腹の上で、少し握った指先がかすかに震えていた。
――深呼吸。
頭の中で何度も唱えて、肺を大きく膨らませる。
でも、白いライトの眩しさと、器具が触れる感覚が重なり、怖さは簡単には消えてくれない。
「子宮頸がんの検査も一緒にしておきますね」
事務的でありながら、優しさを含んだ声。
ブラシが擦れるような感触が体の奥で広がり、澪は唇を噛んだ。
――痛みというより、不安。
その時間をやり過ごすために、器具がカチャカチャいう音だけに意識を向ける。
ここには誰もいない。
隣で手を握ってくれる人もいない。
だからこそ、この感覚も選択も、全部自分ひとりで受け止めるしかない。
装着を終え、処置室のカーテンを出るときには、下腹部に鈍い痛みがじんわりと広がっていた。歩くたび、身体の奥が重く引っ張られるような感覚が残る。
再び診察室に戻り、椅子に腰を下ろすと、白衣の医師がカルテを確認しながら顔を上げた。
「よく頑張りましたね。今は鈍痛があると思いますが、数日で落ち着いていきます」
「……はい」
医師は少し間を置いて、穏やかに尋ねた。
「ミレーナを入れることは、パートナーの方には伝えていますか?」
澪は短く首を振った。
「いいえ。今日、産婦人科に来ることも伝えていません。遠距離なので……」
医師は強く追及することはせず、ただ小さく頷いた。
「そうですか。これは念のためにお伝えしますね」
声を和らげて、続ける。
「あなたのパートナーがそうという意味ではないんですが――現実として、ミレーナを入れたと知ると、コンドームを使わなくなってしまう方がいるんです」
澪は腹部の痛みを感じながらも、耳を傾けた。
「ミレーナを入れていても、子宮外妊娠や性感染症は防げません。ですから、性交渉の際はコンドームを必ず使ってください」
責める調子はなく、患者を守ろうとする確かな優しさがこもっていた。
――雅臣さんが「じゃあ避妊しなくていい」なんて言うはずがない。
そんな言葉を口にする姿を想像することすら、嫌悪感しかなかった。
もし現実で言われたら――きっと、二度と会わなくなるくらいの衝撃になる。
信じている。
疑ってなんていない。
でも、どれだけ信じていても、このことを話そうという気になれなかった。
――それは彼を疑うからではない。
世の中には、わざとじゃなくても人を傷つけてしまう現実がある。
余裕をなくして、自己中心的になってしまうこともある。
そういう“誰か”と“どこか”の出来事が、対岸の火事みたいに確かに存在している。
悲しいけれど、その現実に触れてしまった以上、もう無邪気にはなれない。
――だから、自分のことは自分で守る。
そう決めただけだった。
――雅臣さんに傷付けられたことなんて、一度もない。
わたしはいつも守られている。
優しい言葉をもらって、手を引かれて、支えられている。
けれど、世の中のすべてがそうじゃない。
悲しいことだけど、それが現実。
遠くで誰かが泣いていても、ただ胸を痛めるだけで、自分には何もできない。
――だから、自分のことだけは自分で守るしかない。
未来
「ミレーナをつけている期間は高い避妊効果が得られますが、体そのものは変化していません」
医師は、カルテから目を上げて柔らかく言った。
「もし、赤ちゃんが欲しいと思う時が来たら、外せば生理は再開しますし、ちゃんと妊娠できますからね」
――未来は閉じられていない。
その言葉に、胸の奥が少しだけ軽くなった。
今はまだ、誰にも言わず、自分の中に抱えておく選択をした。
でも、いつかは欲しいと思う日が来るかもしれない。
その時は、また自分で選び直せばいい。
下腹部に残る鈍い痛みを抱えながら、澪は小さく頷いた。
痛み止めを処方され、処置室の奥にあるベッドでしばらく横にならせてもらった。
カーテンで仕切られた小さな空間。
薄い布越しに聞こえるのは、看護師たちの足音や、どこか遠くの話し声だけ。
下腹部はまだじんわりと重い。
でも、少しずつ呼吸は落ち着いてきた。
一人になった途端、胸の奥に別の考えが浮かんでくる。
――赤ちゃんが欲しい、って。
いつか自分もそう思える日が来るのかな。
今は想像がつかない。
けれど、さっき医師が言ってくれた「外せばまた妊娠できます」という言葉が、ぼんやりと頭に残っている。
未来は閉じていない。
ただ今日は、目の前の痛みと、選んだ決断だけを抱きしめている。
事情
産婦人科という場所――
そこにいる人たちは、皆とても優しい。
受付の声も、看護師の手つきも、医師の言葉も。
それは「お客様」や「患者」といった距離の優しさとは違っていた。
ここに来る人たちは皆、女性で。
それぞれに、妊娠、出産、不安、事情……他人には言えないものを抱えている。
だからこの場所には、外の世界とは種類の違う優しさが流れている。
――その中で、私もまた、自分だけの事情を抱えて横になっている。
会計を済ませて、手渡された領収書を見つめた。
金額は一万一千円。――月経困難症の治療という名目だから、この料金で済んでいる。
けれど、もし「避妊目的です」と言えば、この何倍もの額を払うことになる。
日本は医療費が安くて助かる国のはずなのに、ここはどうしてこんなに差がつくのだろう。
保険適応か否か、することは同じでも、目的でそれが明確に分けられる。
領収書の数字を指でなぞりながら、澪は静かに思った。
――これは彼のためだけじゃない。
自分の人生を守るために、必要な選択なんだ、と。
領収書を財布にしまいながら、澪はふと考えた。
――日本で女性が主体的に選べる避妊方法。
低用量ピル、IUDやミレーナ、アフターピル、不妊手術……。
注射やパッチ、インプラントだって名前はあるけれど、取り扱いは限られているし、自由診療なら費用も跳ね上がる。
「選べます」とリストに並んでいても、実際は簡単に手を伸ばせない。
選択肢はあっても、自由に選べるとは言えない。
結局のところ、日々の負担もリスクも、女性の体と人生に偏っている。
――それが現実。
帰還
横浜のサービスアパートメントに戻ると、外の光がすっかり沈んでいた。
処置の痛みはまだ下腹部に残っていて、薬を飲んでも鈍い重さは消えない。
シャワーを浴びて、ベッドに横になったまま、無意識にスマホを手に取った。
ニュースアプリを開くと、テニスの速報が目に飛び込んできた。
――「九条雅臣、準々決勝で敗退」
指先が止まった。
彼の負けを、こんな風に文字で知るなんて。
遠く離れた場所で、自分は自分の身体を守る選択をしていた。
彼は彼で、コートの上で戦い、そして敗れた。
スマホの画面に表示された文字を見て、澪はしばらく動けなかった。
――敗退。
自分の身体に器具を入れたその日に、彼は遠い地で戦い、そして負けた。
別々の世界を生きているような孤独が、胸に広がる。
それでも、メッセージの入力欄を開く。
指先がためらいながらも、短く打ち込んだ。
試合お疲れさまでした。ゆっくり休んでくださいね。
ほんの一文。
でも、嘘はなかった。
――心から、労いたかった。
送信ボタンを押したあと、澪はスマホを伏せた。
下腹部の鈍痛と、胸の痛みが、同じ重さで静かに広がっていった。
労い
プライベートジェットのベッドで横になっていた九条は、目を閉じても眠れなかった。
頭の奥に、試合の光景が蘇る。
――集中の奥。
球の回転、風の匂い、観客のざわめきすら消えた世界。
そこに突然、幻聴のように響いた。
「……雅臣さん」
澪の声だった。
あり得ないはずなのに、確かに聞こえた気がした。
次の瞬間、現実に引き戻されるように意識が揺れた。
張り詰めていた神経が一気に解け、体に重さがのしかかる。
ほんの一瞬の鈍り。
それが、敗北に直結した。
(澪のせいじゃない)
そう思う。
あれは、自分の内側が呼び戻した声にすぎない。
ただ――あの瞬間が頭から離れない。
ポケットの中でスマホが震えた。
画面を開くと、澪からのメッセージが光っていた。
試合お疲れさまでした。ゆっくり休んでくださいね。
短い一文。
けれど、それを目にした途端、彼女の声がまた耳の奥に蘇った。
――敗けた理由を、誰かに問われても答えはしない。
ただ、自分の中には確かに刻まれている。




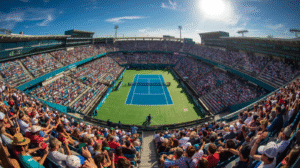

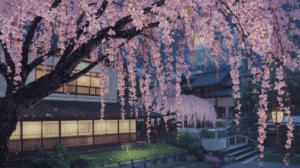


コメント