氷の理性、揺らぐ影
会議室のスクリーンに、ロシア人選手の映像が映し出されていた。
アルチョム・レフチェンコ。
典型的なスラブ系の骨格を持つ男だ。
顎はしっかりと張り、フェイスラインは角ばっている。
頬骨がやや高く、額は広い。鼻筋が通っており、寒冷地生まれらしい白い肌には血管の青がうっすらと透けていた。
瞳は灰色がかったブルー。光の加減で、青銀にも見える。
長い睫毛と、伏せ気味の視線が生む冷たい静けさ。
髪はアッシュブロンド寄りのダークブラウンで、癖が少ない。
試合中は短く整え、オフでは無造作に前髪を落とすタイプだ。
身長は185cm前後。
筋肉は無駄がなく、いわゆる“マッチョ”ではない。
氷の上を滑るような軽いフットワークをする選手で、筋量よりもバランスと柔軟性を重視している。
「次の相手、アルチョム・レフチェンコだ」
蓮見がリモコンを操作し、映像を一時停止させた。
「前年はいなかったな」
九条が低く呟く。
彼は他人の私生活に関心を持たないが、試合の出場履歴だけは正確に記憶している。
初対戦ではないが、昨シーズンこの名前を見ていなかったことを覚えていた。
氷川がタブレットを見ながら補足する。
「メンタルの問題で、ツアーを離脱していました。重度の鬱を患っていたようです。薬の服用もあったと」
九条は反応を示さなかった。
勝負の世界では、精神を壊す危険は誰にでもある。
それを理解していても――同情する余地はない。
「今はピークの時の動きができているのか」
それが彼にとって唯一の関心だった。
「そこが興味深いところでね」
蓮見が映像を切り替える。
「これが、離脱前のアルチョムだ」
映像の中で、彼は激情を露わにしていた。
ラケットを叩きつけ、審判に食ってかかり、ペナルティを受ける。
とにかく攻撃的で、感情が爆発するタイプ。
蓮見がもう一度スイッチを押す。
「で、これが最近の映像」
画面には、別人のように穏やかなアルチョムが映っていた。
音を立てず、無駄を削いだフォーム。
以前のアグレッシブさは残っているが、怒りは消えていた。
嵐を抜けたあとに訪れる、静かな湖面のようなプレー。
「離脱の影響は多少残ってるが、以前よりも思考が読めない。
感情を見せない分、手がかりがない」
試合後、相手に微笑みながら「ありがとう」とロシア語で告げる映像が流れる。
氷川が続けた。
「オフコートの話には九条さんは興味ないと思いますが……
子どもたちのためにプレーを続けることにしたらしいです。
現地では『チョマ』という愛称で呼ばれていて、子どもたちには人気ですよ」
氷川の声が途切れると同時に、九条は手元のiPadに視線を落とした。
スクリーンに映るアルチョムの映像を、無言のまま数秒見つめる。
指先で軽く画面をタップ。
冷静な声が室内に響いた。
「最近の試合の映像をAirDropで送れ。確認しておく」
「やっぱ興味ねーか。試合外の情報には」
蓮見が苦笑する。
九条は目線を上げずに、淡々と答えた。
「事情には理解を示すが、ここは勝負の世界だ。
勝ち負けで全てが決まる。
弱いとは思わないが、この世界で生きるには――“穏やか”は適性じゃない」
一瞬の静寂。
誰も反論しなかった。
その言葉があまりにも、この部屋の空気と合致していたからだ。
蓮見は、何かを言いかけて口を閉じる。
氷川は手元のタブレットを静かに操作し、ファイル送信を完了させた。
スクリーンの中で、アルチョムが最後の握手をしている。
柔らかな笑顔。
九条の無表情とは、対照的だった。
「選手の精神疾患の問題は、我々にとっても他人事じゃない。
誰にでも起こりうることだ。心と体は繋がっている。
相手に同情する必要はないが、弱いからそうなるわけでもない。
俺達も――少しの不調に目を瞑らずに過ごすようにしよう。
特に九条。お前は自分の不調に鈍感すぎる。
“ある日突然”というのは、誰にも起こりうる。頭に置いておけ」
医師としての忠告。
九条はしばらく黙っていた。
わずかに息を吸い、淡々と答える。
「絶対に壊れないという保証は無いが、俺は――アイツほど感情の波がある人間じゃない」
「波がないことが、必ずしも安定とは限らない」
神崎の言葉に、九条は反応を示さなかった。
スクリーンの中では、アルチョムが笑顔で子どもとハイタッチをしていた。
九条はその映像を見たまま、声を落とす。
「……感情の波は、試合の邪魔になるだけだ」
そう言い切った口調には、理性しかなかった。
だがその理性の下に、かすかに触れられたことのない“痛点”のような沈黙があった。
「明日の戦い方について、他に注意事項がなければ――これで解散とする」
誰も言葉を挟まなかった。
椅子の擦れる音だけが、冷たい空気の中に響く。
スクリーンの中では、まだアルチョムが笑っている。
その穏やかさが、九条の視界の隅で淡く揺れていた。
氷の残響
会議室の機材の電源が落とされ、扉の閉まる音が響いた。
チームメンバーはそれぞれ自室へ戻り、部屋には九条ひとりが残った。
テーブルの上に置かれたMacBookを開く。
静寂の中、画面の明かりだけが彼の顔を照らす。
再生ボタンを押すと、アルチョム・レフチェンコ――
通称“チョマ”の試合映像が映し出された。
淡々とボールを打ち返す姿。
無表情のまま、リズムを刻むようにラリーを続けている。
ラケットワークは滑らかで、無駄がない。
一球ごとに力を抜き、次の一手に移る。
理にかなった動きだ。だが――熱がない。
九条は、頬杖をついて映像を見つめた。
鬱を患っていたという情報は、試合には必要ない。
必要なのは、チョマの“戦い方”だけ。
(……あの柔らかさが、どこまで続く)
心の中でそう呟き、再生速度を倍速に変える。
相手の反応、足の運び、ボールの回転――
すべてを分析しながら、目の奥で静かに数字が組み上がっていく。
“チョマ”という名前。
確かに「アルチョム」よりは呼びやすい。
だが、気の抜けた響きだ。
戦う相手として呼ぶには、どうにも締まりがない。
(……だが、蓮見も氷川もそう呼んでいたな)
結局、チーム内ではこのまま定着するだろう。
そう思いながら、九条は再び再生ボタンを押した。
モニターの中のチョマが、ラリーの中で笑っていた。
その笑みを、九条は無表情のまま見つめ続けた。
試合映像を見ていると、確かに以前のように怒りに任せて爆発するような戦い方は影を潜めていた。
ラケットの振り方ひとつ、ショットの選び方ひとつに、力の抜き方が見える。
感情が爆発しないように――いや、もはや爆発させるだけのエネルギーが残っていないのかもしれない。
一度、精神を病んだ人間にとって、かつての「怒りの燃料」は刃のようなものだ。
使えば勝てるが、同時に自分をも削る。
心も体も、その重さに耐えられなくなっている。
だから、彼は自然と“省エネの戦い方”を選んだのだろう。
体力は使うが、精神に過度な負担をかけないように――
淡々と、無理をせず、必要なところだけで力を出す。
それが、今の彼の“穏やかな風”のようなプレーを作っている。
(恐らく、明日の試合もこのスタンスで来る)
もとのポテンシャルは高い。
この戦い方が完全に噛み合えば、以前よりも強くなる可能性すらある。
今は、その“途中”――嵐のあとに訪れる、静かな再生の過程。
九条は無言のまま再生を止め、画面に映るアルチョムの顔をじっと見つめた。
その穏やかさが、何かを思い出させるようで――
彼は小さく息を吐き、MacBookを閉じた。
無風の朝
試合当日の朝。
目が覚めた瞬間、身体が自動的に動いた。
ベッドから起き上がり、ストレッチマットの上に立つ。
呼吸を整え、背筋を伸ばす。
関節の可動域を確認するように、一つひとつ丁寧に動かしていく。
不思議なことに――
昨夜、見たチョマの映像が、まだ脳裏に残っていた。
強敵だと感じているわけではない。
予定外の動きをしなければ、勝てる。
コンディションも悪くない。
心は静かだ。
というより、何も感じない。
プレッシャーも、恐怖も、興奮も。
どれも、試合に必要な燃料ではない。
チーム九条には、メンタルコーチはいない。
他人の言葉で精神を整えることを望まない。
自分の面倒は、自分で見る。
メンタルトレーニングも、瞑想も、ジャーナリングも日課の一部。
それを“特別な対策”とは思っていない。
負けた時、慰めの言葉など求めない。
根本を変えずに表面を撫でるだけの言葉に、意味はない。
それでも――
チームの誰もが「九条にも病む日が来る」とリスクとして捉えている。
そこに対して、何も思わない。
仮にそうなったとしても、戦えるのなら関係ない。
戦えなくなる日が来た時に、初めて考えればいい。
今はただ、呼吸を整える。
今日も同じように、淡々と勝つための準備をするだけだ。
氷と風の前奏
試合開始前。
ロッカールームの空気は、いつもより湿っていた。
エアコンの低い唸りと、テーピングの音だけが響く。
九条はラケットバッグを肩にかけ、出入口へ向かう。
その途中、すれ違うように“チョマ”――アルチョム・レフチェンコが入ってきた。
彼はタオルで髪を拭きながら、軽く笑みを浮かべる。
灰色がかった青い瞳が、まっすぐこちらを見た。
「今日はよろしく。いい試合をしよう」
その声は穏やかで、少しだけ柔らかかった。
戦いの前とは思えないほど、静かなトーン。
九条は一瞬、視線を返す。
だが、感情のない目だった。
「試合に“良い”も“悪い”もない。
勝つか負けるか、それだけだ。
自分のコンディションとプレーのことだけを考えろ。」
短く、冷たく言い放つ。
チョマはほんの一拍の間、言葉を止めたが――
すぐに微笑んで、小さく頷いた。
「……そうだね。」
そのまま、すれ違う。
九条は振り返らない。
ただ、無言のまま出口のドアを押し開けた。
その背中に、チョマの声が微かに届く。
「……それでも、俺は“いい試合”をしたいよ。」
九条は立ち止まらず、そのまま歩き続けた。
まるで、その言葉ごと、音ごと、氷の中に封じ込めるように。
「お前、今の……ちょっとそっけなくないか?」
九条はタオルを肩にかけたまま、無表情のまま答えない。
「向こうから歩み寄ってきたのに、可哀想じゃねえか。」
ようやく、九条が口を開く。
「これから戦う相手と仲良くしてどうする。倒しづらくなるだけだ。
どこまで行っても結局、自分と向き合うしかない。」
淡々とした声だった。
説明でも弁解でもなく、ただ“事実”を述べるように。
蓮見は短く息を吐いて、わずかに肩をすくめた。
「……そういうとこ、お前らしいけどな。」
九条は返事をしない。
ただ静かに立ち上がり、コートへ向かう廊下を進んだ。
氷と風、開戦
コート入場。
九条は、いつも通りだった。
感情の欠片もない表情。
何も感じず、極力考えない。
観客の声、アナウンス、シャッター音――すべての“音”を遮断していく。
外界を閉ざし、内側に潜る。
意識を極限まで狭め、集中の極地へと至る。
そこにあるのは、勝つための思考だけ。
一方で、チョマ――アルチョム・レフチェンコは違った。
マイアミの熱気の中でも、その姿はどこか涼しげだった。
眩しい陽射しに細めた灰青の瞳。
観客席に軽く手を振る仕草さえ、穏やかで柔らかい。
どこまで鬱の症状から回復しているのか、九条には分からない。
重度の鬱を患った後、人は完全に“元”に戻ることは難しい。
だが、それでも――
この灼熱のコートに、自らの足で立ったのなら。
そこに、情けも遠慮も必要ない。
コイントスのあと、審判の声が響く。
「Play!」
乾いた音がマイアミの空気を裂く。
最初のサーブは、チョマ。
ボールを弾ませ、静かに呼吸を整える。
トスを上げる動きに、無駄がない。
――パシン!
強烈な打球音。
思った以上に速い。
だが、かつてのような“爆発”ではない。
以前の彼が火山なら、今は風だ。
荒々しさを削ぎ落とし、
必要な力だけを残している。
無駄のないフォーム、正確な軌道。
力ではなく、精度で打ち抜く。
そのサーブに、九条は無言でリターンの構えを取った。
(……変わったな。)
心の中で、淡々と評価する。
選手の経験も性格も――
人間そのものが、プレーに現れる。
一年間――
チョマがツアーから離れていた時間は、彼の体に確実な“空白”を残していた。
恐らく、その間はロクにトレーニングもできなかったのだろう。
筋肉の張り、反応速度、そして持久力。
どれも、ピークの頃よりわずかに鈍っている。
元のポテンシャルが高くても、日々の鍛錬を欠かさず続けてきた者との差は、確実に現れる。
まして――
彼の相手は、ランキング上位を維持し続けている九条雅臣だ。
若い頃から大きな故障もなく、常に自己管理を怠らない。
走り続け、積み上げてきた“積層の時間”がある。
戦力差は、歴然だった。
だが――
チョマの顔には焦りがなかった。
恥じる様子も、苛立ちもない。
ただ、プレーを“楽しんで”いる。
打ち合う相手に感謝し、
見守る観客に誇れる自分でいようとする姿勢。
彼のテニスは、勝ち負けではなく、
「誰かにこの世界を好きになってもらうためのもの」だった。
その無垢さに、九条は無言で眉をわずかに寄せる。
(……戦う理由が、違う。)
心の奥でそう思った。
九条の戦い方は、冷徹そのものだった。
実力差がある相手に対しても、一切の手加減はない。
むしろ、徹底的に弱点を突く。
追いつけない位置、届かない高さ――
相手の“限界”を正確に測り、そこへ淡々と打ち込む。
まるで、感情を失った精密機械のように。
打球の軌道も、タイミングも、呼吸までもが計算の上に成り立っている。
チョマが抱えていた“事情”を知っていても、
九条は一切の情を交えない。
勝つために、相手のハンディを利用する。
同情はしない。
誰かから非難されようと、関係ない。
――勝利以外に価値はない。
それが、九条雅臣という男の哲学だった。
氷の亀裂
表情は変わらず、息も乱れない。
淡々と、静かに、確実に。
スコアボードの数字だけが、冷たく動いていく。
だが、対面するチョマの顔からは――
穏やかな笑みが、消えなかった。
敗勢でも、苦しくても、笑っていた。
まるで、自分が立てることそのものを喜んでいるように。
心は、沈まない。
風のように吹き抜けて、どこまでも軽やかだった。
3セット。
ストレート負けしても、チョマの表情は変わらなかった。
むしろ、戦えたことを――
清々しいとさえ思っているようだった。
ネットを挟んで握手を交わす。
チョマは笑って言う。
「ありがとう。やっぱり君は強いね。良いプレーだった」
(……なぜ、笑える。)
勝ったことを誇りには思わない。
だが、負けて笑える理由がわからない。
自分を倒した相手を讃える――
そんなことをして、何になる。
それでは、また心が擦り切れるだけじゃないのか。
問いが、無意識に口からこぼれた。
「なぜ、笑っていられる」
チョマは一瞬だけ躊躇うようにまばたきをして、
それでも穏やかな表情を崩さなかった。
「君には、もしかしたら想像も及ばない世界かもしれないけど……
今の僕には、打ち合えるだけで幸せなことなんだ。
去年は、生きるだけで精一杯だった。
でも君は、他の選手と同じように戦ってくれた。
腫れ物扱いせずに、真正面からぶつかってくれた。
それが――嬉しかったんだ。
ありがとう。また、どこかで戦おう」
手を離し、背を向けて歩き出すチョマ。
九条はその背中を、無言で見送った。
歓声も、カメラのシャッター音も、遠い。
熱気の中で、ひとりだけ温度の違う場所に立っていた。
胸の奥に、わずかに残った“何か”。
それが何かは、まだ言葉にならない。
ただ――
「理解できない」という感情の形をして、
確かに、そこにあった。
ありがとうの残り火
試合終了後のインタビュー。
ライトの熱がまだ残る会見ブースに、九条が姿を見せる。
「レフチェンコ選手と、何か話されましたか?」
マイクを向けられても、彼はすぐには答えなかった。
一拍置いてから、短く言う。
「いや……『また戦おう』と言っただけだ。」
淡々とした声。
それ以上の言葉はない。
記者たちは、何か続きを引き出そうと視線を交わす。
だが、九条は目を逸らすこともなく、ただ黙っていた。
ほんの少しだけ――
自分の耳に、チョマの「ありがとう」という声が、
まだ残っている気がした。
けれど、それを口にする理由はどこにもない。
「握手の後、しばらくコートに残っていましたが、何か言葉を交わしたのでは?」
「だとしても、試合の内容には関係ない。
試合は俺が勝った。それ以外に意味はない。」
その声音には、感情の波ひとつない。
冷たくも、揺らぎのない答え。
記者席が一瞬だけ静まる。
フラッシュがまた焚かれ、光が彼の頬を白く照らした。
九条は軽く息を吸い、マイクから視線を外す。
「――次の試合に集中したい。それだけだ。」
言い残して、立ち上がる。
背を向けた瞬間、
遠くの喧騒の向こうに、
まだ“ありがとう”の声が、微かに響いている気がした。
短いインタビューを終えて、会場から出た廊下で蓮見に声をかけられる。
「いつにも増してぶった斬ったな」
「質問に答えただけまだマシだろう」
「まあ、お前にしてはな」
蓮見は「仕方ねえな」という様子で苦笑いする。
照明の落ちた通路に、二人の足音だけが響く。
「お前が人を庇うような事をやったのが、俺は成長を感じたよ」
九条は足を止めず、視線も向けないまま返す。
「俺は誰も庇ってない。勘違いだ」
「そうか」
短いやりとりのあと、再び沈黙が落ちた。
外の空気が流れ込む出入り口の方から、
遠くの歓声がまだ微かに聞こえている。
蓮見はそれを背に受けながら、
「ま、そういうことにしとくか」と小さく呟いた。
九条は何も返さなかった。
だがその横顔には、わずかに熱を帯びた影が差していた。
音のないおやすみ
食事を済ませ、シャワーとストレッチを終え、寝る前のルーティンをこなしているときだった。
AirPodsに、短い通知音。
「綾瀬澪さんからメッセージが届いています。
『3回戦勝利おめでとう🎉ゆっくり休んでね』」
無機質な読み上げ音声が途切れ、室内に静寂が戻る。
Apple Watchの画面を見れば、時刻は20時過ぎ。
日本は朝の時間帯。出勤前に送ってきたのだろう。
(平日だ。リアルタイムで観てはいないはずだ)
そう思いたい。
試合を観ていたなどと想像したくはなかった。
右手のApple Watchで音声入力する。
「ちゃんと寝たか?」
送信の確認音が鳴る。
短いメッセージが、夜の静けさに溶けていく。
我ながら、まるで保護者のようだと思う。
こいつは何度言い聞かせても聞かない。
いや――聞かない時は、何を言っても聞かない。
それでも、言わずに放っておくことはできなかった。
続いて、AirPodsに音声で反応があった。
「綾瀬澪さんからメッセージが届いています。
『ちゃんと寝ましたー。結果だけ朝知りました。帰ってから試合観るね』」
見なくていい。
テニスの試合は長い。
自分の場合は比較的早く決着がつく方だが、長い時は5時間を超える。
働きながら全試合を追う気でいるなら、どこかで疲れが溜まって倒れる。
だが、言えば傷付くか、言っても黙って試合を見ている。――澪は、そういう人間だ。
澪が俺の試合を見ないようにする方法は、残念ながら無い。
好きにさせるしかない。
それでも、
自分の体を優先してほしいと思う気持ちは、消えない。
見ていてほしくない――と言いながら、
見られていることが不快ではない、という内心もある。
だが、“見ていてほしい”とは、言えない。
言うわけにはいかない。
九条は、AirPodsを外し、静かに机の上に置いた。
Messageの音声入力の画面を開き、
Apple Watchに向かって、短く呟く。
「おやすみ」
それだけを送信した。
画面が暗転し、送信音だけが静かに響く。
眠る時も、Apple Watchは外せない。
睡眠のデータはチームで共有されており、コンディション管理の一環として記録が義務づけられている。
プライベートな時間すら、どこかで常に“記録”されている感覚。
それでも――
誰か一人にだけは、“おやすみ”を言葉で伝えたかった。




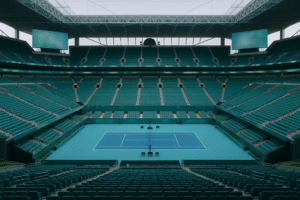

コメント