影に慣れた者
午後の風は湿っていて、どこか重たかった。
九条は、淡々とサーブを繰り返していた。
乾いた打球音だけが、静かな空気を切り裂いていく。
観客も報道もいない。ただの練習。
それでも、その静けさの奥には、張り詰めた集中があった。
遠くから笑い声が近づいてくる。
陽の温度をそのまま運んでくるような声だった。
「よう、九条! 明日よろしくな!」
声が届いた瞬間、ラケットの動きが一瞬止まる。
九条は振り向かない。
指先でボールを転がしながら、短く返す。
「……ああ。」
ネットの向こうで、ガブリエル・モレーノが手を振っていた。
相変わらず長身で、広い肩幅。
年齢を重ねてもなお、動きに一切の鈍さがない。
太陽をそのまま浴びているような、伸びやかな笑顔。
(どうして、コートで戦う相手に、あんな陽気に声をかけられるんだ)
理解はできない。だが、嫌悪もない。
むしろ——少しだけ、羨ましい。
「俺、明日は“楽しく負ける”つもりで来たからな!」
ガブリエルの軽口に、九条はわずかに眉を動かす。
「……そういう冗談は、嫌いじゃない。」
「ははっ、珍しく会話したな!」
周囲のスタッフが笑う。
九条は無言のまま、タオルで汗を拭う。
その動作の裏で、胸の奥に古い記憶が滲んだ。
──まだ若かった頃。
あのガブリエルに感情的になって負けた。
ラケットを握り潰すほどの悔しさを、今でも覚えている。
あの試合が、“感情を表に出した最後”になった。
それ以降は、感情を殺すことで勝ち続けてきた。
だが今、目の前で笑っているその男は、年を重ねてもなお、“感情を武器にできる人間”だった。
九条は視線を上げる。
陽光を背に立つガブリエルの姿を、黙って見つめた。
(昔の俺は、あの陽の光に焼かれていた。だが、今はもう——影に慣れている。)
静かにボールを拾い上げる。
ガブリエルは去り際に、軽く拳を掲げた。
「じゃ、明日な。俺の笑顔、見逃すなよ!」
「……お前の方こそ、止まるな。」
笑い声が風に溶けていく。
九条は再び構えに戻った。
ラケットを握る指先に、わずかに力がこもる。
かつての敗北は、もう過去だ。
あの頃の自分も、もういない。
そして明日——それを証明する。
美しき魅せの伝道師
夜のマイアミ。
湿気を含んだ風がガラスに触れ、低い音を立てていた。
ホテルのミーティングルームには、ランプの柔らかな明かりと、タブレットの画面が照らす白い光だけがある。
机の上にはコートマップ、データ表、そして沈黙。
その沈黙を破ったのは、蓮見だった。
「次はガブリエル・モレーノ。……まあ、何度も当たってる相手だ」
九条は黙ったまま、画面を見つめている。
光の反射で、表情が半分だけ暗闇に沈んでいる。
氷川が端末を操作しながら続けた。
「戦績は五勝二敗。去年以降は九条さんが連勝中です」
「……」
九条の瞳が、数値を追ってわずかに動く。
冷静というより、淡々。感情の揺れは一切ない。
志水が腕を組みながら補足する。
「ただ、年齢のわりに動きはまだ衰えてません。膝の故障から復帰してるけど、柔軟性は健在です」
蓮見が椅子を傾け、腕を組み直す。
「愚問だけど、油断はできねぇ。身体能力も経験もある。調子次第で化けるタイプだ」
その声に、わずかに冷房の音が混じる。
チーム全員が、すでに“勝つ”ことを前提にしている。
それでも、誰も楽観はしていなかった。
蓮見がタブレットを指先で操作し、壁のプロジェクターに映像が浮かび上がった。
ガブリエル・モレーノの姿が、マイアミの光の下で跳ねる。
汗の粒が飛び、笑い声が音声と共に響く。
画面の中でも、彼は楽しそうだった。
「ガブリエルの強みと弱点、癖について——最近変わった点はあるか?」
蓮見の問いに、氷川が視線を上げる。
モニター越しの光が眼鏡のレンズに反射した。
「大きく変化したところはありません。ただ、元々の身体能力が非常に高く、メンタルも強い。
年齢を重ねた分、経験が増して、動きに“迷い”がなくなっています」
九条は椅子に深く腰を下ろしたまま、黙って映像を見ていた。
コートを駆けるガブリエル。
笑いながら、あり得ない体勢からボールを拾い上げる。
観客がどっと湧く。
その瞬間、九条の目がわずかに細くなった。
蓮見が横目で彼をうかがう。
「……映像を見てどう思う?」
九条の声が静かに響いた。
会議室の空気が、わずかに引き締まる。
「身体能力の高さゆえか、元来の性格か——」
九条は、スクリーンに映るガブリエルの動きをじっと見つめたまま続けた。
「地味で確実なプレーを取りにくい。華美な攻めを優先して取る傾向にある。それが却って、隙を生んでいる。」
氷川が頷く。
「それは、過去のインタビューでも本人が自覚していると言っています。
“観客を楽しませたい、それが自分のモチベーション”と。」
九条の視線は動かない。
ラリー映像の中で、ガブリエルがジャンピングスライスを放ち、観客が沸いた。
九条は淡々と口を開く。
「考え方の癖か、華やかな魅せるプレーをした時の観客の“湧き”に、成功体験を得たか——可能性の話でしかないが、行動選択の癖はなかなか抜けない。まして、咄嗟の判断を求められる試合中なら尚更だ。」
ペンを手にしていた蓮見が、無言で頷く。
「つまり、“美しい勝ち方”を選びやすいってことか。」
九条は短く、「そうだ」とだけ答える。
その瞬間、プロジェクターの映像に、過去の対戦シーンが映り込む。
若い九条が打ち込んだボールを、ガブリエルが無理な体勢から拾い上げ、笑顔のままポイントを奪う。
観客が歓声を上げる。
あの頃の自分の表情を見て、九条は無言のまま目を細めた。
(あの時も、彼は笑っていた。
……そして、俺はそれを許せなかった。)
映像の光が、静かな部屋の壁を照らす。
外ではマイアミの風が鳴っている。
チームの誰もが黙り込んだまま、スクリーンに浮かぶ“陽”の男を見つめていた。
コート上の支配者
氷川がタブレットをスクロールしながら、穏やかな声で言った。
「過去のインタビュー映像で、“支配的攻撃型になりきれない”と本人が語っています」
その言葉に、蓮見が小さく鼻を鳴らす。
「……お前の得意技だな」
冗談めいた響きだったが、部屋に笑いは起きなかった。
誰もがわかっている。
その“支配”という言葉が、九条という男の代名詞だからだ。
九条は視線をスクリーンから外さずに答える。
低く、乾いた声。
「元々できていたわけじゃない。身に付けたものだ。」
淡々としたその言葉に、蓮見が少しだけ目を細める。
九条は続けた。
「だが俺は、観客が喜ぶかどうかは関係ない。自分のためにプレーを選択している。」
短い沈黙。
スクリーンの中では、ガブリエルが笑いながらボールを拾い上げていた。
同じコートの上に立ちながら、まるで別の生き方をしているようだった。
蓮見が肩を組み直し、ぼそりと呟く。
「……まったく、真逆だな。あいつは“世界を笑わせる”ために打つ。お前は“世界を黙らせる”ために打つ。」
九条は何も言わなかった。
ただ、画面に映るガブリエルの笑顔を見つめていた。
どこかで風が鳴り、窓ガラスが微かに揺れる。
マイアミの夜の熱気が、静かな会議室の空気をゆっくりと包み込んでいる。
九条が低い声で言った。
「世界が静かな方が、俺は戦いやすい。世界を喜ばせるためにやっていることでもない。」
蓮見が深く椅子にもたれ、苦笑まじりに息をつく。
「そうだけどよ……おかげでメディアに嫌われ放題のサンドバッグよ。」
九条は眉ひとつ動かさず、淡々と返す。
「暇人がやってることだ。他人の人生に興味を持つ時間があるなら、自分の人生に使え。」
その冷たすぎる正論に、蓮見が額を押さえる。
「お前それ、インタビューで言うなよ……氷川の胃に穴が開く。」
端の席でデータをまとめていた氷川が、無表情のまま眼鏡を押し上げる。
「……既に何度か開いてます。」
部屋に小さな笑いが起きる。
それは緊張を和らげるものではなく、長年このチームで生きてきた者たちにしかわからない、“慣れ”に近い笑いだった。
蓮見がため息をひとつ落とす。
「ほんと、いつかお前が“笑顔で話す”日が来るのかね。」
九条は視線を上げずに言う。
「試合で笑う気はない。」
「だろうな。」
氷川がデータを閉じる音だけが響いた。
外では、マイアミの湿った風がまた窓を叩いていた。
怒りの所在
蓮見がタブレットを操作し、画面をスクリーンに送った。
白い光が会議室を照らし、SNSの投稿が映し出される。
「でもよ、こんな温厚なガブリエルでも——怒る出来事があるみたいだぞ。」
九条が無言のまま、画面を見つめる。
映し出されたのは、ガブリエル・モレーノの公式アカウント。
そこには、普段の彼からは想像できないほど、感情のこもった言葉が並んでいた。
『僕への批判なら受け入れる。でも、家族を傷つける言葉は絶対に許さない。
僕の肌の色も、妻の名前も、子どもの笑顔も——何ひとつ、君たちの侮辱のために存在していない。』
その文面の下には、数百万件の“いいね”と、
「Respect」「Stay strong」といったコメントが流れていた。
蓮見が腕を組む。
「前々から、差別的なことを言われても怒らなかったんだとさ。
相手を説得するような言葉で返してた。……けど、家族に向けられた時だけは違った。」
志水が画面を見つめながら、低く呟く。
「“憎しみを憎しみで返さない”って言っていた人が、それでも怒る時があるということですね。」
九条は沈黙を保ったまま、ガブリエルの文面の一点を、じっと見つめていた。
『僕は父親だ。父親は、守るために戦う。』
その一文の前で、九条の指先がわずかに止まる。
彼の中で、何かが小さく軋むように動いた。
蓮見が肘をつきながら、ぼそりと呟いた。
「……お前はその点、差別を受けても怒らねーよな。
練習コートを後回しにされたり、遠征先で雑な扱いされたり……昔は色々あったけどな。」
九条は答えず、ただスクリーンに映るガブリエルの投稿を見ていた。
光に照らされたその横顔は、いつもよりも影が濃い。
しばらくの沈黙のあと、九条は低く、しかしはっきりと言った。
「世界は、所詮変わらない。」
その声に、誰も口を挟まない。
九条の目は、まだ画面の中の文字を追っている。
「言葉を尽くすのは——伝えれば変わると信じているからだ。俺は、試合で勝って黙らせるだけだ。」
蓮見が小さく息を吐く。
「……冷めてるなぁ、うちの王様は」
氷川が、手元の資料を閉じる音が響いた。
会議室の照明が、わずかにガラスに反射して揺れる。
外では遠く、マイアミの夜風が低く鳴っていた。
その静けさの中で、“言葉で戦う者”と、“勝利で戦う者”の対比が、淡く同じ画面の上に重なっていた。
言葉を信じない者
蓮見が腕を組み、静かに問うた。
「……言葉で人を説得するのは、無意味だと思うか?」
九条はすぐには答えなかった。
プロジェクターの光が彼の頬をかすめる。
そのまま数秒、視線を落とし、わずかに息を吸う。
「全くの無意味だとは思わない。」
低く落ち着いた声。
だがその奥には、冷たい観察者の温度があった。
「ただ——人が他人の言葉を聞き入れる時は、優しさからではない。より強い者から言われた、もしくは、聞き入れないと自分に害がある時だ。」
氷川が、目を細めたまま静かに聞いている。
「自分より立場が弱い者。聞き入れなくても害はない者。むしろ、聞き入れる方が不利になる相手。
——そういう存在の言葉は、誰も聞かない。人間は、そういう生き物だ。」
九条の声が止むと、部屋の中にエアコンの低い音だけが残った。
外の風が窓を揺らし、わずかに反射した光が彼の横顔を掠める。
蓮見はしばらく黙って九条を見つめていたが、
やがて小さく笑って言った。
「……お前らしい答えだな。」
九条は椅子に深く腰をかけたまま、低く言葉を継いだ。
「だが、俺たちは——言葉を交わすのではなく、プレーで勝負する世界にいる。
勝って、より強い存在になれば、言葉で説得する必要もなくなる。」
その声音には、感情の揺れがない。
ただ、積み上げてきた現実の重みだけがある。
蓮見が天井を仰いで、やれやれとため息をついた。
「……世界がそう単純だといいな。」
九条は視線を上げずに答える。
「世界が複雑だろうと単純だろうと、俺たちが目指す場所は一つだ。」
短い沈黙ののち、蓮見が頷く。
「そうだな。試合に勝って、大会で優勝する。それだけのために、俺たちは戦ってる。」
その言葉に、志水が小さく頷き、氷川が淡々と資料を整える。
誰もが、自分の領域で果たすべき役割を理解していた。
コーチ、トレーナー、マネージャー——そして選手。
それぞれの立場も、思考の癖も違う。
だが、目指す先はひとつだけ。
マイアミの夜の湿気が、窓の外でゆっくりと音を立てる。
その音の中に、誰も言葉を足さなかった。
もう話すことは尽きていた。
あとは——コートで証明するだけだった。
言葉の続きはコートで
通路の照明が落ちる。
湿気を帯びたマイアミの熱気が、狭い空間に溜まっていた。
九条はヘッドバンドを結び直し、ラケットバッグのベルトを肩にかける。
足音が響くたびに、壁の鉄骨がわずかに鳴った。
スタッフの声が低く告げる。
「Thirty seconds to walk-on.」
その言葉と同時に、通路の奥から光が差し込んだ。
観客席のざわめきが波のように押し寄せてくる。
遠くで聞こえるアナウンスが、名前を読み上げた。
──“From Japan, Masaomi Kujoh.”
一瞬、世界が白く弾けた。
スポットライトの光が視界を焼く。
観客の歓声が割れるように響き、
九条の名を呼ぶ声と、ブーイングが混ざり合う。
その全てが、彼にとってはノイズでしかなかった。
ただの“音”。
世界の雑音。
九条は視線を前に固定したまま、コートへと歩き出す。
足裏に伝わる振動。
呼吸のリズムを乱さず、無言でラインを超える。
そして次の瞬間、
アナウンスがもう一人の名を告げた。
──“And from France… Gabriel Moreno!”
歓声がさらに膨れ上がった。
まるで空気が揺れるような熱狂。
観客が一斉に立ち上がり、光がステージを満たす。
ガブリエルが通路の奥から現れた。
白いウェア、黒いリストバンド、そしていつもの——あの笑顔。
彼は片手を軽く上げ、観客席を指差す。
「マイアミ、今夜は踊ろうぜ!」
スタンドが揺れた。
笑い声、歓声、拍手。
まるで彼自身が、空気を動かしているようだった。
九条はそのすべてを、ただ見ていた。
無表情のまま、コート中央へ。
ガブリエルが歩み寄り、手を差し出す。
「準備はいいか、王様?」
九条はその手を一瞥し、短く答える。
「……試合で聞け。」
ガブリエルが笑う。
「それでこそ君だ。」
両者の影がセンターサークルに交わった瞬間、歓声が再び爆ぜる。
マイアミの夜が、戦いの音に変わる。
開幕の一撃
サーブの音がマイアミの夜に響く。
230km/h近いスピードボールが、硬質な音を立ててネットをかすめた。
観客席が一斉に息を呑む。
それが、ガブリエル・モレーノの“開幕の合図”だった。
九条はリターンポジションで一歩も動かない。
目の奥で、回転の軌跡だけを読む。
次の瞬間、打球が跳ね上がる。
通常なら取れない角度。
だが、ガブリエルは笑っていた。
滑り込みながらのジャンピング・フォア。
重力を無視するような姿勢で、クロスへ叩き込む。
ネットすれすれの球筋が、コートを切り裂く。
観客席が爆発した。
歓声、拍手、笑い声。
あらゆる音がひとつになって、夜の空に響く。
九条は動じない。
タオルを取るでもなく、ただ立ったまま静かに目を閉じた。
観客の音を遠ざけるように。
(守備から攻撃への切り替えが速い……。ただし、次は同じ角度を使えないはずだ。)
次のポイント。
ガブリエルのドロップショットが前に落ちる。
九条は反応しない——わざとだ。
一瞬の沈黙の後、観客のどよめきが広がる。
(誘っている。)
九条の頭の中に、映像が走る。
過去のデータ、ボールの回転、足の向き、呼吸のリズム。
すべてがパターン化されている。
(笑っていろ。)
九条は心の中で呟く。
(その笑顔の裏を、突く。)
次のリターン。
ガブリエルがフォアに回り込む瞬間、九条はわずかに前へ出た。
強烈なカウンター。
音のような直線が、ベースラインぎりぎりに突き刺さる。
会場が静まり返る。
数秒の空白の後、歓声が再び割れた。
ガブリエルは笑い、親指を立てた。
「やるな、王様。」
九条は無言のまま構える。
光と影。笑いと沈黙。
二人のテニスは、まだ始まったばかりだった。
コートを狭くする男
(相変わらず、こいつがいるコートは狭く見える)
九条は目を細めた。
面積は同じはずなのに、ガブリエルが立っている側は、どこか圧縮されたように見える。
身体が大きいだけではない。
動きが異様に早い。
一歩踏み出すだけで、コートの半分を覆うような錯覚。
重心の移動が異常に滑らかで、跳躍のたびに空気が押し出される。
端から端まで——まるで風が通り抜けるように、彼は走る。
守っているというより、そこに先回りしている。
ボールが弾むより速く、ガブリエルの足がそこにある。
フォアからバックへの切り替えが速すぎて、九条は数ミリ単位で打点をずらさなければならなかった。
(反応で動いていない。読んでいる——いや、“感じている”。)
ラリーが続くたびに、ガブリエルの守備範囲が拡張していくように錯覚する。
空間そのものが縮んでいく。
観客席から、笑い混じりの歓声が上がる。
ガブリエルが片手でスライディングしながら拾い、体勢を崩したまま、軽くスピンをかけて前に落とす。
ドロップショット。完璧な深さ。
九条は反応する。
足が滑り、膝が鳴る。
それでも追いつく。
ギリギリで拾い上げたボールは、ネットをわずかに越えた。
その瞬間、ガブリエルが笑う。
「今のは、俺でも拍手だ。」
九条は息を整え、短く答える。
「……勝負はまだ終わっていない。」
観客席がどよめく。
再びラリーが始まる。
ガブリエルの体が動くたびに、コートの空間がさらに狭くなっていくようだった。
支配と敬意
(年が同じだったら、克服できない相手になっていたかもしれない)
そう思うほどに、ガブリエルは今でも十分すぎるほどの強敵だった。
年齢を重ねても、肉体の衰えをほとんど感じさせない。
跳躍も、スプリントも、反応も――いまだに現役の頂点に通じる精度を保っている。
身体で勝負するスポーツの世界において、
“身体が大きく、スピードが速い”という事実は、それだけで他の選手を凌駕する武器になる。
どれほど理論を積み上げても、
どれほど精密に戦略を立てても、
身体そのものの性能には抗えない瞬間がある。
九条は、それを誰よりも理解している。
だからこそ、冷静に認めざるを得なかった。
(この男は、まだ終わっていない。)
これで、もし彼が「場を支配する冷酷さ」を持っていたら――
この時代に、並ぶ者はいなかっただろう。
観客の歓声を切り捨て、勝利のために表情ひとつ変えずに打ち続けるタイプなら、
今ここにいる自分が、その影に埋もれていたかもしれない。
だが、ガブリエル・モレーノは違った。
温かく、優しく、人情味に溢れている。
観客に手を振り、少年のように笑い、
ラリーの最中ですら、相手の好プレーに親指を立てて称える。
それは、勝利を最優先にする者からすれば“隙”であり、
世界一を目指す者からすれば“矛盾”でもあった。
けれどその矛盾が、彼を特別な存在にしている。
人としての温かさが、コートの上でもまだ息づいている。
(……強さとは、冷たさだけでは測れないものかもしれない。)
九条はラケットを握り直し、視線を上げた。
対角のガブリエルが、観客席に笑顔を見せたあと、ふとこちらを見た。
その瞳に宿るものは、敵意ではなく、純粋な“敬意”だった。
九条の中で、何かがわずかに軋む。
それでも、構えは崩さない。
彼にとって、それが“答え方”だった。
強さの孤独
九条の意識が、静かに沈んでいく。
試合前にも入っていた集中状態——それが、今はさらに深く、研ぎ澄まされていく。
周囲の音が遠のく。
観客の歓声も、アナウンスも、拍手も、すべてが膜の向こうに霞んでいく。
代わりに、拾うべき音だけが残った。
ボールがストリングに触れる音。
ガットがわずかに軋む振動。
相手のシューズがハードコートを擦る微かな音。
世界の雑音が消え、必要な情報だけが浮き上がる。
ボールの回転が見える。
風がどう流れ、どの軌道を押し上げるかがわかる。
汗の粒の落ちる位置さえ、予測できた。
だが、同時に——世界が遠のいていく。
相手の表情が見えない。
音は聞こえるのに、意味を持たない。
人間としての気配が、輪郭から削ぎ落とされていく。
(……ここまで来ると、もう“戦う”というより“存在する”に近い。)
九条は息を整え、視界の中心だけを捉える。
ラケットを振る瞬間、空気の抵抗すら計算できる。
身体と意識の境界が曖昧になり、思考が動くより先に、動作が完了している。
完全な集中——
だが、それは孤独だった。
風の流れが見えるのに、世界は遠い。
相手も、観客も、音も、ただ“存在しているだけのもの”になっていく。
その静寂の中で、九条の胸の奥にかすかな痛みが走る。
“感じる”ということを、どこかに置いてきたような痛みだった。
体の感覚が、研ぎ澄まされていく。
それなのに——どこか鈍い。
筋肉の動きが、指令よりも先に反応する。
だが、その動きに“感覚”がない。
指先の圧も、足裏の重みも、まるで他人の身体のようだ。
頭は何も感じていない。
何も考えていないのに、熱だけがある。
脳が焼けるような、透明な熱。
それが全身を満たし、皮膚の内側を走っていく。
呼吸の音が、やけに大きく響く。
肺の空気が出入りするたび、鼓膜の奥で波のように音が揺れる。
心臓の鼓動が聞こえる。
どくん、どくん、とリズムを刻む音が、血流の動きと同期して世界を震わせる。
それでも、周囲の音は遠い。
観客の声も、ボールが弾む音も、
どこかの向こう側で鳴っているように感じる。
風の流れだけがはっきりと分かる。
その軌跡が、視界の中を線のように走る。
だが、人の気配はもう消えていた。
世界は、光と風と、打球の軌道だけ。
音も、感情も、すべてが薄れていく。
九条は、まるで自分の意識だけが肉体から少し浮いたような感覚の中で、ただ“戦い”という行為の中心に在った。
命を削る競技
全てが、スローに見える。
ガブリエルの動きが、分解されていくように見える。
肩の回転、重心の移動、足の角度。
一つ一つの動作が、まるで時間を遅くした映像のようだ。
次に何をするのか。
どう動くのか。
どこへ向かうのか。
その“未来”が、目の前で再生されている。
九条の体はそれを追い越すように動く。
考えるよりも先に、反応していた。
それが「考える」という行為だったことすら、もう分からない。
だが、奇妙な空白があった。
今、何ポイントなのかが分からない。
あと何ポイント取れば終わるのかも分からない。
試合がどの段階にあるのかさえ、もう判断できない。
(……分からなくても、いい。)
思考が削ぎ落とされ、残ったのはただ一つ。
相手が止まれば、終わり。
それだけだった。
観客の声が消えている。
実況のマイクも、審判のコールも、すべてが無音の世界に沈んだ。
ラケットがボールを打つ音だけが、かすかに残る。
だが、それすらも内側で鳴っているように聞こえる。
視界の端で、ガブリエルの口が動いた。
何かを言っている。
だが、音はない。
形だけが、光の中でぼやける。
その姿さえ、輪郭が淡く滲んでいく。
ただ、ラケットとボールと空気の抵抗。
それだけが、確かな現実だった。
時間が止まったような感覚の中で、九条は“動き”そのものになっていた。
深海の底に沈んでいくようだった。
音が消えた。
声も、風も、観客のざわめきも。
世界そのものが、遠い水の向こうにあるように感じる。
何も聞こえない。
何も感じない。
暑さも、痛みも、不快さも、冷たさも――すべてが消えた。
体の境界が曖昧になり、動いているのが自分かどうかさえわからない。
ただ、目の前のボールを追いかける。
打ち返す。
相手が打てない場所へ。
打てないスピードで。
その一瞬だけが現実。
他のすべては存在しない。
世界がどれほど静かでも、心拍だけは、どこか遠くで微かに鳴っていた。
それもすぐに沈む。
もう、音も光もいらない。
ここにあるのは、ただ“打ち続ける”という行為だけ。
終わるまで――延々と、それを繰り返す。
この場所にあるのは、勝敗でも感情でもない。
ただ、時間だけだ。
冷たく、均一に流れ続ける、ひとつの時間。
装置になるまで、戦う
終わりは、唐突だった。
どんなラリーだったのか。
どんなショットで終わったのか。
その記憶がない。
ただ、気づけば静寂が訪れていた。
球の音も、観客のざわめきも、審判のコールもない。
時間が切断されたように、そこだけが止まっている。
かろうじて視界の中に、ネット際に立つ相手の姿があった。
その姿を見た瞬間、
体が自動的に動いた。
ネットへ歩く。
手を差し出す。
握る。
離す。
それだけ。
感情も、言葉もない。
まるでプログラムのように、次の動作へと移っていく。
ガブリエルが何かを語りかけている。
口が動く。
笑っているようにも見えた。
だが、音は聞こえない。
意味もわからない。
世界の音が、完全に消えている。
ただ、自分だけがそこに立っている。
一人で。
何も考えず、何も感じず。
勝つまで戦い続けるだけの、
“装置”のように。
静寂の中で、九条の呼吸だけが残った。
それもすぐに、音ではなくなった。
動きだけが、まだ続いていた。
深淵から引き戻す手
ロッカールームのベンチに腰を下ろした瞬間、背後から何かが首筋に触れた。
温かく、力強い手。
背中、首筋、肩――順に確かめるように、
その手が触れていく。
「……九条。」
低く、少し掠れた声がした。
遠くで響いていた音が、ゆっくりと近づいてくる。
呼吸の音。足音。
世界の輪郭が、少しずつ戻ってくる。
「九条、九条!」
もう一度、名前を呼ばれる。
その声で、ぼやけていた視界がようやく焦点を結んだ。
黒い影が、光の中から浮かび上がる。
――ガブリエルだった。
額に汗を滲ませ、息を荒げている。
だが、その瞳は真剣だった。
冗談も笑顔もない。
ただ、確かに“心配している”目だった。
隣には志水がしゃがみ込み、九条の手首を取って脈を測っている。
「……戻ってきたな。」
志水の声が静かに響く。
九条は深く息を吸い、肺の奥で酸素が焼けるように感じた。
頭がまだ重い。
世界の音が、現実の位置を取り戻していく。
ガブリエルが短く息を吐き、「おい、王様。……どこ行ってた?」と笑う。
九条はゆっくりと視線を上げ、
彼を見た。
声にならない声で、かすかに答える。
「……試合に、いた。」
ガブリエルが少しだけ目を細め、「そうか。……帰ってこい。もう終わった。」と静かに言った。
九条の肩に置かれた手が、温かいまま、確かにそこにあった。
呼吸を取り戻す
「九条、生きてるか?」
低い声が耳に落ちてくる。
「……見ての通りだ。」
息を吐くように答えながら、九条は自分の声が思ったより掠れていることに気づいた。
死んでいるように見えたのか――そんな考えが一瞬だけ頭をかすめる。
「生きてるようには見えなかったから、そう聞いたんだよ。」
ガブリエルが肩をすくめる。
その顔には、いつもの調子で笑みが浮かんでいた。
汗に濡れた額、黒い肌、白い歯。
どれも試合の熱をまだ引きずっている。
「息できたか?」
「……どういう意味だ。」
「息をしてないように見えたんだ。」
ガブリエルが軽く笑う。
「だからこうして、お前のとこに来た。絶世の美女じゃなくて悪かったな。」
その冗談が、あまりに自然で、九条は返す言葉を失った。
黒い肌に白い歯の大柄な男――まるで太陽の形をした人間だった。
その笑い声は、ロッカールームの静けさを押しのけて広がる。
九条は目を閉じ、わずかに息を整えた。
たしかに、さっきまで息をしていなかった気がする。
呼吸の仕方すら忘れていた。
「……そうか。」
その一言だけが、
九条の中で再び“現実”をつなぎ止めた。
支える者たち
ふと気づくと、志水だけではなかった。
周囲には蓮見の姿も見えた。
少し離れた場所には早瀬、そして神崎も。
皆が九条の様子を見守っていた。
それぞれの視線に、職業的な冷静さと、個人的な心配が混ざっている。
「……チーム全員集合、か」
九条がかすれた声で呟くと、蓮見が短く笑った。
「お前がロッカールームで倒れたって聞いたら、全員動くに決まってんだろ。」
その隣で氷川がタブレットを手にしていた。
「メディア対応、遅らせますか?」
九条はわずかに首を横に振った。
「いや……行く。」
声はまだ低く、重い。
だが、その響きにはいつもの硬質な意志が戻っていた。
呼吸は落ち着いてきている。
視界はまだわずかに霞んでいるが、音はもう現実の距離で聞こえていた。
言葉も、思考も、戻ってきている。
神崎が手を伸ばし、脈を測る。
「血圧は正常範囲内。過呼吸の兆候もない。……ただ、少し脱水気味だな。」
志水が首の筋肉を軽く押しながら確認する。
「痙攣はありません。筋反応も正常です。」
早瀬は膝の可動を見て頷いた。
「関節に異常なし。フォームも乱れてなかった。……精神的な極限状態でしょう。」
九条は黙ってその声を聞いていた。
皆の報告が、まるで現実の輪郭を少しずつ取り戻していくようだった。
蓮見が腕を組み、短く言った。
「……まったく。勝って倒れるやつがあるかよ。」
九条は小さく息を吐く。
「倒れた覚えはない。」
九条は最後まで立っていたし、終わっても自分で座ったはずだ。記憶はなくとも。
ガブリエルが壁際で肩をすくめる。
「倒れてなくても、魂はどっか行ってたけどな。」
その言葉に、志水が思わず笑う。
九条は目を閉じ、静かに息を整えた。
身体はまだ熱を持っている。
けれどもう、地に足がついている。
現実に戻ってきた。
自分の戦場に。




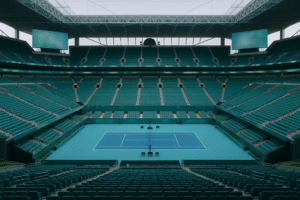

コメント