待ち合わせ
スーツケースを引き、澪は足元を見ながら歩いていた。
スマホで九条との待ち合わせ場所を確認しつつ、ハンドバッグの中にそっと手を入れる。中には、焼いたロッククッキー。緩衝材代わりに入れた柔らかいタオルの奥に、ぎゅっと隠すように詰めてある。
(はー…緊張する…)
深呼吸ひとつ。
澪は“こう見えて”人見知りだ。
職場では営業スマイルでなんとかやれても、知らない男性ばかりの空間は、本当に苦手だった。
ましてや、世界のトッププロを支える精鋭チーム。
肩書きだけで胃が痛くなる。
(ちゃんと挨拶できるかな。変な人って思われたくない…でも無理して明るくするのも変だし…どうしよ……)
スーツケースのキャスターが床に響く音だけが、緊張を際立たせる。
夜、羽田空港近くの専用ゲート前。
澪は指示された住所を頼りに、タクシーで到着した。
普段の空港ロビーのような喧騒はなく、そこにあるのは控えめな照明と、ひっそりと構える「Private Gate」の小さなサイン。
降りた瞬間から、緊張が襲う。
(え、ここ…本当に空港?)
(人がいなさすぎて、逆に怖い…)
スーツケースを引いて建物の前まで歩くと、すでに何人かが集まっていた。
揃いの黒いアウター。誰も笑っていない。
威圧感があるというより、ただ“静かに整っている”印象。まるで軍人の待機列。
その中に、ひとりだけ雰囲気が違う人がいた。
九条 雅臣。
彼が目線だけでこちらを認識したのがわかった瞬間、澪の背筋がぴん、と伸びた。
氷川、レオン、藤代の顔が見えて、少しだけ安心する。
「こんばんは。お疲れ様です。綾瀬です。初めまして…」
カチカチに緊張して、仕事モードとも違う、どこかぎこちない挨拶をする澪。
思ったよりも声は震えなかった。けれど、どこか浮いている気がした。
一歩、前に出てきたのは、柔らかな雰囲気の男性だった。無表情ではないが、感情を強く見せるタイプではなさそうだ。
「蓮見です。よろしくお願いします」
落ち着いた声音で、穏やかに会釈される。少しだけ、緊張がほどける。
続いて、もう一人、背筋をすっと伸ばした男性が名乗った。
「九条の専属医をしています。神崎です。長旅になりますが、よろしくお願いします」
知性と冷静さが滲んだ口調。少し緊張したまま澪は頭を下げた。
「……はい。よろしくお願いします」
ふと視線を移すと、後ろでじっと澪を見ている男がいた。無表情で、口を開こうともしない。
「志水。トレーナーだ」
九条が簡潔に紹介すると、男は無言のまま、わずかに頷いた。それがすべてだった。
――話しかけるべきか、黙っておくべきか。迷った末に、澪は少し声を張った。
「……よろしくお願いします」
返事はなかったが、目は逸らさなかった。拒絶されたわけじゃない。
九条から聞いていた人数よりも、集まっている人数が一人多い。その人は、短めの髪を片側だけ耳にかけ、黒い細身のパンツスーツを着ていた。肌が白くて、輪郭も整っていて、まるで男性モデルのような雰囲気。首が細く、手も華奢で、全体的に中性的だが、美容師というよりは“プロの表舞台に立つ人”のようなオーラがある。
「チーム専属の美容師だ。風早蘭」
九条がさらりと紹介する。
「ども」
低めの落ち着いた声で、風早が軽く片手を上げる。
男なのか、女なのか、一瞬で判断がつかずに澪が戸惑っていると、横からレオンが小声で補足してくれる。
「みんな“カザラン”って呼んでるよ。名字の“風早”と“蘭”を合わせて」
「…あ、なるほど」
聞いてもなお性別が分からない。でも、雰囲気からしてチームにとっては“戦力”であることだけは感じ取れた。何より、あの九条が紹介したということが、それを証明している。
澪は、スーツケースを片手に搭乗した。プライベートジェットの機内は、前回よりも人の気配が多く、ほとんどの席が埋まっていた。
「……やっぱり今回は、全員揃ってるんだ…」
前方の座席には蓮見コーチと神崎医師。奥に氷川と志水、早瀬の姿も見える。そして九条は、機内の一番奥。いつもの定位置。澪は一礼して通り過ぎながら、カバンの中のジップバッグをそっと握り直した。
(いつ渡すのが、自然なんだろ……)
百均で買った、九条っぽい色味のシンプルな袋に入った手作りクッキー。バレンタインだからってだけじゃない。約束してたし、焼いたし、ちゃんと持ってきた。でも、誰かに見られながら「はい、バレンタインです」なんて……無理。
(…席に座って、しばらくしてから?)
でもその頃には、他のメンバーも落ち着いてる。見られる。
(じゃあ、出発直前?)
でも九条が忙しそうだったら……声、かけづらい。
(ええい、じゃあ……トイレ行ったふりして、戻る時にこっそり?)
――あまりに怪しい。
それでも、頭の中ではずっとそのことを考えている。
カバンの中、ほんのりバターと砂糖の甘い香りが漏れている気がして、落ち着かない。
(…ほんとに、いつ渡せばいいの…)
澪の中では“勇気出して一言だけ話しかけて渡す”という小さな決戦が、ずっと準備され続けていた。
機内へ
(……ここ、座っていいのかな)
澪は通路の途中でふと立ち止まる。機内後方にいくつかの空席はあるが、誰かの“指定席”だったらと思うと、勝手に座る勇気が出ない。
そのときだった。
「――こっち来い」
聞き慣れた、低くて静かな声が背後からかかる。
振り向くと、九条が、自分の隣の二人がけの席を指で示していた。
通常、九条は一人がけの席に座って、一人で窓の外を見て過ごしているけど、今日は違った。輪に入ることを嫌う男が、輪を作る席を選んで座っている。
澪が戸惑っている間に、彼はもう視線を窓の外に戻した。
(……あ、ここ座っていいんだ)
その隣に腰を下ろすと、九条の前にある小さなテーブルを挟んで、反対側の二席には氷川と藤代が静かに座った。会話はない。けれど、どこか妙に落ち着いた空気があった。
しばらくして。
「……何か言いたそうな顔してる」
静かな声が、すっと耳に入る。隣の九条は窓の外を見たまま、目線も動かさない。
「え? い、いや、別に」
反射的に否定しつつ、澪はつい鞄の中に目を落とす。その動きに呼応するように、九条が手を、差し出した。
ただ、黙って。
(……あ、気付いてるのか、鞄の中……)
澪の胸が、きゅっとなる。さっき、焼きたてのクッキーを見せたカメラ越しの映像が、ちゃんと記憶に届いていた証拠だった。
何も言わずに差し出されたその手に、そっとラッピングした袋を乗せる。
「…その、潰れてないといいんだけど」
受け取った九条は、袋の重さを確かめるように少しだけ手のひらで転がして、それから静かにポケットにしまった。
「……バレンタインだからって、気張ってないからね。ほんと。ラッピングも100均で……」
言い訳のようにぽつぽつと話す澪に、九条はようやく横目でちらりと視線を向ける。
「見てるのは中身だ」
「……ありがと。でも、ほんと見た目可愛くないからね。ロッククッキーって、そういうものだから」
「知ってる。形が歪で、香りが甘いやつだろ」
(うわ……言われた……)
電話の時に言ったこと、ちゃんと覚えてた。
澪は顔がほんのり熱くなるのを誤魔化すように、ペットボトルの水を開けた。
自分のおやつ
「……まだ甘い匂いがする」
そう言って、九条がほんの少しだけ顔を近づけてくる。視線はまっすぐじゃなく、澪の鞄の方。
「え、うそ。匂い漏れてる?ちゃんと密閉したつもりなんだけど……」
慌てて鞄のファスナーを確認する澪。確かにジップ付きの袋に入れて、しかも更に布袋でくるんだはずなのに。
「……自分の分だな」
「えっ……なんで分かるの」
「お前が人に渡して終わるわけがない」
ぎくり、と澪は肩を揺らす。
「せっかく作ったし、自分でも食べたいんだもん。結構美味しいし。でもチョコとか、レーズン入れたから、雅臣さんのより甘いと思う」
そう言いながら、澪は鞄の中を少しごそごそと探る。
「俺のは入ってないのか?」
「そっちは意識高い系なので、オートミールとナッツです。食物繊維多め、血糖値を上げすぎない仕様」
「……ほう」
九条は興味深そうに目を細めた。だが、それ以上何も言わない。
すると、向かいの席からふと、視線を感じた。澪がそっと目を向けると――
氷川が、手元のタブレットを見たふりをしながら、チラッとこちらのクッキー袋を見ている。
(……え、気になるのかな)
明らかに「チョコとレーズン入り」の方を見てる。健康仕様より、絶対そっち派の顔してる。
澪が苦笑しながら視線を合わせると、氷川はすぐ目をそらして「……別に」と小さく呟いた。
その瞬間――
「氷川。欲しいなら、言えばいい」
九条がさらっと言う。
「いえ、遠慮し――」
「一枚くらいはある」
澪が自分用に持ってきたラッピングなしの袋から、チョコチップ入りを取り出した。澪が鞄から取り出したクッキーの袋は、思ったよりもパンパンだった。
「……一枚って……もっとあるよ? たぶん十枚以上あげられる……」
ぼそっと呟くと、向かいに座っていた氷川が少しだけ目を丸くした。
それでも、九条は何食わぬ顔で言った。
「一枚なら許可する」
「……え?」
あまりに冷静で、理不尽なまでに“支配的”なその物言いに、澪が思わず聞き返す。
「ちょ、何その“分配権は俺”みたいなやつ……私が作ったんだけど……」
「配るのはお前。判断するのは俺だ」
「それは横暴では……」
「氷川が今、食べる一枚に異論はない」
「限定品すぎる……」
不満を飲み込みながらも、澪はクッキーをもう一枚取り出し、氷川にそっと差し出す。
「……どうぞ……」
「ありがとうございます。じゃあ……遠慮なく」
氷川は慎重に受け取り、まるで壊れ物でも扱うように大事そうに袋を手に取った。
「――あんまりやるな。お前の分が減る」
低く静かな声が、隣から飛んできた。九条が澪の手元をちらと見て、言葉を差し込んでくる。
「なんでそんな意地悪言うの。あなたのマネージャーさんなのに」
「だからこそだ」
即答に、澪は思わず眉をひそめる。
「日頃お世話になってるから、せめてものお礼として…」
「氷川は仕事だ」
「……仕事でも差し入れは必要です」
そう返すと、九条はしばらく黙ったまま、視線だけで「気に入らない」と言っていた。
向かいに座る氷川は、そんなやりとりにも無反応で、ただ淡々とクッキーの袋を受け取っていた。
ヤキモチ
そんな微妙な空気の上に――
「ねぇレオン、あれ…」
「うん、完全にヤキモチだね」
背後からひょいっと顔を出したのは、レオンとカザラン。
席の背もたれの上にあごを乗せて、完全に“見てたよ”という顔。
「嫉妬、拗らせてるだけじゃん」
「かわい~~」
澪は一瞬目を見開いて、それから顔を赤くする。
にこにこ笑うカザランの声に、九条がじろりと横目を向けたが――
その嫉妬深い目つきすら、レオンとカザランにとっては格好の“からかい甲斐”だった。
まだ諦めない
「ねえねえ、綾瀬さん」
通路を挟んだ隣の席でリラックスしていた蓮見が、ふいに身を乗り出してくる。
「はい?」
「イギリスでさ、九条の執事服作るんだって?」
「……あ、はい。素材選びと採寸は前回終わったので、今回は仮縫いの確認を――」
「仮縫い中のとこ、写真撮っといてもらっていい?」
「おい」
低い声が飛ぶ。九条が澪の真横で睨んでいた。
「まだ諦めてなかったのか」
「諦められるわけねーだろ!こんな面白いこと!」
「椅子に縛り付けるぞ」
「縛り付けられても言う!絶対に写真と動画が欲しい!」
「今すぐ降りるか?」
「もう離陸なのに!?」
「まだ地上だ。死にはしない」
そのやりとりを、レオンが腹を抱えて笑いながらスマホのメモを開いていた。
「“仮縫い中の九条様”、ってメモしとくね。完成まで何枚写真撮れるかなー」
「勝手にシリーズ化するな」
「せっかくだから動画は縦長で。TikTok向けに」
「絶対に許さない」
「執事服完成したら、ダンス動画撮ろうぜ」
蓮見の目が本気だ。ワクワクと期待に満ちている。
「殺すぞ」
即答。急に物騒。
その場が一瞬、凍りつく。
……が、次の瞬間、レオンが吹き出した。
「ちょ、唐突すぎて怖っ……でもちょっと想像した……」
「メイド姿の澪ちゃんと並んで踊ってほしいな。バレンタイン限定で」
「全員黙れ」
淡々と、低音で、重みだけがのしかかる。
そんな中、カザランが何食わぬ顔で、
「その際のヘアメイクは、お任せください」
と、しれっと差し込んだ。
数ミリの変化
「ところで九条さん、髪伸びましたね」
カザランが、何気ない声でぽつりと言った。
「先月末に切ったきりだからな」
九条は軽くそう返したが、実際に伸びたのは一センチもない。ほんの数ミリ。
だが、カザランはその“数ミリ”を見逃さない。
「イギリス着いたら、時間見つけて切りましょうか。ドバイの試合までには、整えておいた方がいいですし」
「そうだな」
九条はごく自然に頷いた。
彼にとっての“髪”は、単なる身だしなみではなく、スポンサー契約の一部。
ほんのわずかな乱れも許されないことを、カザランは誰よりもよく理解している。
それなりの仕事
レオンが「だからカザランの報酬は桁が違うんだよね~」と背もたれの向こうでこっそり呟く。
「いやいや、チーム内で一番稼いでるの、蓮見さんですから」
カザランが、スケジュールを見たまま、何気ない調子でさらっと言った。
「え、そうなの?」
レオンが小さく目を見開く。
「そりゃーそれなりの仕事してるからな、俺」
蓮見が胸を張るように腕を組む。
「ボールぶつけられそうになりながら走って逃げるとかね」
ふかふかの毛布を被って寝かけていた志水がぼそりと差し込んだ。
「……あれはマジで死にかけた」
笑い話にしたいのに、誰も笑わない。本人も笑えてない。
あの事件――明らかに狙って打たれた一本――が、チーム内では“触れていいギリギリのネタ”として扱われていることは、澪にも伝わった。
「いやほんと、プロのサーブで殺意向けられたら洒落になんないからな……」
蓮見が小さく震えるふりをすると、レオンが後ろでこっそり合掌していた。
「雅臣さん、そんなことしたの?」
澪が驚いたように身を乗り出す。
冗談で聞いたつもりだった。まさか本当にそんな、命中させる気でボール打ったなんて――
「……あれは蓮見が悪い」
あまりにも即答で、あまりにも真顔だった。
「お前! 長年連れ添ってきたコーチに対して言うことか!」
後ろの席から蓮見が思わず叫ぶ。
「お前には言ってない」
九条は静かにそう返す。
目線も、声も、完全に澪だけに向けたまま。
――澪への返事として、それだけだった。
「……あー……うん……」
澪がちょっとだけ黙って、苦笑いを浮かべると、
カザランが吹き出しそうになって、必死で手を口に当てていた。
世界一の条件
「このチームには……常識が通じる人が一人もいない……」
神崎医師が、ため息混じりにぼやいた。
周囲からは笑い声が漏れるでもなく、妙にしっくりとした沈黙が流れる。
その静けさの中で、珍しく、氷川が口を開いた。
「常識で動いていたら、恐らく――世界一にはなれていません」
真面目な声音で、まっすぐに。
反論、というよりも、事実の確認のような口調だった。
その言葉を聞いて、澪はふと、自分が九条に初めて会った日のことを思い出す。
――そういえば、あの時もびっくりしたな。
家の中に玄関がないことも、車も家も真っ黒ばっかりで全体的に無彩色なのも、冷蔵庫に何も入ってないのに、ワインセラーにはぎっしりワインが入ってることも。
日常のどこを切り取っても、まるで別世界みたいだった。
「この人、やっぱり特別なんだな」って――あの頃は、ただそう思っていた。
でも今では。
あの非日常が、ほんの少しだけ馴染んでいて。何が起きてもあまり驚かなくなってきた。
まだ一ヶ月も経っていないのに、
あの日の驚きが、ずいぶん昔のことのように思えるのが、なんだか不思議だった。
仮初の世界のはずが
――私は、ずっと思ってた。
ここは、私のいる場所じゃない。
一時的に、ちょっとだけ置いてもらってるだけで。
そのうち元の世界に戻るって、ずっと思ってた。
今だって、きっと本当はそうなんだろう。
なのに気が付けば、私はまたこうして彼の隣にいて、
チームの誰かと笑い合って、
プライベートジェットでイギリスへ向かってる。
しかもそのまま、ドバイまで一緒に行く予定で――
……部外者のはずなのに。
今は、どういうわけか、この輪の中に入れてもらっている。
でも、それは“入っていいよ”って言われたからじゃなくて、
誰も「入るな」と言わなかったから、ただ、そこに居るだけだ。
私がここに居てもいい理由なんて、どこにもないのに。
自分だけ、ずっと椅子を借りて座ってるような感覚。
「お前はその席にふさわしくない」って、いつか誰かに言われそうな気がしてる。
それなのに、笑ってしまった。
レオンさんや蓮見さんの冗談に、小さく肩を揺らして。
作ってきたクッキーを欲しがって、氷川さんがそれをじっと見てて――なのに彼は1つしか許可しなくて。
まるで、それを毎日見てきたような気がして。
……こんなふうに過ごしていると、
時々、自分がどこにいたのか、わからなくなる。
元の世界に帰ることを忘れて、
ここが当たり前みたいに感じる瞬間がある。
それがいちばん、怖い。
だって私は、この人たちみたいにはなれないから。
誰よりも速く走れるわけでも、支えられる技術があるわけでも、プロフェッショナルとしてここに居るわけじゃない。
私は、誰の“必要”でもない。
……だから、笑うたびに、少しだけ胸が痛む。
まるで、それが許されていないみたいに思えてしまうから。
(…私は、やっぱり、ここに居ていい理由なんて――)
そんなふうに、心の奥でまた椅子を返しそうになっていたとき。
不意に、九条がこっちを見た。
「忘れ物があれば、向こうで買う。すぐ言え」
ポツリと落とされたその一言に、澪は思わず顔を上げた。
「……うん」
九条は既に視線を戻していた。何かiPadで書類に目を通している。その態度はどこまでも事務的で、優しさのつもりなんて、たぶん一ミリもない。
「フライトが長い。ちゃんと寝ておけ。着いてから体調崩すなよ。イギリスとドバイで、時差に慣れる時間はない」
(……あ、そっか)
気付けば、短期間に移動する国は三か国。
彼にとっては当たり前のスケジュールでも、澪にとっては未知の旅路だ。
だけど九条は、「女の子だから」「慣れてないから」なんて特別扱いはせずに、ただ当然のように、彼女がそこにいること前提で話してくる。
そこには余計な感情もないし、優しい声色もない。ただ、事実としての“配慮”。
――それが、逆に沁みる。
この世界には、まだ“仮住まい”の気持ちがどこかにあって、
「私は場違いなんじゃないか」と、思う瞬間がふとよぎることもある。
けれど、こうして何でもないように「体調を崩すな」と言われると、
それがまるで、最初から居るべき場所だったみたいに思えてくる。
(……なんで、そんな風に自然に言えるんだろう)
澪は、少しだけ深く椅子にもたれた。
目を閉じてみれば、緊張していたはずの肩の力が、少しだけ抜けていた。
騒がしい離陸
「離陸まで数分です。皆さん、座ってシートベルトをしっかりお締めください」
機内に氷川の声が響く。静かだけど、聞き取りやすく通る声。
「はーい」
「了解でーす」
カザランとレオンが、背もたれからぴょこんと顔を出して、ふざけたような声で応える。
(……え、意外と騒がしい)
澪は内心、驚いていた。もっと張り詰めた空気かと思っていた。だけど、ほんの少しだけ肩の力が抜けた。
後方では、志水と早瀬が既に毛布にくるまって、目を閉じている。移動中は寝て体力温存――完全に“仕事モード”に入っている二人の姿は、逆に頼もしい。
その隣で、神崎医師が澪の席まで歩いてきた。
「酔い止め、ありますから。もし気持ち悪くなったら、無理せず言ってくださいね」
穏やかな声と目線。医師としての冷静さと、人としての優しさが同居している。
「あ……ありがとうございます。大丈夫です」
そう答えながら、澪の心に、じんわりと温かさが広がっていった。
目の前にいるのは、プロの集団。
でも、ピリピリしているわけじゃない。
“世界を支える空気”は、案外ざっくばらんで、優しさに満ちていた。
(……私、今この中にいるんだ)
ふとそんな実感が湧いた瞬間、澪は少しだけ表情を緩めて、ブランケットを膝にかけた。



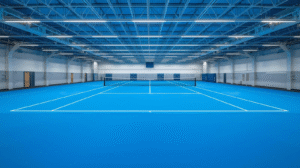




コメント