寝る前に
部屋の灯りを落としてから、まだ数分。
九条はシャワーを浴びて戻ってきたばかりで、髪の先に水滴を残したまま、無言でベッドに入る。
澪はすでに布団に包まっていたが、九条が隣に入ると、その存在だけで温度が変わるのがわかる。
すっと背後から腕が回される。
肌に触れる手のひらが、ゆっくりと腰に滑る。
「……今日は、疲れてるんじゃないの?」
そう囁いた澪の声に、九条の鼻先がうなじをなぞる。
「お前に触れたら、目が冴えた」
その低い声と、耳の後ろを撫でるような吐息に、澪の背筋が震える。
指先が、布の上から優しくなぞる。
急がず、焦らず、ただ“触れていたい”だけのように。
「…ねえ、今日は……寝るんじゃなかったの?」
「寝る前に、温度を確かめておきたいだけだ」
「……なにそれ……」
言葉ではからかいながらも、澪の身体はもう抵抗していない。
呼吸がゆっくり深くなり、九条の手に自分を預けていく。
「お前がそばにいる夜は、眠るのが惜しい」
そう呟いて、九条は首筋にそっと唇を落とした。
それはキスというより、肌に印を残すような“確かめる行為”。
澪は背中を預けるようにして、九条の胸元にすっぽりとおさまる。
「……週末、またイギリスでしょ?」
「そうだ」
「今週中に、あんまり疲れたくないんだけどな……」
「…努力はする」
「できるの?」
「……してみる」
返事は少しだけ間があって、それがかえって優しかった。
澪が笑いながら振り返ると、九条の顔がすぐそばにある。
迷うような間があって、そっとキスをする。
唇が重なった瞬間、ミントの味とひんやりした感触が交差する。
火照るような感覚じゃない。ただ、静かに、触れ合うだけのキス。
名残惜しそうに唇を離すと、九条が耳元で囁いた。
「……起きていられるなら、ずっとこうしていたい」
「でも明日、お互い仕事だよ」
「わかってる」
そう言っても、九条の手は腰から背中を撫でるように動いていた。
でも、それ以上は何も起きなかった。
心も身体も、満たされている。
“触れたくて仕方がないのに、抑える”――その静かな熱が、2人の距離をもっと近づけていた。
「ねえ、私お昼寝しちゃったから、あんまり眠くないかも」
九条の胸元でそう言うと、彼は低く静かな声で返す。
「……余計なことを」
「え?」
「寝ててくれた方が、理性が保ちやすい」
その言葉に、澪はちょっと嬉しそうに笑う。
でも、九条の腕は本気で離そうとしない。
「ねえ、ちょっとだけキスしてもいい?」
返事はなかったけれど、九条の手が頬に触れて、優しく顔を引き寄せてくる。
くちづけは静かで、けれど長くて、澪の背中が小さく震えた。
口の中に、歯磨き後のミントの味がほんのり残っていて、余計に相手の温度が鮮明になる。
「私は今日お休みだったから、雅臣さんが先に寝て」
ベッドの中、澪が掛け布団を軽く整えながらそう言った。
九条はすぐに目を閉じるでもなく、静かに天井を見たまま応じる。
「……指示か?」
「違うよ、お願い」
「なら、拒否してもいいのか」
「……うん。でも、寝かせてあげたい気持ちは本当」
少しの間、沈黙。
けれど次に聞こえた九条の声は、わずかにトーンが低かった。
「俺を先に寝かせようとするのは、お前くらいだ」
「そうなの?」
そう答えた澪の声は柔らかくて、迷いがなかった。
ベッドの中、澪はそっと九条の髪に指を伸ばした。
寝る前の静かな時間。
部屋の照明は落とされて、ほんのわずかな月明かりが窓辺から差し込んでいる。
九条の頭をやさしく撫でながら、澪が小さな声で言った。
「こうしたら、眠れるかと思って」
九条は目を閉じたまま、ほんの少しだけ眉を動かす。
「……子供か」
「でも、気持ちよくない?」
撫でる指先に、力はない。
ただそこにあるだけの、静かな優しさ。
しばらく間があってから、九条がぼそりと呟いた。
「……悪くはない」
その声が少しだけ低くて、わずかに甘さを含んでいたのは、気のせいじゃない。
澪は、くすっと笑って――もう一度、髪を撫でた。
翌朝
テーブルの上には、レオンが早朝に準備した朝食が並んでいた。
味噌汁の湯気がゆるやかに立ち上り、玄米のおにぎりと焼き鯖、彩りのあるサラダボウルが皿の上に整然と並ぶ。
澪は湯呑みを手に取りながら、軽く息をついてから言った。
「来月、大きいボートショーがあるの。だから、その準備で外出の予定も増えてて……今日もその一環で、午前中から外回り」
「屋外か?」
「うん、展示場。現地でクライアントさんと打ち合わせしてくる」
「寒さには気をつけろ。風も出るはずだ」
「はーい」
気の抜けた返事をしながらも、澪の表情は引き締まっていた。
出勤用に整えた身なりは凛としていて、朝の眠気などすっかり抜け落ちている。
「帰りは?」
「19時前には戻れると思う。そっちは?」
「午前は低酸素ルーム。午後は昨日より強めにクレーで追い込む」
「じゃあ帰ったらすぐストレッチね。お風呂、ちゃんと温まってね。シャワーじゃなくて」
「お前が帰る前には済ませておく」
そんなことを言い合いながら、2人は向かい合って淡々と朝食をとる。
けれど、声の奥には互いを案じる色がきちんとある。
澪の出勤
外の冷たい空気の中を一歩ずつ歩いてきたはずなのに、エントランスを抜けると、途端に現実が背筋に乗ってきた。
澪はエレベーターのミラー越しにもう一度自分の髪を確認し、小さく息を吐く。
「綾瀬さん、おはよう」
「おはようございます」
いつもの受付スタッフに軽く会釈し、カードキーでゲートを抜けて自席へ。
そのときだった。
「綾瀬さん、ちょっといい?」
振り向けば、直属の上司が手に資料を持って立っていた。
穏やかで物腰の柔らかい人――澪にとっては、数少ない“話しやすい大人”のひとりだ。
「はい、大丈夫です。どうかされました?」
「あの……うん、ごめんね。朝から。ちょっとだけ頼みたいことがあってさ」
言いながら、どこか申し訳なさそうに眉尻が下がっている。
澪は少し驚きつつも、自然と微笑んだ。
「大丈夫ですよ。なんですか?」
「……ありがとう。いや、ほんと、無理は言わないけど、綾瀬さんにお願いできたら心強いなって思って」
詳細には触れられなかったが、口調と表情で十分だった。
誰かに押し付けるような頼み方ではない。
できることなら助けたい、そう思わせる誠実な上司だった。
「わかりました。じゃあ、あとで会議室で内容、教えてください」
「助かる。ありがとうね」
その一言に、上司は心底ホッとしたように頭を下げた。
澪は席に戻る途中、自分でも不思議なくらい自然に笑っていた。
無理を押し付けられるのは苦手だけど――信頼されて頼られるのは、嫌いじゃない。
低酸素トレーニング
酸素の薄い空気が、肺の奥にざらついた感触を残す。
走るたびに、わずかに遅れて心拍が追いついてくる。
低酸素ルーム――人工的に作られた高地環境。
この部屋では、外の世界と時間の流れが違う。
九条雅臣は、何も言わずにトレッドミルの上を走り続けていた。
フォームは崩れない。背筋は一直線のまま、一定のリズムで足が地面を蹴る。
静かだった。
モニターに表示された心拍数と酸素飽和度が、唯一の会話相手。
息が上がってきても、声にはしない。
この苦しさは、選んだものだ。誰にも訴えない。
「……あと5分」
志水が無言で指を立てる。
それに頷くこともなく、ただ九条は視線を前に戻す。
感情を排したまま、ただ心を追い込む。
“どこまでいけるか”を測るためじゃない。
“行くと決めた場所に、どんな状態でも届けるため”の訓練だ。
スピードが上がった。
制御された酸素の中で、マシンが吐き出す風すら重たく感じる。
それでも、彼は止まらない。
限界は、自分が決めるものだ。
今日もまた、それを確かめるために――走っている。
低酸素ルームから出てきた九条は、すぐに志水の渡したタオルで汗をぬぐい、深く息を吐く。呼吸は乱れていないように見えるが、神崎は手元のモニターを確認しながら言った。
「水分、すぐに。ミネラルも含めて」
無言で受け取り、口をつける九条。
「ストレッチ入れて10分、クールダウン。今日の午後は実戦形式だから、午前で筋肉を追いすぎるな」
志水が無感情にそう伝えると、九条は静かにうなずいた。
その様子を見ながら神崎がポツリと漏らす。
「低酸素下の反復走は、地味に内臓に来る。明日以降のコンディションに影響出たら、本末転倒だ」
「分かってる」
「分かってるなら、早めに横になれ。中枢神経の回復には横になっての静的休息が効く」
志水が、いつものように冷めた声で付け加える。
「眠れないなら、目だけでも閉じてください。拒否は無効です」
九条は軽く息を吐いて、スポーツドリンクのボトルをテーブルに置いた。
「……お前たちは甘やかすのが上手いな」
「壊されたら困りますから」
神崎も、志水も、それだけ言って離れていった。
澪からメッセージ
軽くストレッチを済ませ、プロテイン入りのスムージーを手にランチスペースへ移動した九条は、テーブルの隅にiPhoneを置いて画面を確認した。
未読のiMessageがひとつ。
差出人は澪。
帰ったら、お知らせがございます
その一文を目にした瞬間、自然と眉が動いた。
なんだそれは。
良い知らせか悪い知らせかも書かれていない。
少しだけ間を置いてから、短く返す。
良い知らせか悪い知らせか、どっちだ
返事はすぐに届いた。
わかんない。それも踏まえて、ちょっと相談というか。帰ってから話すよ
……わからない?
なんだそれは。
練習後の疲労がじわりと残るこのタイミングで、“わからない”などという返答は混乱を招く。
カップを置き、静かにため息をつく。
澪の言い回しは曖昧だが、本人なりに悩んでいるのは伝わってくる。
だったら、今詮索するより、帰宅後に直接聞いた方が早い――そう判断するまでに、3秒かかった。
帰ってから聞く
何らかの外的要因
(……想定より動けている)
午前は低酸素で走り込んだ。
午後は時雨との打ち合いに、マシンを加えた2:1の実戦ラリー。
負荷は十分。むしろ、オーバー気味だ。
(通常なら、もう少し重さが出てもいい)
疲労はある。呼吸も上がっている。
だが、動作に粘りがある。戻りが早い。
集中が途切れていない。
……理由は不明。
ただ、思い当たるのは一つだけだ。
(昨夜、澪と一緒にいた)
会話をした。肌に触れた。
何かをしたか、していないかではなく――
同じ空間にいたという事実。それだけで違う。
(……眠りの質が違う)
感覚的なものだ。証明はできない。
だが、あいつと過ごした夜の翌朝は、身体が違う。
神経の張りが緩み、過緊張が抜けている。
(無自覚のうちに、力を抜かれているのか)
理屈では説明できないが、結果として、動けている。
なら、それがすべてだ。
──
「何故か、練習の内容の割には疲労があまり溜まってませんね」
神崎が、タブレットを確認しながらぽつりと言う。
志水も、静かにうなずいた。
「やっぱり日本人なので、日本の土地や食べ物が体質に合っているんでしょうか?」
「……それもあるだろうが。もしかすると、何か別の外的要因があるのかもしれない。精神的なものか」
視線の先にいるのは、淡々と打ち返し続ける男。
冷静で、余計な感情を持たぬように見えるその背に、何かが変わった痕跡をふと感じ取る。
「何にせよ、悪い変化ではなさそうですね」
「そうだな。今は、見守るだけでいい」
2対1
時雨の放つ重く鋭いトップスピンを正確に返球しながら、九条は反対側から飛んでくる球にも対応していた。
蓮見がマシンの設定を切り替え、ランダムに球種とコースを変える。
「返せるようにはするが、球種はランダムだ。走らせることが目的だから、カッコつけてないでナダル並みの食いつき見せろよー」
軽口とは裏腹に、放たれる球はコートの四隅を鋭く突く。スライス、キックサーブ、ドロップ、左右に揺さぶる高速ショット――
見ているだけでも、心拍数が上がりそうなラリーだった。
少し離れた位置で、その光景を見ていたレオンが、ぽつりと漏らす。
「……あの人、口調は軽いけど、ドSですよね」
隣に立っていた氷川が、特に表情を変えずに応じる。
「そうでなければ、九条雅臣のコーチはできません」
「選手が自分にも周りにもドSだもんね。……彼女以外(小声)」
「それ、他の人に言わないでくださいね。特に蓮見には。揶揄われるのが嫌で知られたくないかと」
レオンは声を殺して笑いながら、そっと前髪をかき上げた。
「10代の時から見てるから、息子に彼女ができたみたいでいじりたくなっちゃうんじゃないですか?」
「反発されるやつですね」
「それもまた、かわいい」
氷川は何も返さなかったが、どこか目元が柔らかくなったように見えた。
レオンが笑いを堪えながら、横目で氷川を見た。
「氷川さん、一緒にイギリス行ったんですよね? 二人のやりとり、面白くありません?」
氷川は無表情のまま、しかし間髪入れずに返す。
「何度か吹き出しかけました」
「めっちゃ笑ってるじゃん、それ」
レオンが突っ込むと、氷川はほんのわずかに口角を動かし、
「気付かれないように努力はしましたが」
と、しれっと言った。
「無理でしょ。絶対バレてますよ」
「……彼女の言動が予想を越えてくることが多いので」
「でしょー? あれは反則ですよ」
二人は遠くで真剣にラリーを続ける九条を横目に、トーンを落としつつ、ささやかな“裏方の楽しみ”を共有していた。
レオンと氷川の会話が一段落したときだった。
ふと、視線の先――ラリーの合間に九条がこちらを一瞥した気がして、二人は揃って小さく肩をすくめた。
「……今の、聞こえてないですよね?」
レオンが囁くように問うと、氷川は腕を組んだまま、淡々と返す。
「流石にこの距離で聞こえはしないでしょう」
「でも、あの目……完全に“聞いたぞ”って感じでしたよ」
「……いつの間にか、口の動きで何の話してるか読めるようになったんでしょうか」
「あり得ないでしょ、それは――」
言いかけて、レオンは口をつぐむ。
「……いや、あの人なら、やりかねないと思えてしまうのが怖いですね」
氷川の言葉に、レオンは思わず苦笑いを浮かべた。
「チーム九条って、つくづく油断できないですよね……」
「ええ、特に“あの人”の周りを支えるチームなので」
そう言って、二人は黙ってラリーを続ける九条の背中を見つめた。
そこには、言葉にしなくても“伝わってしまう”支配者の気配があった。




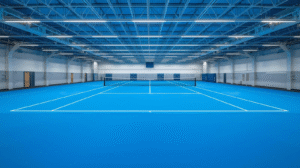



コメント