事後報告
レオンがキッチンから顔を出す。
「澪さん、明日も出勤?」
「んーん、リモート!」
澪はピースして笑う。
「夜は空港まで自分で行くから、待ち合わせで!」
「……あ、そうだ」
レオンが何かを思い出したように声を上げた。
「九条さん、チームメンバー全員と一緒に行くこと、澪さんに伝えた?」
「いや」
九条はごく自然に答える。
澪、一時停止。
「……え?」
完全に止まった空気の中で、レオンが「あ〜〜〜」と気まずそうに眉を寄せた。
「チームメンバーって……雅臣さんのチームの人、全員ってこと?」
「そうだ。イギリスから、そのままドバイ入りする」
「え、ちょっと待って。それって、いつ決まったの?」
「今朝だ」
「……え!? 連絡してよ!」
「してもしなくても、決定事項は変わらない」
「いやいや、こっちの“心の準備”が変わるの!!」
「……今、言った」
「それたまたまじゃん!レオンさんが言わなかったら、私、明日の夜にびっくりするやつだったよね!?」
澪が信じられないという顔で詰め寄ると、九条は一瞬だけ視線を逸らし――そのまま何事もなかったように椅子に深く腰を下ろした。
「問題はない」
「いやあるから!そもそもさ、チームメンバーって何人なの!?誰がいるの!?」
「レオン、氷川、藤代、蓮見、志水、早瀬、神崎」
「めっちゃいるじゃん!!後半の4人知らないし!!どんな役割の人!?」
「蓮見はコーチなのは覚えてるか?」
「それは大丈夫」
「志水がトレーナー、早瀬は理学療法士、神崎はドクターだ」
「……うわ、やっぱり。めっちゃプロ集団……。で、雅臣さん、通訳の人いないの?」
「必要ない」
「いやいやいや、いろんな国行くのに通訳なしって……え、何語喋れるの?」
「日常会話程度も含むなら、英語、フランス語、ドイツ語、中国語……」
「いやどんだけやねん!」
思わず関西弁で突っ込んだ。
「…初めて聞いた」
「…通訳なしで行くとかすごすぎでしょ。ていうか、私、初対面の人4人もいるんだけど?自己紹介とか、ちゃんとしたほうがいいよね?」
九条は少し考えたような素振りを見せて、静かに言った。
「お前は黙って座っていればいい」
「そんなわけにいかないでしょ!どんな鋼メンタルよ!」
「お前ならできる」
「いや、普通に挨拶するわ!」
思わず声を張り上げた澪に、レオンが笑いを堪えきれずに吹き出した。
「はは、いいなあそのやりとり。こういうの、久しぶりに見たかも」
「え、何が?」
「九条さんが“フォローしない前提”で話してるの、安心感あるというか。うちらの時もそうだったから、懐かしいなって」
「フォローしないことをデフォにしないで!?リーダーでしょ?」
澪の声に、九条は微動だにしない。
「うちに上下関係はない」
「はい、絶対嘘」
「本当だ。上司も部下もない」
「って言いつつ絶対反論を許さない空気出すじゃん」
九条は無言のまま、ふと視線を澪に向けた。
「……」
「自覚あるんかい!!」
勢いよくツッコんだ澪の声に、レオンが肩を揺らして笑う。
「ね、そういうとこなのよ。慣れると居心地いいんだけど、最初はみんなそう思うんだよねー」
「みんな!?やっぱりみんな思ってたの!?」
「うん。最初は“やばい独裁者がいる”ってなるけど、だんだん“この人が一番疲れてる”って分かるから」
「フォローしてんのかディスってんのか分かんない…。ちょっと気になったんだけど…その中に女性いる?」
「いない」
九条、即答。きっぱり。
レオンが申し訳なさそうに笑って補足する。
「ごめんねー、男ばっかりでむさ苦しくて。でも、女の子がいてくれると空気が和らぐよね」
「いやいや、私そんな“学園のアイドル”みたいなポジション取れないから」
「取らなくていい。求めてない」
「それはそれでショックだからね!?」
「…そうなのか?」
九条が素で首を傾げる。
どうやら、本気で意外だったらしい。
「“お前には学園のアイドルは無理”って言われてるようなもんだから、それ」
「…だから好きなんだが…」
「ちょっ、やめて!天然で急に告白しないで!?心臓ついて来れないから!!」
澪がソファの上に崩れ落ちるように突っ伏した。
レオンは笑いながら、「そのテンポでくるのずるいよねー」と苦笑していた。
「誰にでも愛想がいい奴は好きじゃない」
ぽつりと落ちたその一言に、澪は思わずソファに突っ伏したまま動きを止めた。
上から見下ろす九条に、悪気は一切ない。ただ事実を述べただけ。
「そりゃ私の愛想はめちゃくちゃ偏ってますけども…」
顔をソファに埋めたまま、ややくぐもった声で澪がぼやく。
「お前の偏り方は極端だ。俺には過剰で、他人にはゼロだ」
「それ褒めてるの?それとも偏りすぎてやばいって話?」
「褒めてる。都合がいい」
「都合がいいって言うな!!」
澪がバッと顔を上げて抗議の声を上げた。頬がちょっと赤い。
怒ってるはずなのに、目が笑ってる。
「自分でも思ってるんだから、あんまり堂々と言わないでよ……!」
「だが、そうだろう?」
「ぐぬぬ……」
否定できないのが悔しい。悔しいけど、ほんのちょっと、嬉しい。
九条はと言えば、無表情のまま澪を見下ろしている。その目は穏やかで、少しだけ緩んでいた。
「お前のそういうところが、好きなんだが」
「……あーーー!!!」
澪は再びソファに顔を埋めて、全力でジタバタした。
「っていうか、他人への愛想がゼロって何でわかるの!?」
澪が上体を起こして、ソファの背もたれに肘をつく。ちょっと必死。
「勘だ」
即答。
「鋭すぎでしょ!野生動物か!!」
「当たってるだろ」
そのまっすぐな目に射抜かれて、澪は言葉を飲んだ。
「……」
図星だった。
なぜか心の奥のほうまで見透かされたような気がして、反論する気力が抜けた。
「お前、基本的に知らない人には目も合わせない」
「それは……タイミングと気分による!」
「言い訳だ」
「ぐぬぬ……」
再びソファに倒れ込む澪の背中を、九条の視線が静かに追っていた。
「……仕事の時はちゃんとしてるもん」
澪が、ソファのクッション越しにむくれたように言う。
「客に対してはな。プライベートでは、無闇に他人に愛想よくしたりしない」
「……」
図星すぎて、言葉が出ない。
同僚でも、嫌いなタイプにはそれなりの温度しか出せないのは、たしかに自覚している。
「だが、信じた相手には尽くす」
九条は何の感情も込めないような声で言ったのに、その言葉だけはまっすぐ心に入ってくる。
「……そんなに尽くしてないし」
そっぽを向きながら答える澪の耳が、ほんのり赤くなっている。
「尽くしてないと、自分では思ってるだけだ」
その言い方がまた、自然すぎてずるい。評価でも賛美でもなく、ただの“事実”としてそう言うから。
思わず目をそらしたまま、唇を噛んだ。
朝のお見送り
朝。
九条が練習に出る準備を終えて、エレベーター前に立つ。
澪は見送りのために、スリッパを鳴らして近付いた。
「いってらっしゃい。また夜にね」
そう言って、軽く背伸びをして、九条の頬にキス。
その瞬間。
九条の目が、すっと細くなる。
――あ、まずい。
と思ったときには遅かった。
九条の腕が、腰を逃がさぬようにしっかりと回されて、唇を奪われていた。
「っ……ん……」
それだけじゃ足りない、と言わんばかりに、唇を重ねたキスは深く、長い。
息ができなくなるほどのキス。
一瞬のつもりでかけた言葉が、彼の“スイッチ”を押してしまった。
深く唇を奪ったあと、九条は名残惜しそうに澪の肩に額を寄せる。
そして、ぽつりと。
「……夜、二人ならよかったのにな」
その一言が、朝の空気にじんわりと広がる。
「……ちょ、朝から何言ってんの」
澪が慌てて言い返すけど、声がうわずっている。
九条はそれに応えることなく、ただ一言。
「物足りない」
淡々と、まるで天気の話でもするように。
そのまま離れ際、背中越しにもう一言。
「機内で寝ておけよ。着いてから我慢できる気がしない」
「馬鹿」
それでも口元はゆるんでいて、澪は少しだけ、照れくさそうに笑う。
「行ってらっしゃい」
クッキー作り
そして今、澪はキッチンに立っている。
今日――2月14日、バレンタインデー。
以前、スーパーで一緒に買い物をしたときに交わした約束を、澪はちゃんと覚えていた。
「作るって言ったからには、作る」
昨日、「尽くしてない」とか言っておいてこれだ。
自分でも笑えるけど、約束は破れない。
澪はそういう女だ。
作るのは、自分のオリジナルレシピのロッククッキー。
見た目は可愛くない。
洗い物が少なくて済むように、ボウルひとつで完結する簡単仕様。
砂糖とバターはギリギリまで減らして、ザクザクした食感重視の大人向け。
しかも今回は、オートミールを混ぜてある。
「少しでも食物繊維を増やした方がいいでしょ」って、誰にも言わないけど、そんな気遣いをしっかり入れ込んだ。
旅行の準備はもう終わってる。
パッキングも済ませて、出発前にシャワーを浴びればいいだけの状態。
自分のことは最低限に。
時間も材料も、今日はぜんぶ“誰かのため”に使ってる。
それを澪は、誰にも言わない。
言わないけど、こうやって――尽くしている。
「別に、尽くしてるわけじゃないし。私も食べたいし」
自分に言い訳しながら、澪は無心で生地をこねる。
ボウルに入っているのは、小麦粉300g。九条が高級スーパーで「これ」と選んだ、なんかお高いやつだ。バターは1箱の半分、包丁でばすっと真ん中から切って、サイコロ状に。卵も、黄身が濃いオレンジ色をした栄養価高そうなやつ。砂糖はザクザクした食感を出すためにグラニュー糖を使って、80g。減らせるけど、それ以上減らすと甘みが足りない。食べられるけど、物足りない。オートミールも、九条が買った砂糖不使用の“意識高いやつ”を食感程度に混ぜる。生地がまとまるくらいで十分。
焼き上がる頃には部屋に甘い香りが満ちていて、なんだかんだで、澪は嬉しそうにしている。
──昨日、「尽くしてない」って言ったくせに。
でもこういうのは、なんか約束だし。バレンタインにクッキーを作る、って自分で言ったし。彼も楽しみにしてる…たぶん。
だから別に、尽くしてるんじゃなくて、ちゃんと約束を守ってるだけ。それに、どうせ自分も食べるし。
「ちょっと見た目可愛くなさ過ぎるかなぁ…」
そう呟きながら、スプーンで天板に落としていく。丸めず、あえてごつごつした岩のような形にした。
「でもこの形の方が美味しいんだよな。あんまりこの手のクッキー売ってないし、こういうのは手作りの特権でしょ」
九条のリクエストで、ナッツ入りもいくつか作った。ローストしたアーモンドを粗く刻んで、ごつごつしたクッキーの中に混ぜ込む。
焼き上がりは、まさに理想のロッククッキー。ザクザクで、でも中はしっとり。ナッツの香ばしさもちゃんと出ている。
「……うん、悪くない」
“尽くしてない”って言いながら、ちゃんと量も多めに作ってるあたり、もう言い訳になってない。
でもまあいい。
夜、空港で渡せばいい。
焼きたて
「焼きたてが食べられるのは作った人の特権だよねー♪」
小さくガッツポーズしながら、ザクザクのクッキーをひとつ摘んで、ぱくりと口に入れる。香ばしい香りと、まだ少し柔らかい食感がたまらない。焼きたては格別だ。
――と、そのとき。
テーブルの上でスマホが震えた。
「うわっ…なんで今…!?」
表示された名前は「九条雅臣」。
まさかこのタイミングでかけてくるなんて。慌てて口の中のクッキーを一気に飲み込んで、咳き込みそうになりながら通話ボタンを押す。
「…はい?もしもし」
『……何食べてる』
「えっ、なんで分かるの!?怖っ!」
『お前はいつも何か食べてる』
「それ、人としてどうなのって言い方しないで!?一日中もぐもぐしてるわけじゃないんだから!」
『で?』
「……クッキー。焼いたから、焼きたて食べてる」
ちょっと照れくさくて、語尾がしぼんだ。
電話の向こうからはすぐに返事が来ない。でも九条は、確かに覚えていた。
――“バレンタインにクッキー作る”
って澪が言ったこと。
それと同時に、澪が「会社に持って行くと、結構好評」と言ったのも。
“男にも配ってるのか?”と、ひそかにムッとしたことも。
「いっぱい焼いたから、雅臣さんの分もあるからね」
キッチンに立ったまま、スマホ越しにそう伝える。焼きあがったばかりのクッキーからは、バターと砂糖の甘い香りが部屋中に広がっていた。
「見た目は可愛くないけど。部屋の中めっちゃバターの甘い匂いする」
『……夜、持って来い』
「そのつもり」
『潰すなよ』
「ロッククッキーだから潰れないよ。少しは割れるかも?密閉できる容器で持ってく?」
『ああ』
九条の返事は、いつも通り簡潔だ。けれどそのやり取りの中に、ちゃんと“待ってる”という意思がにじんでいるのが、もう分かってしまう。
「なんか、全然可愛いラッピングとかしてなくてごめん。バレンタインなのに」
少し申し訳なさそうに言うと、九条はすぐに返した。
『外側の飾りには興味がない』
「うわ、らしいわ……」
苦笑しながらも、なんだかんだでその“らしさ”が嬉しかった。
「カメラで映せ」
「え、今? 恥ずかしいんだけど」
スマホ越しの九条の声に、澪は思わず眉をひそめる。
「どうせ後で見る」
「そうだけどさ……ほんとに可愛くないよ? 味は美味しい」
そう言いながら、スマホのカメラを外側に切り替えて、
皿に盛ったロッククッキーを映す。形は不揃い、でも焼き色は香ばしく、
アーモンドとオートミールが混ざったゴツゴツとしたそれは、まさに「ロック」だった。
「一口で食べられるサイズにしてます。こぼさないように」
そう説明しながら、カメラのフレーム内に自分の指先も映る。
自分がつまんで食べるために作ったサイズ――当然、九条もそのくらいで食べられる。
『お前らしいな』
電話越しに聞こえたその言葉に、澪は少し引きつった笑みを浮かべた。
「……不器用そうって意味?」
一応、澪なりに形を整えたつもりではある。
不器用というほどでもない。物作りは好きな方だ。
けれど、九条は少しの間をおいてから静かに言った。
『力強くて、形が歪。でも、香りが甘い』
まるで、澪の心そのものみたいだ――そう言われたような気がした。
作業効率を重視して洗い物を減らし、
甘さも控えめに、だけどちゃんと美味しく。
合理的だけど、愛情がにじむ。
「……あのね、そういう言い方やめて? 嬉しいけど、恥ずかしいんだけど」
照れ隠しでそう言うと、電話の向こうで少しだけ息を吐くような音がした。
『今夜、食べるのが楽しみだ』
それだけ言って、通話は切れた。
ラッピング
密閉できる袋にロッククッキーを詰めながら、澪は少し考える。
「……このままだと、さすがに味気ないよね……一応バレンタインだし……」
引き出しの奥から、以前買っておいたラッピング用の袋とタグ、そしてシンプルなリボンを取り出す。
どれも100均のものだけど、ちゃんと「バレンタインっぽさ」はある。くまのワンポイントがついたタグとか、
落ち着いた色合いのワックスペーパーとか。甘すぎない、でもさりげなく可愛い。
「気合い入れすぎて引かれるのも嫌だし、かといって何もなしはそれはそれでなぁ……」
ぶつぶつ言いながら、袋の中の空気を抜いてクリップで留め、タグを結ぶ。
ラッピングが終わって、ふぅ、と一息。
「……まあ、いいよね。どうせ中身で勝負だし」
なんて言いながらも――
それを差し出す時の九条の反応を、ほんの少しだけ、期待してしまっている自分がいた。
「絶対ピンクとかハートとか好きじゃなさそうだし、持ってても似合わないし……」
なんてひどいことを思いながらも――
実際、真っ赤なハート柄の袋を九条が手にしている姿は、どうにも想像できない。
けれど、せっかくのバレンタイン。
だから澪は、濃紺に金のアクセントが入ったシンプルな袋を選んだ。ほんの少しだけ、縁にくまの小さなワンポイントがある。言われなければ気づかない程度の可愛さ。
「これくらいなら…バレない可愛さでいける」
くまのタグをつけながら、自分で笑ってしまう。
「私ってば、どんだけ気ぃ使ってんの……」
袋詰めが終わった後、クッキーの入った密閉袋を見つめながら、澪は小さくつぶやいた。
「渡すとこ見られるの恥ずかしいから、雅臣さんにこっそり渡そ」
誰に言うでもなく、ただ自分に言い聞かせるみたいに。
イベントを祝うタイプじゃないし、派手な演出も似合わない。
けど、彼にだけは――特別なものを、ちゃんと届けたい。
“ありがとう”とか“好き”とか、言わなくても、伝わるように。



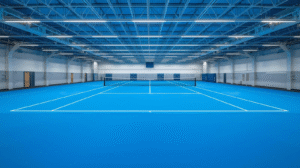




コメント