夕陽が沈みかけた頃、センターコートはようやく静けさを取り戻していた。
試合の熱気はすでに消え、観客も報道陣も去った後。
そこに残されていたのは、コート脇の一脚のベンチだけだった。
乾いた風が、青いベンチの表面を撫でていく。
さきほどまで、そこに“王”がいた。
だが、彼の背中はすでにコートを離れ、記憶だけが残っている。
プレー中、彼は何も語らなかった。
勝っても、拳を握ることなく。
サーブも、ウィナーも、ラリーすらも、すべて無表情のまま淡々と処理されていった。
実況が語った「人間かどうか疑うレベルの精度」は、ベンチにも静かに染み込んでいた。
——このベンチには、汗も、疲労も、安堵も残されていない。
ただ、“存在の跡”だけが、空気に滲んでいた。
誰もそこに座らない。誰も音を立てない。
まるでこの場所が、“まだ試合中”であるかのように。
それほどまでに完璧で、
それほどまでに“他者を排していた”。
そして、この異常なまでの静寂は、
彼が勝者であることを、誰よりも雄弁に語っていた。
——だがそれは、あまりに孤独な勝利でもあった。



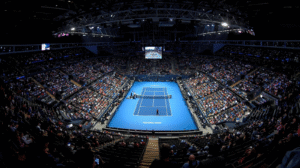

コメント