起動前確認 / Pre-Boot Check
九条雅臣は、コート入り直前の控室で、スマートフォンを手にしていた。
着替えも、テーピングも、すでに完了している。
あとはただ、呼ばれるのを待つだけ。
画面を開く。iMessage。
そのまま数秒、何かを考えていた。
それから、静かに入力を始める。
ためらいも迷いもなく、ただ“そうすると決めた”速度で。
送信。
画面を伏せ、スマホを静かにケースへ戻す。
まるで何事もなかったかのような手の動きで。
その直後。
「Kujo, ready.」
ドアの向こうから、スタッフの声。
九条は立ち上がる。
もう再起動は終わっていた。
【第1ゲーム】初期化完了 / Boot Complete
コートに立った瞬間、
九条雅臣の姿勢には、余白がなかった。
歩幅、視線、呼吸。
すべてが最適解で構成された“動作の集合体”。
観客席の喧騒も、風の流れも、ノイズに分類される。
無視する必要すらない。処理対象にすらならない。
初期化は完了した。
いまコートに立っているのは、“人”ではない。
試合開始の合図。
ボールを受け取り、静かに構えた。
その瞬間——
空間が一つ、切り取られたように感じられた。
打球音が、ひときわ鋭く響く。
サービスエース。
ワンバウンドもせず、ラインぎりぎりに突き刺さる。
対戦相手の動きは、ほんの少しだけ遅れていた。
——否。遅れたのではない。
追いつけるという前提が、はじめから存在しなかった。
スコア、1-0。
機械が、最初の出力を完了させた。
【第2ゲーム】初期誤差補正 / Input Adjustment
2ゲーム目。
ようやく対戦相手が、反応を見せ始めた。
——遅すぎた。
最初のラリー。
九条のリターンに対して、相手は角度のあるクロスを選んだ。
軌道は悪くない。タイミングもそこそこ合っていた。
だが、その「そこそこ」を、九条の演算は許容しない。
すぐさま足元に沈める低弾道の逆クロス。
それを拾わせた直後、
ネット前に落ちるフェイクを含んだドロップ体勢——
からの、フルスイング。
ロブを予期して下がった相手の裏をかき、
強烈なトップスピンショットがサイドラインを抜いた。
スタンドがざわめく。
その球には、“予測不能”の要素が含まれていた。
いいや、違う。
予測不能ではない。
「対戦相手だけが、予測できなかった」だけだ。
九条の中では、初期誤差はすでに補正済み。
試合は、もはや最適解の上で進んでいる。
スコア、2-0。
処理速度が、さらに上がっていく。
【第3ゲーム】同期干渉 / Synchronization Disrupt
わずかに、タイミングが噛み合った。
ラリーが続いたのは、初めてだった。
観客席には小さな拍手が起きる。
「ようやく試合になってきた」
——そんな空気が、一瞬だけ流れた。
だが、それは“試合になった”のではない。
“誤差が生じた”のだ。
九条の足元。
コートとシューズの摩擦が、1ポイントだけ乱れた。
スピンの収束がわずかに狂い、ボールは想定より浅くなった。
その瞬間、対戦相手のラケットがしなる。
フォアのクロス。
狙いは完璧だった。
——ライン際。
ボールは、九条の目前をかすめて抜けた。
コールは「イン」。
1ポイント。
たったそれだけの取得が、会場の空気をわずかに変える。
そして九条は、無言のまま次のサーブ位置に移動した。
顔色も変えず、視線すら動かさない。
同期? 干渉?
違う。
演算に不要な信号が、ただ一度だけ割り込んだにすぎない。
スコア、2–1。
ノイズの発生。
しかし、それもまた演算の一部だった。
軸ズレ感知。スニーカー接地圧、わずかに乱れました。
表面温度、数値微妙に変化してる。
調整入りましたね。次、整うはず。
【第4ゲーム】演算補正開始 / Correction Protocol
次のゲーム、九条はサーブから始めた。
動きに迷いはない。
さっきまでと、何一つ変わっていないように見える。
だが、それこそが“補正”だった。
フォームの角度。
打点の位置。
サービス後の重心移動。
——全てが、前ゲームで生じたノイズに対応して再調整されていた。
1ポイント目、ワイドへのサービスエース。
2ポイント目、スライスを混ぜて時間差を生み、バックに沈める。
3ポイント目、相手が食らいついたリターンを前で処理し、ドロップショット。
そして、4ポイント目は——
無音。
九条の動きに、観客すら音を忘れる。
サーブから決着まで、打球音が4回しかなかった。
スコア、3–1。
誤差は補正された。
演算は、最初の形に戻りつつある。
【第5ゲーム】振動抑制 / Vibration Suppression
揺れが、なくなっていく。
対戦相手は、まだ諦めていなかった。
意図を持った配球、ポジショニング、緩急の変化。
それらは確かに“作戦”として機能していた。
しかし、九条雅臣の目は、
その全てを「ノイズ」として処理していた。
リターンに少し高さを出せば、即座に足元へ落とされる。
打点をずらせば、時間差のリカバリーを読まれる。
粘ろうとすればするほど、足が削られていく。
それはまるで、振動を吸収する制御装置のようだった。
ベースラインから決して外れない動き。
反応ではなく、予測による静止。
ラリーの末、相手が先に崩れた。
ボールがネットにかかる。
打ち終えた相手が、肩で息をしていた。
スコア、4–1。
九条は、一度も呼吸を乱していない。
【第6ゲーム】反射率制御 / Reflectivity Control
ボールが跳ね返ってくる。
だがそれは、偶然の産物ではない。
——すべて、想定内。
九条は今、相手のスイングに込められたわずかな力の向きを、
物理現象として計算している。
打点の高さ。
ラケット面の角度。
足の重心移動と、それによる球の初速変化。
それらを観察するのではなく、演算によって“予測”する。
結果——
リターンは来る前に処理される。
球が跳ねる前に、彼のラケットはすでに“そこにある”。
観客席では、一部のコーチ陣が首を傾げ始めていた。
「読みじゃない」
「反応じゃない」
「これは……」
言葉にならない違和感が、周囲に波のように広がっていく。
スコア、5–1。
跳ね返りの予測精度、100%。
演算領域は、センターからコーナーまで拡張されていた。
【第7ゲーム】出力ゆらぎ / Output Drift
わずかに、軌道がズレた。
それは、目視では判別できないほどの誤差だった。
だが、精密に制御されたシステムにおいては——
たった数センチが、結果を決定づける。
1ポイント目、スライスで時間を稼いだ相手が、ドロップショットを仕掛けてきた。
九条は走り込む。
届く距離。届くはずの動き。
だが——
ほんの一瞬、ステップが地面を噛み損ねた。
ラケットは触れた。
だが角度がわずかにズレて、ボールはネットを越えなかった。
「くずれた?」
観客席で誰かが呟く。
違う。
崩れたのではない。
出力が乱れただけだ。
その後も、相手は意図的に“ラリーを崩す球”を織り交ぜてきた。
リズムのない展開。
断続的な打ち合い。
「演算が及ばない“ゆらぎ”」を狙うプレー。
……そして、それが一度だけ成功した。
スコア、5–2。
出力に生じたゆらぎ。
だが、その揺れすら、次の制御に取り込まれていく。
呼吸リズムは安定。温度上昇、許容範囲内。
反応処理に一時的な遊びが出てました。
見た目以上に落ち着いてます。
【第8ゲーム】安定状態到達 / Stable Mode Achieved
乱れは、もうない。
九条雅臣の動きに、
「次に何をするか」が存在しない。
すでにすべては“決定済み”の演算として組み上がっていた。
観客が静かになっていた。
感情ではなく、理解が追いつかないからだった。
何が起きているのか説明できないまま、
ただ“そうなるとしか言えない”得点が続く。
1ポイント。
2ポイント。
3ポイント。
——そして、最後の1球。
相手の打球を、九条はわずかに後ろへ下がりながら処理した。
その動きに、焦りも攻撃性もなかった。
むしろ、“終わらせるための動き”。
低く沈んだショットが、ネットの手前で2度バウンドする。
ゲームセット。
スコア、6–2。
安定状態に到達。
もはや修正は不要。
これが、“解析開始”の第1セット、完了形。


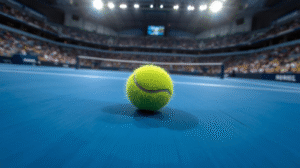
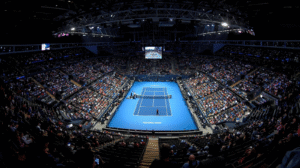

コメント