【第1ゲーム】処理速度上昇 / Processing Boost
第2セット、開始。
九条雅臣は、左の手首を軽くひねるだけで、
ラケットの角度を変えた。
ほんのわずかな回転。
けれど、それがコート上では“方向性の切り替え”に等しい。
最初のサーブ。
ワイドにえぐる左利きのスライス。
相手のバックハンド側ギリギリを狙って、外へ逃げる軌道。
——ノータッチエース。
2ポイント目。
リターンを受け止めた直後、左足を軸に逆クロスへ展開。
タイミングが1拍、早い。
相手の反応が遅れているのではない。
処理速度が追いついていないのだ。
3ポイント目、4ポイント目も同様。
サーブ、ラリー、フィニッシュまで、
全てが「判断の前に完了」している。
わずか数分でゲームが終わった。
拍手も、どこか追いつかない。
スコア、1–0。
処理速度は、まだ上がる。
【第2ゲーム】テンポ撹乱 / Tempo Distortion
九条の動きが、わずかに“遅く”なった。
……ように、見えた。
リターンの構えがいつもより半テンポ遅れたことで、
相手は一瞬だけ“攻めの隙”を感じる。
ドロップを混ぜるか、ワイドへ走らせるか。
選択肢が浮かび、その判断がほんの数秒、脳内を往復した。
——その一瞬が罠だった。
九条は次の瞬間、ラリーのテンポを倍速へ引き上げる。
左利き特有の逆クロスで、角度をつけて崩し、
浅い球には前進してネットへ詰める。
相手は、予測できないのではない。
“テンポに置いていかれている”のだ。
ゲーム終盤には、相手のフットワークがわずかに乱れはじめていた。
まだ追えてはいる。
でも、その“追えている”ことが、逆に負担を増やしていく。
スコア、2–0。
テンポは、もう九条の手の中にある。
【第3ゲーム】データ同期化 / Data Alignment
同じ場所に打ってくる。
同じテンポで返してくる。
同じ球質が、同じリズムで返される。
……相手にとっては、それが異常だった。
ラリーが続くほど、
「この状況、さっきも見た」と思う瞬間が増えていく。
そして、それは事実だった。
——九条雅臣は、状況を記憶し、再構築している。
ボールの弾道。
相手の足の出方。
汗の飛び方まで含めて、状況を“再現”してくる。
リターンAに対しては処理パターンB。
クロス展開には、0.3秒後の逆モーションC。
そのデータが、九条の中ではすでに同期済みだった。
2ポイント連続で、まったく同じ軌道のラリーから、
同じカウンターでポイントが決まる。
相手の表情が、明らかに戸惑いに変わっていた。
スコア、3–0。
再現性100%。
人間の変数は、もう収束し始めていた。
【第4ゲーム】応答抑制 / Response Suppression
返す前に、終わっていた。
打つ構えを見せる前に、もう打たれている。
ラリーが始まる前に、もう終点が定まっている。
それが、このゲームの全てだった。
1ポイント目。
ワイドに振られた直後、逆クロスへ切り返された相手は、
打つべき球に“ラケットを出す暇すらなかった”。
2ポイント目。
ドロップ気味の緩急ショットから、急角度のトップスピン。
一歩動いた瞬間には、球はもうバウンドを終えていた。
観客席に座るテニス経験者ほど、
この異常な支配を正確に理解していた。
「反応できてない」
「いや、反応する前に終わってる」
「処理が……速すぎる……」
ただ打ち合っているのではない。
“応答という概念”そのものを消されているのだ。
スコア、4–0。
ここにはもう、選択肢という反応装置は存在しない。
映像で見ると“動いてるように見えるだけ”に近い。
九条の球が“全部可能性”になってる。
反応じゃなくて“誘導”されてる形。
【第5ゲーム】高負荷処理 / Overload Handling
演算にも、限界はある。
それは、処理不能ではなく、処理の“集中度”が極端に跳ね上がる瞬間。
このゲームがまさにそれだった。
対戦相手は、あきらめていなかった。
むしろ、ここが勝負だと読んでいた。
ボールに緩急を。
スピンに縦回転を加え、落差を強調する。
左右に散らす配球に加えて、前後の差も大きくとる。
——九条の演算範囲が、限界まで広げられていく。
処理できてはいる。
だが、そのたびに数パーセントずつ演算負荷が上がっていく。
走り出す前に次の地点を計算する、その精度にヒビが入る直前。
4ポイント目、フルラリーの末、
対戦相手のロブが九条の頭上を越えて落ちた。
走るか——否。
判断が、一瞬だけ遅れた。
球は、ラインぎりぎり。
イン。
会場がざわめく。
ベンチに戻る相手の表情には、苦しさと達成感が混ざっていた。
スコア、4–1。
九条の処理装置はまだ壊れていない。
だが、高負荷時のリスクが、確かに一度発生した。
【第6ゲーム】応答誤差 / Delay Detected
遅れている。
反応ではない。
判断でもない。
……処理そのものが、ほんのわずかに遅れていた。
1ポイント目。
相手のトップスピンが、想定より0.1秒早く着弾。
九条のリターンは正確に返るが、角度が浅くなる。
2ポイント目。
スライスを読み切ったはずの足運びが、半拍ずれた。
それは“反応の限界”ではなかった。
処理キューが詰まりかけている。
連続演算による、演算順序のスレ。
——応答誤差発生。
だが、九条は止まらない。
むしろ、エラー処理の上書きに入る。
3ポイント目以降、
彼は打球時のリズムを微調整し始めた。
足の重心を下げ、わずかに“待つ”構えを加える。
その結果、出力は数パーセント落ちたが、誤差は収束に向かった。
ロングラリーの末、バックのラインショットが決まる。
スコア、5–1。
遅延は検出された。
だが、補正処理はすでに完了していた。
【第7ゲーム】安全領域逸脱 / Safe Range Breach
走った。
九条が、“本気で走った”。
それは彼にとって、計算された逸脱だった。
今まで一歩で届いていた距離。
だがこの1本は、全力でなければ届かない。
左足から踏み込んだ瞬間、
軸がわずかに外れた。
リカバリーは間に合っていたが、スイングが甘くなる。
ボールはネットを越えた。
だが、深さが足りない。
——甘く浮いた球を、相手が強打。
ラインぎりぎりに沈むショット。
九条、対応できず。
この1ポイントを皮切りに、
相手が再びテンポを乱すプレーを増やしてきた。
変則的な球。
予測しづらい回転。
速度ではなく、読みづらさで勝負をかける展開。
それでも九条は崩れなかった。
……が、このゲームだけは安全領域を越えた代償として、
応答に“ほころび”が現れた。
ゲームを落とす。
スコア、5–2。
だが、逸脱の先で得たデータは、すでに演算に取り込まれていた。
【第8ゲーム】上書き終了 / Overwrite Complete
処理は、完了しつつあった。
さきほどまでの“ズレ”や“逸脱”は、もう記録ではない。
すべてが正規データとして上書きされている。
立ち位置。
打点。
テンポ。
すべてが、初期化済みの演算式に再統合された状態。
1ポイント目、静かに打ち出されたスピンサーブ。
相手のラケットがかろうじて触れ、ネットイン。
2ポイント目、緩急をつけたラリーから、左利き特有の逆クロス。
ライン際に沈み、動けず。
3ポイント目、相手が深く返してきた球を、
一度後ろへ下がってから叩き込む強打。
“安全領域逸脱”のデータが、ここで生かされた。
最後の1球は、極めて静かだった。
ネット前へそっと落としたドロップショット。
相手が走る。
届くか、どうか——
届かない。
スコア、6–2。
第2セット終了。
すべての誤差、乱れ、逸脱は、上書きされた。
演算は止まらない。
九条雅臣、完全同期領域へ突入。
股関節、あえて可動域セーブしたかも。
身体が先に“リスク処理”してる感じ。
許容範囲内で制御できてます。
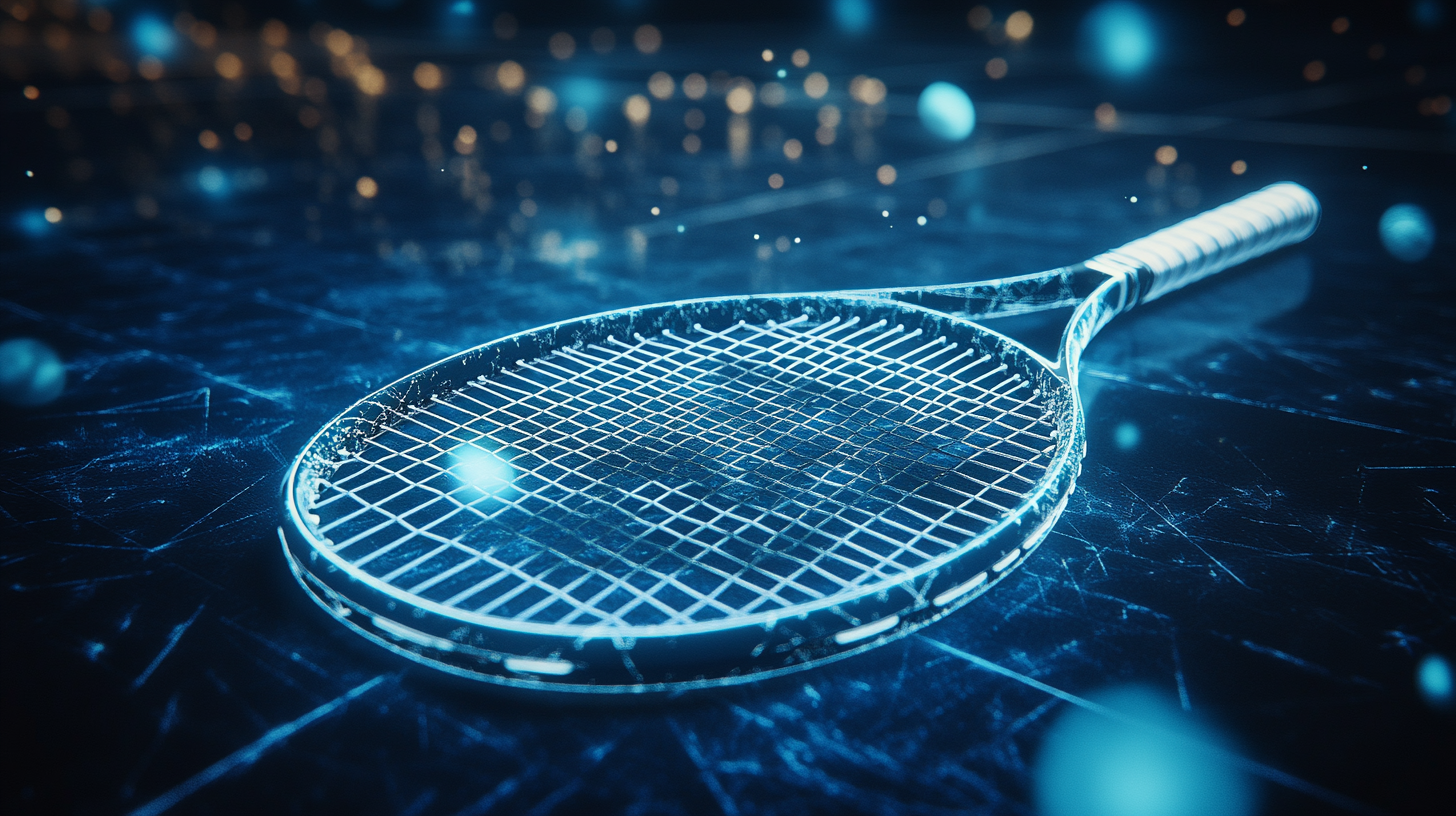





コメント