準々決勝 開始
インディアンウェルズ、準々決勝。
日差しが傾き、スタジアムの空気は熱気とざわめきで満ちていた。
マティアス・ヴォルフ。
背の高い体を折りたたむようにしてベースラインの遥か後ろに立ち、ラケットを軽く揺らしている。
まるで最初から「引き延ばす」ことを前提にした姿勢。
九条はベースラインに立ち、冷たい視線を相手に向けた。
一球ごとに試合を短く終わらせる算段を立てる――そのつもりだった。
第1セット序盤。
九条はいつものように速攻を仕掛けた。サーブから強打へとつなぎ、効率的にポイントを奪うつもりだった。
だが、マティアス・ヴォルフは崩れない。
深く沈むボールを、フェンス近くまで下がっても拾い上げ、無理のないスライスで返す。次の一球も、その次も。
「まだ返すか」
九条の眉がわずかに動いた。
観客席からため息が漏れ、やがて長いラリーに拍手が混じる。
ヴォルフは平然と返球を続け、ラリーの合間にちらりと笑みを浮かべた。
「氷も……時間をかければ、溶ける」
誰に聞かせるでもなく、そんな言葉を吐き捨てる。
九条は聞こえていないふりをした。だが、その声は確実に耳に届いていた。
一瞬の苛立ちがショットに表れ、打球がわずかに甘くなる。
それすらヴォルフは逃さない。粘り続け、さらにラリーを引き延ばしていく。
合理的に、短く終わらせる――九条が信じてきた勝ち筋が、泥のように足を取られていく。
ラリーは続いた。
30回、40回――数えること自体が無意味になるほどに。
九条の足音がコートに乾いた音を刻む。
だがヴォルフは呼吸一つ乱さない。後方に張りつき、ただ「返す」ことに徹している。
観客席からは、ため息混じりのざわめきが広がる。
いつまで続くんだ―― そんな空気が会場を覆った瞬間、ヴォルフの口元がわずかに吊り上がった。
「氷の王も、汗はかくんだな」
皮肉が、ネット越しに落とされる。
九条は聞こえないふりをした。
だが次の一球、僅かに力みが混じる。
強打は放たれたが、コースは甘く、ヴォルフに拾われてしまう。
――合理的に終わらせるはずの試合が、終わらない。
終わらせようとするほど、深みに嵌まっていく。
集中を保つはずの心が、次第にざわめきに浸食される。
時間を稼ぎ、焦らせ、揺さぶる――それがヴォルフの狙いだと分かっていても。
九条は唇を噛み、無言で構え直した。
だがその胸の奥で、微かな苛立ちが確かに脈打っていた。
九条の強打を拾い上げながら、ヴォルフは低い声で吐き捨てる。
「……氷像みたいな顔だな。割れる瞬間を、観客は待ってる」
九条は無言で打ち返す。
だがヴォルフはさらに言葉を重ねる。
「短く終わらせたいんだろう? 無駄だ。ここじゃ、俺が時間そのものだ」
観客席にざわめきが走る。
その声は九条の耳にも届き、苛立ちを煽る。
沼の入り口
観客席から、長いラリーのたびにため息とざわめきが混じった。
「また返したぞ」
「どこまで拾うんだ」
拍手が起こるのは、九条のウィナーではなく、ヴォルフの粘りを称えるものだった。
氷の王にとって、初めての違和感。自分が試合を支配しているはずなのに、会場の空気は相手に傾いている。
ヴォルフは、汗で濡れた前髪を掻き上げながら小さく笑った。
「完璧な氷像も……観客の熱で曇る」
わざと聞こえる声量で言葉を落とす。
周囲がざわめき、九条の耳にもしっかりと届く。
次のラリー。
九条は打ち急いだ。
一球で決めにいく攻め、だがヴォルフはまたも深く返す。
返して、返して――永遠のようなラリーが続く。
苛立ちを悟られまいとする九条の表情は、逆にわずかな強張りを見せていた。
ヴォルフはそれを逃さない。ネット越しに薄い笑みを刻みながら、さらに泥のようなラリーへ引き込んでいく。
熱狂の残響
ラリーはすでに百を越えていた。
九条は一瞬の隙を突いてネットへ出る。
ここで仕留める――そう決めて放ったボレーは鋭く沈んだ。
しかし、ヴォルフのスライドが追いついた。
地を這うようなバックハンドのパスが、ライン際へ突き刺さる。
審判の声が響いた。
「アウト……」ではない。
「ポイント、ヴォルフ」
スタジアムがどっと沸いた。
歓声と拍手、まるで勝負が決まったかのような熱狂。
九条のラケットを握る手に、わずかに力が籠もる。
視線は冷徹なままだが、胸の奥で苛立ちが確かに膨れ上がった。
ヴォルフは肩をすくめ、観客に片手を挙げる。
そしてネット越しに、わざと口を動かす。
「氷も、ひびが入れば脆い」
九条はその言葉を聞かなかったふりをした。
だが耳の奥に残響は焼き付いていた。
内省
――中盤。チェンジエンド。
タオルを頭にかぶり、呼吸を整える九条を横目に、ヴォルフが笑った。
「合理主義……効率主義……そんなものは泥に沈めば終わりだ。
氷は強い。だが、ひびが入れば脆い。お前も同じだ、九条」
彼の声は低く響き、観客席にさえ届く。
審判が睨むが、ヴォルフは気にしない。
「俺は崩れない……崩れるのは、いつも対峙した相手の方だ」
タオルを手に、九条は額から滴る汗を拭った。
呼吸は乱れていない。それでも胸の奥に燻る苛立ちが熱のように広がっている。
ベンチ横に立つ蓮見が、静かに言った。
「……相手の挑発に乗るな。あれはお前のペースを狂わせるために言ってるだけだ」
九条は短く目を伏せ、タオルを膝に置く。
「……わかっている」
わかっている――だが、わかっているからこそ苛立つ。
合理的に、冷徹に試合を支配するはずが、今は自分が“支配される側”に回っている。
観客のざわめきも、ヴォルフの皮肉も、わずかに体内のリズムを乱していた。
水を一口含み、目を閉じる。
思考を切り替えろ――そう自分に言い聞かせながら、九条は無言でラケットを握り直した。
氷の彫像
セット中盤。
再び長いラリーが始まった。
ヴォルフは後方に張り付き、ただ返す。ひたすら返す。
九条は苛立ちを飲み込むように、深く息を吐いた。
さきほどまでは一本で仕留めようと力みすぎていた。
その焦りを、ほんの少しずつ削ぎ落とす。
(終わらせようとするな。点は目の前にある)
自分に言い聞かせ、リズムを整える。
強打に頼らず、淡々とラリーを重ねる。
観客は一見して同じような応酬に見えただろう。
だが九条の中では確実に変化が起きていた。
苛立ちを燃料にするのではなく、冷却材に変える。
相手の狙いは自分の集中を溶かすこと――ならば逆に、時間を凍らせればいい。
ヴォルフのボールを受け止め、深く打ち返す。
「……悪くない」
ネット越しに、相手が皮肉混じりに呟いた。
九条は反応しない。
まるで氷の彫像のように無表情で、次の一球を待っていた。
削る
九条の意識が切り替わった。
“早く終わらせる”のではない。
“徹底的に削る”。
ヴォルフが延々と返球を続けるなら、その返球を受け止め、さらに深く突き返す。
鋭さではなく、正確さで。
冷たい氷が、じわじわと相手の体力を蝕んでいく。
観客は気づき始めていた。
長いラリーは同じに見えて、わずかにリズムが変わっている。
ヴォルフの足取りが重くなり、息が荒くなっていくのがはっきりと分かった。
九条は容赦しなかった。
クロスへ、ダウン・ザ・ラインへ、深く深く打ち分ける。
無言のまま、氷の針を突き立てるように。
ヴォルフはそれでも返した。
だが返すたびに肩が落ち、膝が沈む。
「……チッ」
舌打ちがネット越しに響いた。
九条は表情ひとつ変えず、次の構えを取った。
狙いは決して変わらない。
――削り尽くす。
コードバイオレーション
九条の冷徹なラリーが続く。
ヴォルフは必死に追い、返し続けるが、返すたびに身体から力が抜け落ちていくのが自分でも分かる。
観客席の空気が変わり始めた。
「ヴォルフが押されている……?」
「さっきまで九条の方が苛立っていたのに」
やがて、その変化はヴォルフの表情に現れた。
苦々しい顔でラケットを振り回し、拾ったボールを無造作に叩き返す。
一球、二球――そして九条の深いショットに届かず、ポイントを落とした瞬間。
「クソッ!!」
ヴォルフはラケットを空に放り投げ、苛立ちを隠さなくなった。
会場がざわめく。審判がすぐに「コードバイオレーション」を宣告した。
九条は表情を崩さない。
無言でタオルを取り、額の汗を拭う。
視線は氷のように冷たいまま、ただネットの向こうを見据えていた。
――泥に引きずり込むはずが、いつの間にか自分が氷に閉じ込められている。
それを悟った瞬間、ヴォルフの感情は完全に顔に出ていた。
沼が凍る
ラケットを拾い上げたヴォルフは、なおも自分を奮い立たせるように吠えた。
だが吠える声とは裏腹に、ラリーは乱れ始めていた。
無理に打ち込んだフォアは浅くなり、クロスを狙ったショットはラインを割る。
彼の“粘り”が武器であるはずなのに、その粘りを支える冷静さはもう失われていた。
九条は逃さない。
一球ごとに深く突き刺す。
観客席からはため息と歓声が交互に漏れる。
「ヴォルフ、崩れたぞ!」
「九条のボールが重い……!」
ヴォルフの返球は次第に雑になり、やがてネットにかかる。
審判の声が冷たく響く。
「ゲーム、九条」
スタジアムに大きな拍手が広がった。
ベンチに戻るヴォルフの背は重く沈み、肩で息をしている。
一方の九条は無言でタオルを取り、淡々と汗を拭った。
氷の表情は揺るがない。
――沼は崩れ、氷が支配権を取り戻した。
氷と沼
第2セット。
九条は氷のごとき冷徹さで一点一点を積み重ねていた。
だがヴォルフは沈まない。
後方に張りつき、なおもラリーを伸ばす。
返すたびに、荒い息の奥から低い声が漏れた。
「……まだ終わらん」
観客席がざわめく。
百を越えるラリーの末に、ヴォルフが拾ったボールは辛うじてラインに落ちた。
会場が大きく沸き、スタンドから拍手が送られる。
九条は顔を崩さない。
だがその内心で、わずかに警戒を強めていた。
(しぶとい……)
ヴォルフは、膝に手をついて荒い呼吸を整えながらも、ネット越しに視線を向けてきた。
「氷は強い……だが、溶けるまで俺は諦めん」
次のゲームも、ヴォルフは崩れかけながらも拾い続けた。
滑るように伸ばしたラケットの先で、なおもボールを返す。
その姿に、観客は立ち上がり、拍手と声援を送った。
九条はタオルを握り直し、額の汗を拭った。
(沈め。……沈むまで、削り尽くす)
氷と沼。
二つの執念がコートの上でぶつかり合い、試合はなおも続いていった。
沼を沈める
第2セット終盤。
観客は総立ちだった。
ヴォルフは足を引きずりながら、それでも返し続ける。
声は枯れても、目の奥にはまだ火が残っていた。
「……俺は沈まん……沈むのは、いつも相手の方だ……」
低い声がネット越しに響く。
だが、もう返球は浅かった。
九条は一瞬の隙を逃さない。
ベースライン際に鋭いフォアを突き刺す。
ヴォルフが必死に伸ばしたラケットは、ボールに届かない。
審判の声がコートに落ちた。
「ゲーム、セット、マッチ――九条」
スタジアムが割れんばかりの歓声に包まれる。
ヴォルフは膝に手をつき、荒い息を吐きながらも立ち上がった。
ネットへ歩み寄り、握手を求める。
その顔に、まだ負けを認めぬ強情さが滲んでいる。
「……氷は砕けなかったか。だが――いつかひびは入る」
九条は無言で手を握り返した。
氷の瞳は揺るがず、ただ次の獲物を見据えていた。
――インディアンウェルズ準々決勝。
“沼”を沈め、“氷”はさらに研ぎ澄まされた。
試合後の控え室
控室に戻ると、空気は熱を帯びながらも落ち着いていた。
九条がタオルを肩に掛けて入ってくると、チームメンバーが自然と視線を向ける。
蓮見は資料から顔を上げ、短く言った。
「……長い試合だったな。だが、最後はお前が相手の粘りを削り切った。修正の速さは評価できる」
氷川は腕を組んで頷いた。
「観客の空気もあったが、飲まれなかった。それが何よりです」
志水は淡々とメモを確認し、
「疲労はあるが、回復可能な範囲」と報告する。
一方で、レオンはペットボトルを手渡しながら穏やかに笑った。
「いやー、“沼”相手にあれだけ冷静でいられるの、恋してる人間にしては上出来でしょ」
九条は眉をひそめ、受け取った水を無言であおった。
「おい、レオン」
蓮見が低く咎めるように言うが、レオンは肩をすくめる。
「だって本当のことだろ? 氷が溶けかけた瞬間、ちゃんと固まった。……澪ちゃんが見てたら拍手してたと思うよ」
九条は言葉を返さず、タオルで汗を拭き続けた。
ただその視線の奥には、冷徹さと共に、どこか澪の影がちらついていた。
「疲れただろうし、あとで澪ちゃんに労ってもらってね」
レオンの声は軽口めいて聞こえるのに、響きには揶揄がなかった。
むしろ本当にそう願っているような調子で、彼は九条の背中をポンと叩いた。
九条は振り返らずにタオルで顔を拭い、そのまま黙って水を口に含んだ。
レオンの一言は、冗談に聞こえながらも胸の奥に微かな熱を残す。
“労われる”という感覚自体、九条には長らく無縁のものだったからだ。
控室に静けさが戻る。
その空気を破ったのは蓮見だった。
「――シャワーの後、次の準決勝の相手、確認するぞ」
九条は水を飲み干し、ペットボトルをテーブルに置いた。
削りたての氷のように整った眼差しが、次の戦いに向けられていた。
次の相手
シャワーを浴び終えた九条がバスローブのまま部屋に戻ると、すでにチームの面々が集まっていた。
テーブルの上にはタブレットが置かれ、そこには直前の準々決勝の結果が映し出されている。
Lucas Eriksson def. [対戦相手]
準決勝のカードが確定していた。
「決まったな」
蓮見が低く告げる。
「次の相手は――ルーカス・エリクソンだ」
その名前が出た瞬間、部屋の空気が変わった。誰も表情を崩さない。ただ、全員の意識が一点に収束する。
志水が映像を止め、画面を指さした。
「フットワークは軽い。だが三十球を超えるラリーでは着地が乱れる。腰に負担が出るのは明らかです」
早瀬が横から補足する。
「右足首の癖もある。後半は必ず軸がぶれる。そこまで持ち込めれば勝機は見える」
氷川はノートを閉じ、淡々と言った。
「観客は彼に寄るだろう。声援を燃料にする選手だ。だが苛立ちも激しい。長くなれば感情が揺れる。その瞬間を逃さないことだ」
神崎が静かにグラスの水を持ち上げる。
「持久戦を覚悟してください。呼吸と水分補給の間隔を必ず意識すること。体力面は万全でも、長引けばリスクは増える」
藤代が腕を組んだまま短く続ける。
「スタンドは騒がしくなる。外乱は俺が遮る。お前は試合だけを見ていろ」
言葉が一巡し、視線が九条に集まる。
九条は椅子にもたれかかり、しばし目を閉じた。
やがて口を開く。
「……打たせる。削る。苛立たせて、終わらせる」
その一言に、誰も反論しなかった。
戦うべき相手の姿が、全員の中で鮮明になっていた。

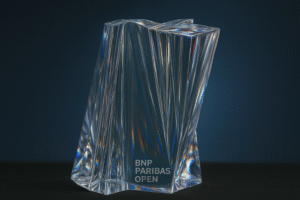





コメント