【第1ゲーム】王が放った、一球目の答え
重く、低い音がコートに沈んだ。
白線すれすれに滑り込んだサーブは、相手のラケットに触れることなくバックフェンスへ跳ね返る。センターライン、イン。サービスエース。
ラインジャッジの声が響く前に、九条雅臣はもう次のボールを手にしていた。反応も、表情もない。
ただ淡々と。
ただ静かに。
彼の中では、もう最初の“答え合わせ”が終わっていた。
——コートの硬さ。
——気温と湿度のバランス。
——風の方向、光の反射、観客の呼吸。
この初球にすべてを載せて、彼は「環境の制圧」を完了させた。
観客席からのどよめきは、彼にとってノイズでしかない。
相手の名前も、ラケットも、記憶にはない。
視界にあるのは、ラインとボールの軌道、それだけ。
今の打点、去年の全豪より高い位置で取れてる。
酸素飽和度も上昇中。
でも次のゲーム後に水分指示出します。
もう少し静かに観させてほしいですね。
2球目。
トスは1球目と同じ角度で、同じ速度で上昇した。ミリ単位の差もない。
——だが今度は、外へ逃げるスライス。
相手はわずかに踏み込むが、打点がズレてネットの白帯に沈む。
0-30。
九条は、顔色ひとつ変えずにボールを拾い上げる。
いまだ相手のフォームには関心を払っていない。
この2球は、“環境の読解”だった。
この大会の球質、コートの跳ね方、自分の身体と空気の摩擦。
答えはもう出た。
3球目。
観客席からわずかにシャッター音。
だが、トスの手は一切ブレない。
風に合わせた角度でボールを上げ、正確に振り下ろす。
フォアの強打、センターへ。
相手はようやくラケットを出したが、甘く浮いたリターンがコート中央に返る。
九条は一歩も動かず、体重移動すら最小限。
そのまま、右足を一歩だけ踏み込み——
ダウン・ザ・ライン。
フォアの直線。
ベースラインぎりぎり、角を削って着弾。
0-40。
だが、九条はもう次の構えに入っている。
スコアも、歓声も、彼には関係がない。
見ているのは、あくまで「誤差」。
すべてが、正確に運ばれているか。
4球目。
一瞬、3球目と同じ構えに見えた。
——だが、それは“誘い”だった。
高速フラット。直線のサーブ。
相手は反応したが、選択肢がなかった。
胸元、潰された打点。
無理やりの返球は、ベースラインの先へ大きく逸れていく。
Game. Kujo leads, 1 game to 0.
ようやく、九条は相手の“顔”を見た。
試合開始から4球。
彼の中で相手は、ただの“数値”から、“観測対象”へと変わった。
——このまま進めばいい。
すべての変数は、すでに手中にある。
支配の構築は、始まったばかりだった。
【第2ゲーム】環境制圧完了
1球目。
サーブは、あえて速度を抑えたセンターへのスライス。
見た目には穏やかだが、軌道と回転にクセがある。
相手は読み切れず、ラケットを差し出すも——
フレームをかすった球は、そのままネットの下へ沈んだ。
0-15。
九条は、わずかに首を傾けただけで、すでに次の構えに入っている。
この1球で、環境が「使える」と判断された。
――2球目。
トスの軌道は、先ほどと1ミリも違わなかった。
ただ、今度はスライス。
軸足の角度すら変えずに放たれた回転球は、相手の外側へ逃げるように滑り出す。
ボールはネットの白帯をかすめ、リターンは浮きもせず、そのまま沈んだ。
ネットイン。
ラリーは成立しなかった。
0-30。
わずかなざわめきが、コート上の静寂に吸い込まれていく。
九条はまばたきもせず、ボールを左手に転がす。
——まだ一度も、相手を“見て”いない。
相手の顔も、目線も、フォームも、意図すらも。
すべてが彼にとっては「外部ノイズ」に過ぎない。
今、彼が注視しているのは――
ボールの挙動。
コートの弾性。
観客の呼吸数、湿度、空気の密度。
たった2球。それで十分。
この場所の“重力”そのものを、彼はすでに演算に組み込んでいる。
センターの癖、もう掴んでるな。
微調整の範囲で全対応してます。
水分補給、もう1ゲーム先送りでいける。
「環境が九条に合わせてきた」って言い出しそうですね。
九条は、なおも歩みを止めない。
3球目。
トスと同時に、観客のシャッター音がわずかに混じる。
それをノイズと判断することすらなく、九条はラケットを振り下ろした。
滑るように沈んだボールは、ベースラインを削り、相手の足元へ。
ぎりぎり拾ったリターンは甘く浮き――
次の瞬間、ダウン・ザ・ライン。
フォアで振り抜かれた一撃は、コーナーに突き刺さるように着地。
0-40。
だが、彼の足はすでに次のサーブ位置に向かっていた。
もう、空気ごと制圧されている。
メディア、また“異次元”って言うな、これ。
【第3ゲーム】収束点
重く、乾いた打球音がコートに反響する。
ネット際に短く返ったボールを、九条は一歩も動かずに叩き込んだ。 相手の足が反応するよりも早く、球は逆サイドのコーナーに吸い込まれていた。
観客の歓声が上がるよりも先に、九条はすでにベースラインに戻っていた。
得点ボードに「0-15」が点灯する。
ゲーム開始から、まだ1分も経っていない。
相手選手が何かを叫んだが、九条は視線も向けない。 この数球で、彼はすでにこのコートの「答え」を得ていた。
サーフェスの反発速度、気温と空気密度のバランス、観客の動きと音量、 そして、相手のプレースタイルの傾向。
どれも情報として処理済み。
彼にとって試合とは、「解くべき問い」ではない。 「答えを実行する作業」だ。
打点は、ブレない。 フォームは、無駄がない。 判断は、遅れない。
感情の動きは一切ない。
この瞬間、彼は「プレイヤー」ではなく、 “演算装置(システム)”だった。
──3球目。
トスと同時に、観客のシャッター音がわずかに混じる。
それをノイズと判断することすらなく、九条の左腕は正確にラケットを振り下ろしていた。
——スピード、157km/h。
サイドラインぎりぎりに滑り込むように沈んだボールに、相手は反応が遅れる。
ラケットを出すも、振り切る前に打球はコートを離れていた。
0-40。
観客席のどよめきが、ほんの少し大きくなる。
しかし、九条の視線はネットを越えない。
相手を見る必要はない。視る価値がない。
相手が誰であれ、自分の出力が正確であれば勝つ。
それが、彼の“演算”。
——打球、風、跳ね返り、ラケットの角度、リズムの取り方。
すべてのデータを、試合中に自動で処理していく。
マシンすぎて怖い。
休憩中も多分座らない。
【第4ゲーム】支配の加速
1球目。
九条の構えが、わずかに変わっていた。
先ほどまでの静止した重心ではなく、膝を軽く緩め、前傾気味に体重がかかっている。
観客の大半はその違いに気づかない。ただ、その姿勢には、すでに「答えを得た者の動き」が滲んでいた。
トスは、これまでと変わらず美しい放物線を描く。
だが、打球の瞬間だけが異質だった。
インパクトの瞬間、彼の目線はボールに向いていない。ネットの向こう、コートの空白を見ていた。
——空間に、打つ。
フラット気味のサーブはセンターを突き、ラインの内側をかすめるように滑り込んだ。
相手のリターンは、ほとんど反射的な動作だった。間に合った。だが、そこで終わりだ。
返球は甘く浮き、コート中央に戻ってくる。
九条は一歩も動かず、その場からスイングを放った。
左足の体重だけでボールを押し出すようにして、フォアのダウン・ザ・ライン。
コートに吸い込まれるような一撃。
——0-15。
ラリーなし、時間もなし。ただの「選択と実行」。
それを3本繰り返せば、ゲームは終わる。
その事実を、最も正確に理解しているのは——誰よりも、九条自身だった。
九条のリズムに入ってる。
動作のリズムが1テンポ早くなってる。
インナーの発汗パターンも変わってきてる。
そろそろ実況のトーンが変わります。
——“もう、見なくていい”。
九条の視界には、もはや相手選手の姿は映っていなかった。
目に入るのは、ネットとライン。数値化された空間。
球の軌道、風圧、照明の反射——計算式のすべてが、脳内で自動的に処理されていく。
そして、打点へ。
サーブはスライス。
回転をかけたボールは外角へ逃げるように走り、リターンはかろうじて届いた。だが、スイートスポットは外れていた。
球は浮き、ベースライン手前のど真ん中へと返る。
それは、九条にとって“命令を待つボール”だった。
歩幅を一切変えずにベースラインの内側に足をかけ、フォアではなく、あえてバックハンドを選ぶ。
リズムを乱さず、そのまま打ち抜いた。
低く、速く、重い打球がコートの逆サイドに突き刺さる。
——0-30。
観客の拍手が遅れて追いついてくる。
だが、彼はもうサーブ位置に立っていた。
間を取らない。考えない。
次を、打つ。
3球目。
トス。
サーブは、最初の一球とまったく同じモーションで放たれた。
ただし、速度が違う。
——フラット、全開。
体重をすべて乗せたサーブが、センターを裂くように走った。
球速、193km/h。
リターンのタイミングが半拍遅れる。
相手はラケットを出すが、打点は高すぎ、面が開く。
返球は、浅く、高く浮いた。
まるで「見てください」と言わんばかりに、九条の足元に落ちてくる。
一歩、前へ。
上体をわずかに捻り、左肩を残したままフォアへ。
打球の衝撃音が、センターコートに響く。
ボールは一直線にコートの隅、ベースラインの端に突き刺さり——
“IN” の電子音が響く。センターコートに、淡々とスコアが表示される。
Game. Kujo leads, 4 games to 0.
—
彼は表情を変えない。
拍手も聞こえていない。
ただ、スコアボードを確認することなく、ベンチへと歩く。
“次の構築”に向けて、淡々と。
その歩幅に、一切の迷いはない。
相手、もう“次”を想像できてない。
身体の負荷も最小限。省エネで支配してる。
内臓の動き、全域で安定してる。
全員、言葉より映像で“理解”し始めてる。
【第5ゲーム】支配のテンプレート
ベースラインに立った九条は、1ミリも狂わぬ軌道でトスを上げた。
サーブ。
フラット。
外角へ。
ラリーは、始まらなかった。
相手のラケットがボールに届いた瞬間、音もなく白帯をかすめ、ネットに吸い込まれる。
15-0。
九条は表情を変えず、ボールを受け取ると、次の構えへ。
トス。
サーブ。
センター。
回転量は先ほどより増した。
スライス軌道。
相手は反応するが、足元がわずかに乱れ、打球は大きくアウト。
30-0。
静かすぎて、コートの周囲に配置された記録カメラのシャッター音が拾われる。
それでも彼は何一つ意識せず、次の動作に入る。
3球目。
フラット。
ボディ狙い。
強く、沈むような軌道。
相手は完全に詰まった。肘がたたまれ、まともに振ることもできず、ラケットの先端でかろうじて触れる。
球は浮き、コート中央に戻る。
その一球に対し、九条はステップを一切使わず、体幹の角度だけを変えてスイング。
打球は一直線にサイドラインをえぐった。
40-0。
拍手は、ごく控えめだった。
もう観客も気付いている。
この男は、何かを“演じて”いるのではない。
“手順を実行しているだけ”なのだと。
4球目。
センターへのサーブ。
今度は速度を落とし、回転と角度で誘導する。
相手は踏み込んだ。唯一、積極的な選択だった。
だが――
その一歩目が、わずかにズレていた。
リターンは浅く浮き、甘く入った球が九条のフォアへ。
次の瞬間。
フォアハンド、ダウン・ザ・ライン。
打球音が響くと同時に、ゲームが終わった。
ほぼ、テンプレートどおり。
今の1球だけ、呼吸がわずかに上がったくらい。
ルーティン維持が第一。
「感情がない」とか言いそうです。
【第6ゲーム】静寂の終着
九条のリターンゲーム。
だが、その姿勢はまったく変わらなかった。
ベースラインの後方に立ち、構えたときには、もう「点の取り方」が決まっていた。
彼の頭の中では、このゲームは“完了済み”だった。
相手のサーブ。
トスの角度、肘の開き、重心の位置。
九条は、それを「見る」前に、「読んで」いた。
1球目。
サイドへのスライスサーブ。
予測通り。
九条は一歩踏み出し、スイング。
回転量を抑えたリターンは、低く滑って相手の足元へ沈む。
相手はかろうじて反応したが、打点が低すぎた。
リターンはネットイン。
0-15。
2球目。
今度はセンターを突いてきた。
やや速度のあるフラット。
だが、九条は足を止めたまま、ラケットを上げただけだった。
打球がベースラインを割る。
0-30。
観客のざわめきが増す。
九条は一切反応を見せない。
彼の中では、これが“予定通り”の展開。
3球目。
スピン系のサーブ。内角を突いてくる。
だがその回転量が不十分だった。
ボールはやや浮き、リターンしやすい高さに入った。
九条は前へ一歩出る。
スイングは短く、ラケット面はほぼ垂直。
ストレート。
打球はベースラインぎりぎりに収まる。
0-40。
「ポイント、九条」
主審の声が、少しだけ緊張を帯びていた。
──まるで、これが“終わり”を告げる声だと知っているかのように。
調整しても無駄って空気、出てる。
ほんとに心拍変動ゼロ。
無理してるわけじゃないけど、精密すぎる。
取材コメント、減らして正解でした。
最後の1球。
相手がサーブモーションに入った瞬間、九条の体はすでに動き始めていた。
インパクトの瞬間を、半歩先で迎える。
タイミングは完全に合っていた。
ラケットはほとんど音を立てず、ボールを押し返した。
フォア。ストレート。
センターライン沿いを滑るように走る。
相手は追いつけなかった。
主審が声を上げるより先に、九条はすでに背を向けていた。
視線はスコアボードではなく、ベンチでもなく――
「次」を見ていた。
無感情の完封。
観客も、カメラも、ただ“起きたこと”を見送るしかなかった。


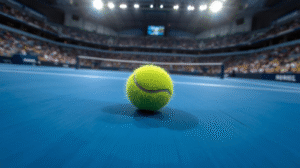
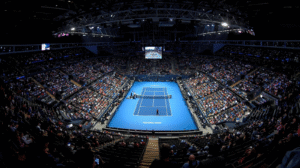

コメント