「止まらない支配」
第2セットが終わった瞬間、スコアボードには「6-0」の文字が並び、観客席からようやく拍手が広がった。
だが、そのざわめきすらも、九条雅臣の足を止める理由にはならない。
彼はベンチに戻らない。
タオルにも、水にも、視線を送らない。
その背筋は伸びたまま、ただ静かにベースラインの端に立っている。
まるで——セット間の休憩時間すら、「試合の一部」として演算に取り込んでいるように。
スタッフの誰もが知っている。
彼にとって、“休憩”という概念は存在しない。
この2分間もまた、「支配の中継時間」に過ぎない。
身体は動いていなくても、思考と演算は止まらない。
目には何も映っていないように見えて、その実、彼はコート全体の“未来”を走査していた。
観客が飲み物を取りに立ち、実況が次の解説に切り替わっていく中で——
九条雅臣だけが、まだ“中にいる”。
静かに。確実に。
「次のセット」は、すでに彼の中で始まっていた。
【第13ゲーム】「shutdown」
最初のサーブが入った瞬間。
相手のラケットは動いた。だが、遅かった。
いや、“動かないほうが正解だ”と、どこかで思ってしまったような、そんな半端な一歩だった。
結果、返球はラインを割る。
(15–0)
ベースラインに戻る九条雅臣の背中は、まるで“命令を終えた装置”のようだった。
静かで、正確で、迷いがない。
もう、感情での対話は終了している。
音も、視線も、気配も——届かない。
相手の身体に宿っていた「戦う意志」は、このゲームの最初の一撃で、“シャットダウン”された。
次のポイント。
サービスラインの内側に落ちる浅いリターン。
九条はただ一歩踏み出すだけで、それを叩き込む。
角度、軌道、スピン、速度——すべてがシミュレートされた“処理”だ。
(30–0)
あれ、もう“選択肢がなかった”って顔してる。
完全に指令信号が遅れてる状態です。
“戦闘意識”じゃなくて、“自律的停止”の領域。
……ちょっと異様な空気ですね。
3ポイント目。
相手がドロップを試みた。
精度は悪くない。
でも——九条は、ネットに近づきすぎず、“そこに来る”と決まっている空間にだけ視線を送った。
あとは、そこへ足を運び、スライスで沈めるだけ。
(40–0)
そして、ラストボール。
サーブ。
スピードは出ていなかった。
だが回転とコースが、まるで“存在しないルート”を通ったように消える。
相手は——反応すらしなかった。
棒立ち。
ボールが跳ね返る音だけが、センターコートにこだまする。
Game. Kujo leads, 1 game to 0.
【第14ゲーム】「静かな終末予告」
時計の針は、まだ9:20を少し過ぎたばかり。
けれどこのコートの“時間”は、とうに止まっていた。
観客のざわめきも、カメラの動きも、どこか遠くから聞こえるだけ。
九条雅臣の内側では、すでに「終わり方」の演算が完了していた。
1ポイント目。
相手が出したリターンは、甘かった。
バウンドも浅く、スピンも弱い。
けれど、九条は叩かなかった。
ただ一歩、足をずらし、角度を作って──
バックのスライス。ネットの白帯すれすれに滑らせる。
相手は動かない。
違う、動けなかった。
(15–0)
ラケットを構えてはいるが、目線に“追う意思”がなかった。
どこか遠くを見るような、投げ出すような視線だった。
2ポイント目。
今度は、わずかに粘った。
しかし、5往復目には完全に押し込まれ、体勢が崩れる。
ラリーを終わらせたのは、九条の一撃ではない。
“選ばなかった”一手だった。
ストレートを打てる位置に立ちながら、
あえてクロスに、ゆるやかに逃がす。
——つまり、見逃させた。
相手の足は、そこで止まった。
(30–0)
無理に追わせて壊すよりも、
“追わせない”ことで心を止める。
それが、九条雅臣のやり方だった。
3ポイント目。
構えに入った時点で、もう誰もが理解していた。
──これは、終わる。
サーブはセンター。回転も速度も、過不足ない一球。
相手は動いた。足も、腕も、しっかり反応していた。
けれど、リターンはラインを大きく逸れた。
打つ瞬間、目を閉じたのが見えた。
(40–0)
静寂。
九条は、ほんの一瞬だけ空を見た。
スコアボードも見ず、観客も見ず。
そのまま、最終スイングへ。
ラリーは3往復で終わった。
乾いた打球音。遅れて響く歓声。
だが、彼の背中はすでにベースラインへと向いていた。
あれ、もう“選択肢がなかった”って顔してる。
完全に指令信号が遅れてる状態です。
“戦闘意識”じゃなくて、“自律的停止”の領域。
……ちょっと異様な空気ですね。
【第15ゲーム】「絶対精度の継承」
開始の合図と同時に、九条雅臣の動きが再開される。
だがそれは、“始動”ではなかった。
もうすでに“稼働中”だった何かが、ただ次の命令を実行しただけ。
スイッチもなく、判断もない。ただ、処理。
1ポイント目。
相手のサーブ。速度はある。コースも悪くない。
だが、打点は読まれていた。
九条はほんの一歩、右足をずらすだけでリターンポジションに入る。
インパクトは、0.1秒もズレない。
フォア、ストレート──ライン際へ突き刺すような一撃。
(0-15)
反応する隙もなかった。
相手の目が、視線で「どうして」と訴えていたが、
九条はその目を、**“存在していないかのように”**見なかった。
2ポイント目。
わずかに球足を遅らせたサーブに、タイミングをずらされる選手も多い。
だが九条は違う。
「ずらし」そのものを先に演算していた。
スイング開始までの“沈黙”を長く保ち、最終動作だけで速度と方向を修正。
そしてまた、フォア。
今度は角度をつけて、浅く狙う。
(0-30)
——音が、ない。
コートには確かに球が飛び交っているのに、
打球音も、歓声も、脳に届いてこない。
まるで「今」という瞬間が、九条にとっては再生されるだけの記録になってしまっているかのようだった。
3ポイント目。
今度は、わずかに足が乱れた相手がクロスへ逃げる。
構えを崩すフリだけして、逃げのラリー。
だが、それすら計算に入っていた。
九条はステップを踏まず、体幹だけで打点に合わせた。
リズム、完璧。
距離、完璧。
球速、完璧。
(0-40)
——3球とも、異なる角度。異なるテンポ。異なる配置。
それなのに、精度はすべて**「同一」**だった。
最後のポイント。
観客はもう、立ち上がるタイミングを見失っていた。
拍手もない。歓声もない。
ただ、九条雅臣が**“記録された演算”**を忠実に再生する時間が流れていた。
相手のバックに打たれたスピン系の球。
九条は一歩も動かず、ラケットをそっと合わせた。
球が浮く。ストレートに入る。
(GAME KUJO)
その瞬間、まばたきをした。
試合中、何度目のまばたきだろうか。
空気が少しだけ、揺れた。
だがそれは、“変化”ではなかった。
更新。
次の構造への、静かな合図だった。
1球ずつ、“設計図どおり”って感じだ。
対応する必要すらない。**再現だけで勝ってる**。
無理してないどころか、“何もしてない”レベル。
書いても“同じ”になっちゃうから。
【第16ゲーム】「終局への引力」
球を打つ前から、もうすべてが“定まっている”ようだった。
相手がどちらに動こうと、何を打とうと——
それは九条雅臣の中では、すでに“過去”になっていた。
1球目。
サーブはセンター。速度はわずかに落としている。
だが、それすら“設計通り”。
相手は一瞬、フォア側に動きかけた。
だが、躊躇のあとで踏み直す。打点がズレる。
打球はネットを越えるも、高く甘いボール。
九条は、動かない。
体の軸だけで捻り、バックのクロスへ静かに押し込む。
(15−0)
——動いていないのに、すべてが“動かされた”ようだった。
2球目。
今度は相手のサーブ。スライス気味に外へ逃がす。
だが、九条はそこに“吸い寄せられる”ように歩を進める。
打点に入るのが早い。
タイミングを遅らせて、逆クロスへ。
カウンターというより、“未来予測”。
(30−0)
観客席から、小さな息を呑む音が聞こえた。
誰もが、もはや勝敗ではなく——
「いつ終わるのか」を、ただ見守っていた。
3球目。
相手の1stサーブはネット。2ndも守りに入ったスピン系。
九条はまるで“捨てられた選択肢”を拾うようにして、前に出た。
ストレートに構える素振りで、急に角度を変える。
相手の視線は完全に逆を向いていた。
球は、誰にも触れられることなくライン際へ。
(40−0)
この時点で、会場に緊張感はなかった。
あるのは、ただ静かな重力。
逃れられない「終局」の気配。
4球目。
サーブの構えに入った相手のラケットが、少しだけ揺れる。
それは、迷いではなかった。
「諦め」と言えば語弊があるが、もはや“抗いようがない”という表情だった。
——結果は、見えていた。
トス。インパクト。リターン。
そのすべてを、九条は半歩先で待ち構えていた。
短く浮いた球を、無駄のないフォームで打ち抜く。
フォア。斜めの軌道。コーナーぎりぎり。
“音”はなかった。
ただ、主審の「Game Kujo」の声が、空気の中にゆっくりと沈んでいった。
【第17ゲーム】「最後の演算」
打点にブレはない。
歩幅にズレもない。
ラリー中、呼吸の乱れすらない。
ここまでのすべてが、最後のこのゲームに向かって“設計されていた”のだと思わせるほど、九条雅臣の動きには一切の無駄がなかった。
——それは、支配の最終段階。
1球目。
サーブはセンター。相手は一瞬、読みを外された顔をした。
けれど読めていたとしても結果は同じだっただろう。
球はライン際で跳ね、ラケットには触れたが、打球はコート外へ逸れる。
(15−0)
スタンドから、わずかに拍手。
けれどその音も、すぐに沈む。
2球目。
わざと“同じトス”から、違う球種。
九条はスライスで外へ逃がす。
回転量がえげつない。
相手は足元でバランスを崩し、スイングの途中で止めてしまう。
ラケットの先が、空を切った。
(30−0)
観客は静まり返っている。
いや、“静かに見届けている”という方が近い。
もう誰も、「勝負」を見ているわけではない。
見ているのは、“九条雅臣”という演算体が最後に出す「答え」だった。
3球目。
相手のリターンは、意地の一打だった。
クロスへ鋭く打ち込まれる。
だが九条は、読むどころか“すでにそこにいた”。
ステップはゼロ。
肩だけをひねり、ラケットを逆サイドへ差し込む。
カウンターではない。演算の“上書き”。
相手の打球は、より正確な“答え”に書き換えられていた。
(40−0)
ラストポイント。
彼は構えながら、ほんの一瞬だけ空を見た。
その視線に、誰も気づかない。
けれど彼だけがわかっていた。
これが、“この試合最後の命令”だと。
トス。インパクト。
相手のラケットが触れるより先に、
ボールは地面を滑り、白線に吸い込まれた。
その瞬間、観客の誰もが、心の中で言った。
(終わった)
だが、九条はまだネットを見ていた。
相手が何か言いかけたのを、音として認識することなく。
ただ、ベースラインに静かに背を向ける。
彼の“最後の演算”は、もう終わっていた。
【第18ゲーム】「記録装置の終幕」:完全なるシャットダウン
その瞬間、コートには“時間”が存在しなかった。
観客の息づかいも、実況の声も、風の揺らぎも。
すべてが“止まっていた”。
そして、たった一人。
九条雅臣だけが、動いていた。
1球目。
リターンゲーム。
相手のサーブは、わずかにスピードを増していた。
けれどそれは、最後の抵抗ではなかった。
ただの“逃避”だった。
九条はステップを踏まず、視線だけで軌道を掴む。
ラケットを振るというより、そっと“置いた”。
それだけで、球はコートの奥深くに吸い込まれる。
(0−15)
人間じゃない。静かすぎる。
コマンド実行中っていうより、“保存モード”に入ってる。
多分これ、本人の中ではもう試合終わってる。
この空気、メディアは書けないかもね。言葉が追いつかない。
2球目。
相手が攻めに出た。
だが、無意味だった。
その一歩目が“計測可能”になった時点で、九条はもう読み切っていた。
体重移動を使わず、軸だけで返す。
重く、鋭く、冷たい打球。
(0−30)
3球目。
フェイクを挟んだ。
一度、わざと“反応が遅れたふり”をする。
相手が踏み込む。
強打。コートの端を狙ったショット。
だが、九条の足はそこにあった。
読みでも、反応でもない。
“最初からそこにいた”。
静かなカウンター。
(0−40)
セットポイント、マッチポイント、そして“記録の終点”。
4球目。
相手のサーブはセンターへ。
ラケットが振られるより早く、九条は動いていた。
打球は、スライス。
だが、それは“切り札”ではない。
もう、ただの「記録処理」。
観客はそれを理解していた。
打球音は、静かだった。
ネットの振動すら、聞こえなかった。
コートの奥、白線の角に、最後の球が着弾する。
その瞬間、スコアボードが更新される。
試合終了。
だが、拍手が遅れる。
誰も、“終わった”という実感がない。
ようやく音が戻ってきたとき、
それは波のように静かに広がった。
そして、九条雅臣は、
ただ、静かにラケットを下ろした。
誰も見ていない場所を見ながら、
彼は、次の“演算”へと進んでいた。


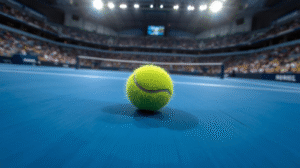
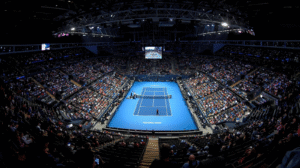

コメント